慢心でダメにしたぬか床を復活させる。
ヨメが専業主婦だった頃やっていたぬか漬け。今は保育士としてバリバリ働いておりそんな暇はありません。逆に私は早朝出勤で早夕帰宅。スーパーで買い物をして夕飯を作るのが私の役割です。
どれどれ。主婦のすなるぬか漬けといふものを旦那もしてみむとすなり。やってみるべか。
ヨメが仕舞い込んでいた陶器のぬか床容器を取り出し、ネットを見ながらぬか床を仕込みます。ふむふむ。そして一ヶ月もすると美味しいぬか漬けが出来るようになりました。
やはりぬか漬けは人の想いが味となるのだ。私が作るぬか漬けが美味しくないわけがない。ほほほ。そのような慢心。あまり上手く行き過ぎると人は興味を失い慢心してしまう。
記録的な猛暑が続いた日。慢心と飽きで手入れをしなかったぬか床はすっかり黒いカビとクッチャイ腐敗臭の床になっていました。
ヨメ「ありゃ〜。こうなったらもう捨てて新しく作り直すしかないね。」
でも捨てるのは抵抗あります。私の慢心でダメにしてしまったぬか床。何とか復活させられないか。
何をやっても効果なし。やはり一度捨ててやり直すしかないか。
ネットを見ながらいろいろ試行錯誤しますが、やはりダメです。むむむ。そこから数ヶ月。私は毎日「まずいぬか漬け」を食べ続けることになる。なんか粉っぽい糠風味のコクも何もない漬物。
ぬか漬けは毎日付けないと復活しない。しかし出来る漬物はまずいのでヨメには出せない。だから私がそのまずいぬか漬けを食べる。うむむ。まずいなあ。(T_T)
ぬか床はいかに糠の中の植物性乳酸菌を増やすか。もうこれに付きます。
腐敗臭のするぬか床にヨーグルトを入れたい衝動にかられますが、ヨーグルトは動物性乳酸菌なので入れてはダメのようです。あぶないあぶない。
植物性の菌ならいいだろう。と塩麹をいれてみました。確かに臭いニオイは軽減されますが、漬物の味はいまいちのまま。やはり麹菌と乳酸菌は別物。ぬか床のメインは乳酸菌なのです。
昆布はぬか漬けの味の旨味を深めますが、それも乳酸菌がきちんと培養された状態でのプラスアルファ。きちんとぬか床が培養されないうちは意味がありません。
鰹節は動物性なのでぬか床にはいれません。ヨーグルトを入れないのと同じ理由。ぬか床はあくまでも植物性の菌の床であります。男子禁制みたいなものですな。植物と植物性菌の培養の館であります。
ネットでは「カゴメのラブレ(植物性乳酸菌サプリ)」をぬか床に大量にいれたらぬか床が復活した。という記事もありました。しかし費用がかさむと。うむむ。もっと自然の力で復活させたい。
乳酸菌漬けで乳酸菌を培養する。
そんな時乳酸菌漬けの記事を発見しました。このブログで何度も紹介している記事ですが再掲します。
乳酸菌と食物繊維を一度に おいしい!乳酸発酵漬け
日経スタイル 2018/4/20
・・・
「乳酸発酵漬け」に必要なのは、野菜と水、そして塩だけ。この割合さえ守れば、塩分控えめの浅漬けのような風味に仕上がる。
乳酸菌をしっかり増やし、発酵を成功させるポイントは2つ。
1つ目は、「塩水をたっぷり注ぐ」こと。材料がひたひたになるまで塩水が注がれていることが重要だ。「野菜からしっかり糖などを浸出させるためにも、塩水にはしっかり浸すこと。野菜の表面が空気に触れていると、カビが生える一因にもなる」(宮尾教授)。
2つ目は、白濁し始めるまでは冷蔵庫に入れず、「室温で保管する」こと。今の時期であれば、1~3日前後で漬けた汁が白く濁り始め、プツプツと泡がでることもある。これは、発酵が進んで、「炭酸ガスをだす乳酸菌が増えるため」(宮尾教授)だ。
白濁が全体に広がって、なめて酸味を感じるころには、酸っぱい香りも漂うようになる。そうなったら食べごろ。室温から冷蔵庫に移し、1カ月以内に食べきろう。
・・・
「乳酸発酵漬けに使う塩水の基本は、水1カップに塩小さじ1。作りたい量が少量でも大量でも、この方程式で塩分を調整すれば失敗しません」(萩野さん)。野菜が水に浸りきらない時などもこの割合で塩水を作って足せばいい。塩分濃度は約3%。
・・・
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO29259110R10C18A4000000/
日経スタイル 2018/4/20
・・・
「乳酸発酵漬け」に必要なのは、野菜と水、そして塩だけ。この割合さえ守れば、塩分控えめの浅漬けのような風味に仕上がる。
乳酸菌をしっかり増やし、発酵を成功させるポイントは2つ。
1つ目は、「塩水をたっぷり注ぐ」こと。材料がひたひたになるまで塩水が注がれていることが重要だ。「野菜からしっかり糖などを浸出させるためにも、塩水にはしっかり浸すこと。野菜の表面が空気に触れていると、カビが生える一因にもなる」(宮尾教授)。
2つ目は、白濁し始めるまでは冷蔵庫に入れず、「室温で保管する」こと。今の時期であれば、1~3日前後で漬けた汁が白く濁り始め、プツプツと泡がでることもある。これは、発酵が進んで、「炭酸ガスをだす乳酸菌が増えるため」(宮尾教授)だ。
白濁が全体に広がって、なめて酸味を感じるころには、酸っぱい香りも漂うようになる。そうなったら食べごろ。室温から冷蔵庫に移し、1カ月以内に食べきろう。
・・・
「乳酸発酵漬けに使う塩水の基本は、水1カップに塩小さじ1。作りたい量が少量でも大量でも、この方程式で塩分を調整すれば失敗しません」(萩野さん)。野菜が水に浸りきらない時などもこの割合で塩水を作って足せばいい。塩分濃度は約3%。
・・・
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO29259110R10C18A4000000/
そこを捨てるのは勿体ない。
キャベツにはたくさん乳酸菌がついていると言います。スーパーではキャベツの外葉を捨てて持っていく人がいますが、もったいない。しっかりと洗う必要はありますが、キャベツの外葉は炒めると美味しいんですよ。チャーハンでもパスタでも。あるいは味噌汁でも。
そのキャベツの外葉を使って乳酸菌漬けを作ります。本当にカンタンに漬かります。
白濁した液。なめると酸味がある。これこそ乳酸菌。私が数ヶ月ぬか床試行錯誤しても全然増えなかった乳酸菌。それがキャベツの外葉を3%塩水に数日漬けて置くだけで発酵が進んでいく。
そして私はその「乳酸菌漬汁」をぬか床に加えました。そして見事ぬか床が復活したのでした。
ぬか漬けが美味しい理由。
糠に乳酸菌が復活し始めると、次に糠の表面に白い酵母が育つようになります。この酵母が「風味」であります。ぬか漬けが美味しいのは
・漬物の塩味
・乳酸菌の酸味
・酵母の風味
この3つのハーモニーであります。
乳酸菌漬けは、塩味と酸味だけでした。でもぬか床に乳酸菌が増えると、表面に酵母が出来ます。そしてこの酵母を糠の表面から内部に混ぜ込むと、アルコールや脂肪酸などの芳香な成分になるのです。
ぬか床は緩いくらいでちょうど良い。
このようにして復活した我が家のぬか床。毎日酵母がはって美味しい漬物に戻りました。白菜などの葉物も(他の野菜と同じように)塩をまぶしてぬか床につけると、野菜から水がでて、ぬか床が水っぽくピチャピチャになります。
今まではそうなるたびに糠を足していました。しかし乳酸菌漬けのように塩水でもいいくらいなのです。ですからぬか床も水っぽいぐらいの方がちょうどいい。ピチャピチャぐらいが丁度いい。ゆるいぐらいが丁度よい。どうも乳酸菌は(ヨーグルトがそうであるように)水分たっぷりピチャピチャプルンプルンぐらいの方がいい。というのが私の今回で得た経験です。
実践編。
乳酸菌漬けです。キャベツの外葉と今回はえのき茸を塩水につけて常温に2日ほど。昨日は暑いくらいでしたから、もう漬け汁は白濁して酸味があります。

我が家のぬか床。漬物を一度取り出し、

お米屋さんから貰ってきた新しい糠をどそっと足します。

ここに乳酸菌漬汁を惜しげもなくどぼどぼっと漬けます。ちょっと緩いくらいで丁度良い。

よくかき混ぜたら、さきほどのぬか漬けと乳酸菌漬けの野菜を糠にもどします。
一晩置くと表面に白い酵母がびっしり。ぬか床の状態が良いことがわかります。乳酸菌漬けで培養された乳酸菌が糠を養分にしてどんどん繁殖しているということです。よかったよかった。

復活したぬか漬けです。アオサをふりかけて召し上がれ〜。

上記はもう成功しているぬか床に糠を足したので1日で酵母膜が出来ました。初めての方は糠に乳酸菌が馴染むまでにもう少し時間がかかるかもしれませんが。いろいろ試行錯誤なさってください。
乳酸菌漬けで培養した乳酸菌をぬか床に利用する。
新しくぬか床を作る方。あるいはどうもぬか床が上手くいかななという方。
・乳酸菌漬けで乳酸菌漬け汁を作ってから、
・そしてこの漬け汁をぬかと混ぜる。ちょっと緩いかなというぐらいがちょうど良い。
・1日1回は軽くかき混ぜて、表面に白い酵母膜ができれば成功。
というやり方もあります。いかがでしょうか。
おまけ(読者の方によって教えて頂いたこと)
おまけは別便で投稿します。
おまけは別便で投稿します。
本ブログに共感される方はクリックのほどよろしくお願いいたします。
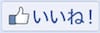
にほんブログ村ランキング
■ブックマーク
備忘録検索(β版)
画像ライブラリ
■防災意識リマインダー
防災に注意が必要な期間は、メールやTwitterで防災意識リマインダーを受け取ることができます。詳しくはこちら
■地震雲写真投稿方法
地震雲(飛行機雲のように短時間で消えない立ち上がる雲)を目撃された方は、雲の御写真と目撃情報を下記のメールアドレスにお送り頂ければ幸いです。
ohisama.maruzo@gmail.com
御写真とともに送って頂きたい情報
・目撃された日時(何日何時頃など)
・目撃された場所(県名や地名など)
・目撃された方向(可能なら)
地震雲かわからない方は地震雲の見分け方をご参考になさってください。
(個人情報は厳重に管理し、私以外の第三者に投稿者のメールアドレスなどの個人情報を開示することはありません。また御写真の画像情報や機種情報は消去いたします。人物が特定できる映り込みなどのぼかし加工もこちらで対応いたします。なおお送り頂いた御写真と目撃情報は関連サイトにも掲載させて頂くことがあります。)
■非掲載希望のコメントについて
1.公開を希望しないコメントは投稿しないでください。基本的に投稿されたものは他の読者の方の目にもふれるとお考えください。
2,どうしても公開されたくないメッセージを送りたい方はメールでお願いします。
ohisama.maruzo@gmail.com
3,ただしメールでお送り頂いた内容に対し、私はメールで返信をお送りすることは一切ありません。一方通行となります。
4,上記のようにコメントは原則公開ですが、炎上つながる場合や個人情報が含まれている場合、読者間での私信コメントは、私の判断で非公開とする場合があります。
■引用転載について
本ブログは引用元をあきらかにしていただければ、ブログやSNSでの拡散は許可いたします。









