本作のロケ地となっているドイツ・ルール地方の工業都市ヴッパータールは、ヴィム・ヴェンダースがかつて『都会のアリス』(1973)でカメラを向けた街だ。「懸垂式」というらしい、千葉都市モノレールのように天井から吊り下がった形のモノレールが、高低のダイナミックな視界と前進/後退移動でもって画面を心地よく活気づけながら、ダンサーたちの超人的な動きに介入していくのを3D眼鏡ごしに眺めていると、「『都会のアリス』をまた見たい」という切ない思いへと、誰もが誘われることだろう。
ヴッパータールのタンツテアターは、本作の “主人公” ピナ・バウシュ(1940-2009)が芸術監督をつとめ、死の瞬間まで情熱をもって指導し続けた舞踊団であり、団員たちは女主人の喪に服し終えたいまも、彼女のレパートリーを一点の曇りもなく演じ、完璧に再現してみせる。 “主人公” がもはやこの世の人ではなく、この映画で “主人公” が踊る勇姿はまったくと言っていいほど見ることができない。それはあくまで「かつて在った」ものである。それでも物事は、その存在の残り香を辿って彷徨うかのように自然に進行していくのだ。これはきわめてヴェンダース的な事態ではないだろうか。
そもそも、昨年ようやく日本公開された『パレルモ・シューティング』も、写真集『Places, strange and quiet』も、この事態がいよいよヴェンダース的生存の根幹を侵食していることを窺わせてはいなかったか。つまり、登場人物の死が映画作家自身の来たるべき死をも暗示しているのである。後者には当然のごとく、ヴッパータールのパノラマ写真が掲載されている(パノラマはヴェンダース写真のシンボル的手法だ)。この街の肌理の中の肌理をも凝視したとき、何かの後ろ姿の影が写っていることがわかるだろう。
ペドロ・アルモドバル『トーク・トゥ・ハー』(2002)の冒頭で、ピナのレパートリー「カフェ・ミュラー」をピナ本人が上演しているのが見られるが、本作ではこの「カフェ・ミュラー」はもちろん、あらゆるレパートリーの断片を、「彼女はもういない」という事実を噛みしめながら、別の誰かが代行する。この代行の先端に何が見えるか。そして、生の芸術というものは、有限的な肉体の死滅を経たのちにどこへ向かい、どこへ去っていくのか。ヴェンダースは、芸術の行き先においても質量保存の法則が適用されうることを、ピナ・バウシュの面影を使って必死に証明しようとしているかのようである。
ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿バルト9他、全国順次公開
http://pina.gaga.ne.jp/
ヴッパータールのタンツテアターは、本作の “主人公” ピナ・バウシュ(1940-2009)が芸術監督をつとめ、死の瞬間まで情熱をもって指導し続けた舞踊団であり、団員たちは女主人の喪に服し終えたいまも、彼女のレパートリーを一点の曇りもなく演じ、完璧に再現してみせる。 “主人公” がもはやこの世の人ではなく、この映画で “主人公” が踊る勇姿はまったくと言っていいほど見ることができない。それはあくまで「かつて在った」ものである。それでも物事は、その存在の残り香を辿って彷徨うかのように自然に進行していくのだ。これはきわめてヴェンダース的な事態ではないだろうか。
そもそも、昨年ようやく日本公開された『パレルモ・シューティング』も、写真集『Places, strange and quiet』も、この事態がいよいよヴェンダース的生存の根幹を侵食していることを窺わせてはいなかったか。つまり、登場人物の死が映画作家自身の来たるべき死をも暗示しているのである。後者には当然のごとく、ヴッパータールのパノラマ写真が掲載されている(パノラマはヴェンダース写真のシンボル的手法だ)。この街の肌理の中の肌理をも凝視したとき、何かの後ろ姿の影が写っていることがわかるだろう。
ペドロ・アルモドバル『トーク・トゥ・ハー』(2002)の冒頭で、ピナのレパートリー「カフェ・ミュラー」をピナ本人が上演しているのが見られるが、本作ではこの「カフェ・ミュラー」はもちろん、あらゆるレパートリーの断片を、「彼女はもういない」という事実を噛みしめながら、別の誰かが代行する。この代行の先端に何が見えるか。そして、生の芸術というものは、有限的な肉体の死滅を経たのちにどこへ向かい、どこへ去っていくのか。ヴェンダースは、芸術の行き先においても質量保存の法則が適用されうることを、ピナ・バウシュの面影を使って必死に証明しようとしているかのようである。
ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿バルト9他、全国順次公開
http://pina.gaga.ne.jp/

















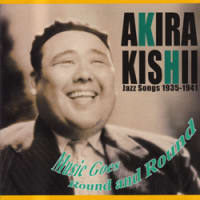


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます