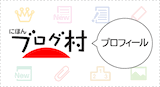200以上300以下の整数の和として正しいものを、次の①〜⑤から1つ選べ。 ①20000 ②25000 ③25250 ④35000 ⑤35250 ボーリングのピンは、なぜ10本なのでしょうか?それは、ボーリングというゲームを作った人がそう決めたからなのです。 しかしながら、そんなことを言い出すと、大坂城を作った人は大工さんたちだと言うことになってしまい、ただの言葉遊びになってしまいます。 ボーリングのピンは、1番手前にピンが1本、手前から2列目に2本、3列目に3本、4列目に4本配置されているではありませんか。つまり、1+2+3+4=10。だから10本です。 僕と同じ年代の人は、20才前後の頃に、ハスラーという映画を見て、ビリヤードをやったはずです。 さて、ローテーションでは、玉の数は、白玉を除くと、1+2+3+4+5=15個ですね。 ですねっていっても、この記事を勉強のために読んでいる皆さんは大変お若いので、知るかよって感じでしょうけど。あるいは、ナインボールの方をするのかな? 話がそれましたが、1〜nまでの全ての整数の和は、次の公式です。
本問の場合は、
ということで、正解は、肢③です。ここをポチッとお願いします。→
にほんブログ村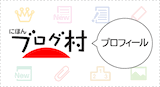


本問の場合は、

ということで、正解は、肢③です。ここをポチッとお願いします。→
にほんブログ村