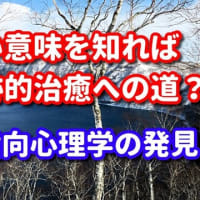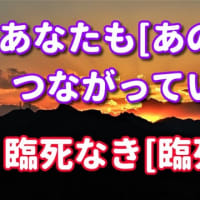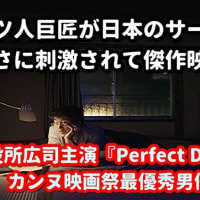瞑想には、止(サマタ瞑想)と観(ヴィパッサナー瞑想)があり、心をひとつのものに集中させ統一させ、サマーディを完成させようとするのがサマタ瞑想だ。たとえば呼吸や数を数えることや曼陀羅に集中したり、念仏に集中したりするのはサマタ瞑想だ。
これに対してヴィパッサナー瞑想は、今現在の自分の知覚や心に気づくというサティの訓練が中心になる。そしてサティをするには、気づいたことに短い言葉を使ってラベリングすることが有効だ。
たとえば寝床に入ったとき、私はしばらく腹の動きにサティし、「膨らみ」「ゆるみ」とラベリングし続ける。そのうち注意が他の対象にそれる。手のちょっとした痒みだったら「痒み」とラベリングしつつサティをいれる。さらに注意がそれて何かを考えていることに気づいたら「思考」とサティを入れて、再び腹の動きへのサティへと戻る。
最近のこうしたヴィパッサナー瞑想を少しづつ復活させている。当然のことだが、ヴィパッサナー瞑想のサティを続けていると心の中の独り言、半ば無意識的な思考が少なくなる。つまり日常的なサティを続けていれば、エックハルト・トールが言うように「思考が注意を独り占めすることがなくなる。思考と思考の間にギャップ、つまりスペース、静寂が生じる。するとあなたは、あなたが思考よりもどれほど巨大で、どれほど深いかということに気づきはじまる。」
かなり長いこと、日常的なサティをおろそかにする年月が続いた。しかし脳内の半ば無意識的な思考こそが「自我」の本体であるなら、思考から少しでも自由になるという意味での、サティの継続は、この上なく大切であることに改めて気付いた。
エックハルト・トールのStillness Speaks(『世界でいちばん古くて大切なスピリチュアルの教え』)の中にこんな言葉があって、かなり印象を受けた。
The human condition: lost in thought.
「人間の条件:思考の中で迷子になること」とでも訳すのだろうか。「思考の中で自失すること」「思考の中で迷うこと」などという訳も可能だろうか。いずれにせよ。英語で読んだときの「まさにその通りだ」という印象は薄れる。
私たちは、思考するがゆえに迷っている。自分の心を占領しつづける愚かしい無数の思考に気づけば気づくほと、思考の中に迷っているのが私たちであることは、ますます分かる。ヴィパッサナー瞑想のサティは、その無数の思考に少しでも気づきを入れるのに有効な手段なのだ。
これに対してヴィパッサナー瞑想は、今現在の自分の知覚や心に気づくというサティの訓練が中心になる。そしてサティをするには、気づいたことに短い言葉を使ってラベリングすることが有効だ。
たとえば寝床に入ったとき、私はしばらく腹の動きにサティし、「膨らみ」「ゆるみ」とラベリングし続ける。そのうち注意が他の対象にそれる。手のちょっとした痒みだったら「痒み」とラベリングしつつサティをいれる。さらに注意がそれて何かを考えていることに気づいたら「思考」とサティを入れて、再び腹の動きへのサティへと戻る。
最近のこうしたヴィパッサナー瞑想を少しづつ復活させている。当然のことだが、ヴィパッサナー瞑想のサティを続けていると心の中の独り言、半ば無意識的な思考が少なくなる。つまり日常的なサティを続けていれば、エックハルト・トールが言うように「思考が注意を独り占めすることがなくなる。思考と思考の間にギャップ、つまりスペース、静寂が生じる。するとあなたは、あなたが思考よりもどれほど巨大で、どれほど深いかということに気づきはじまる。」
かなり長いこと、日常的なサティをおろそかにする年月が続いた。しかし脳内の半ば無意識的な思考こそが「自我」の本体であるなら、思考から少しでも自由になるという意味での、サティの継続は、この上なく大切であることに改めて気付いた。
エックハルト・トールのStillness Speaks(『世界でいちばん古くて大切なスピリチュアルの教え』)の中にこんな言葉があって、かなり印象を受けた。
The human condition: lost in thought.
「人間の条件:思考の中で迷子になること」とでも訳すのだろうか。「思考の中で自失すること」「思考の中で迷うこと」などという訳も可能だろうか。いずれにせよ。英語で読んだときの「まさにその通りだ」という印象は薄れる。
私たちは、思考するがゆえに迷っている。自分の心を占領しつづける愚かしい無数の思考に気づけば気づくほと、思考の中に迷っているのが私たちであることは、ますます分かる。ヴィパッサナー瞑想のサティは、その無数の思考に少しでも気づきを入れるのに有効な手段なのだ。