昨晩、珍しくテレビニュースのチラ見でしたが、11ch(名古屋テレビ)と3ch(NHK総合)で、ベトナムへ日本の新幹線を売り込みに、鉄な国道交通大臣が出かけていったそうですね。
11chは古舘さんの番組で、大岡越前を見終わりVTRを止めた時にたまたま映っていたのがベトナムの鉄道。まぁ雑誌の海外鉄道情報で見てはおりますが凄いですねェ、市街地の線路。「線路まで家が迫っている」という言葉がありますが、それでも日本では道路ではない線路側に玄関を設けるなんてまずあり得ませんが(例外あり)、ベトナムのそれは線路側が玄関で線路が道路の如く、住居空間の中に列車が走る様。そして停車場ではホームに玄関がある御宅が並んでいて、京福電鉄の嵐山本線太秦広隆寺駅にそんな様子が見られます。
ま、ベトナムの鉄道は兎も角、日本の新幹線を、JR東海が、車両メーカーが、そして政府がいろいろ売り込んでいるニュースがよくありますけど、こんな事書くと石ぶつけられるかな・・・、日本の新幹線ってそんなにいいものなのでしょうか。
いや日本の新幹線技術は、車両の技術も、運行を管理するシステムも、そして軌道・土木技術も世界一であります。ただこれは日本の厳しい輸送条件、特に東海道新幹線の輸送を満たすべく鋭意努力したもので、世界の何処にでも必要だとは思えないのですね。
日本の新幹線列車は動力分散方式、平たく言えば「電車」であり、16両編成中何両かはモーターの無い車両がありますが、編成中の各車両にモーターを配する方式。一方で諸外国の多くでは長距離の列車は動力集中式、いわゆる機関車方式です。フランスの高速鉄道TGVも見かけは電車みたいですが、編成両端の車両は動力車のみ。
動力費は、編成長にもよりますが、動力集中式の方が概して安いです。しかし日本では折返し駅での線路不足があったり、加速・減速度を高めたいという要求があったりして、機関車方式よりも電車方式が多く取り入れられて来ました。新幹線もその延長上にあります。
そしてこのような緻密ダイヤ、3分毎に270km/hの列車を走らせ、加速・減速度も毎秒2km/hなんて高速列車を走らせられる技術は、世界の多くではオーバースペックではないのかな。米国ではワシントン~ニューヨーク間などでは有ってもいいかもしれません。テレビにあったベトナムでは、国土の発展で高速鉄道は必要でしょう。でもそれは日本方式ではなく、フランスのTGV方式やドイツの方式も考えてみたら如何と、ニュースを見ての感想でした。













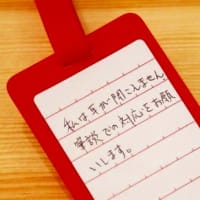
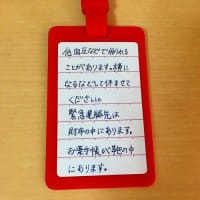





私は良く分かりませんが、日本の新幹線の技術は、かなり優秀らしいです。外国へ輸出する物はN700系です。いま日本で技術開発している新幹線は、次のものを研究中だそうです。フランスのTGV(テージェーベーと読むらしい)に乗った事が有る人に聞いた話ですが、テーブルのコップが前後左右に動いて遂に床に落ちるそうです。それ程の揺れ方です。これは道床だけの問題で無さそうです。道床と台車、エヤサス、箱、パンタなどのマッチングなんでしょう。
先日テレビで見ましたが今研究中のパンタ、全く離線しないパンタがほぼ完成してますね。やはり日本の新幹線は優秀だと思います。しかし、あまり優秀な技術は輸出して貰いたくありません。特に中国には。狭い心の持主かもしれませんがね。その点、JRは心得ているようです。
最新の技術は絶対に外には出さず、ある程度古くなってからにしているようです。
フランスのTGVは仰る通り「テージェーベー」と読みます。私は一応フランス語をかじったことがあるものでして。
TGVがよく揺れるという話は聞いたことがあります。日本の新幹線も一時はハデに揺れていました。車両若しくは軌道から来る特性の他、整備不良というのもあります。フランスは何と言ってもあのお気楽な土地柄ですし、車両個別で当り外れがあるやにも聴きます。
離線しない集電装置ですが、これは電車線路(架線のこと:正式名称)にレーザー光を当てて、正確な距離を測定しながら追随させるやり方で、これが考えられる最善の集電装置です。
高速鉄道の問題点の一つにこの終電の問題があって、発生するスパークをどう処理するか、どのような形が追随性が良いのかが大変でした。そして風きり音。フランスではこれは差ほど問題にはなりませんでした。
別に日本の何方でも16両編成が270km/hで一時間20本も運転出来るものを輸出しようとしているわけではないそうですが、あまりにも高スペックですね。加速度を期待しなくてもよいのなら、私は機関車方式のTGVやICEが良いのではないかと思っているのですが。
車両などの修繕費は、動力集中だと思いますが、新幹線レベルの速度だと、軌道に与える影響は動力分散のほうがはるかに少なく、保線費もかなりの差が出るのではと思います。あと動力集中だと電気制動が出来ないので、ブレーキの保守に手間がかかると聞いたことがあります。
あと新幹線のほうが優れていると思えるのは、本線にデッドセクションがない点があります。交流電化では変電所ごとの位相の違いによって、異相セクションがどうしても発生し、そこだけは惰行運転が必要です。ここをそのまま通過すると、パンタグラフから大きなアークが発生して、架線切断事故の原因になるため、在来線やTGVの場合、交直流のデットセクションのように惰行で走行する必要があります。
しかし日本の新幹線の場合、セクション内で、自動的に一瞬停電させて、前の変電所から次の変電所に切り替えています。これによって慣行の必要がなくなります。BTき電方式から、ATき電方式になって、セクションでのアークの発生もさらに抑えられるようになりました。
ATき電方式については、間違いなく世界最高の技術ではないかと思います。
仰る通り動力分散式は軸重を軽くすることができ、軌道に与える負担影響は少なくて済み、ひいてはそれが保守費用軽減に繋がります。
機関車方式で後に続く客車が無動力でブレーキの保守手間ですけど、私が思うには、日本の鉄道のような高加減速を要求しなければ、制輪子による制動でもやれるのではないかと思います。また無動力客車でも各車軸に円板を取り付け渦電流を発生させて制動力を得る方法もあります。
新幹線鉄道の電車線路セクションは、1980年代に一層の高速化を目指して大きな問題となりました。結局はstakenakaさんコメントにある通り、セクション内では短い区間を独立させ、走る列車に合わせて変電所の供給電力を追わせる方式ができました。
昔(といっても四半世紀前)、走る新幹線を見て「ぴかっと光ればひかり号」、そうでなければ「こだま号」などというお遊びがありましたけど、今は電車線路からのスパークは少ないですね。そんなピカピカ光っていては、270km/hで走られませんし。
***
stakenakaさんへ私信ですけど、四線会名駅立飲みオフで何度かお会いした、元名工大のあいそっくさんが、本を出されましたね。
渦電流ブレーキは、制動力こそ強力ですが、軽量な誘導電動機が普及した現在では、M車よりもかえって重くなると聞いていますのでN700系からは廃止されています。
あと200km/h超での動力集中による軌道負担は馬鹿にならないようで、次のTGVも動力分散になるといわれています。
またドイツの場合、ICE 3で本格的に動力分散になりましたが、新線の建設費節約のため、勾配区間が増えて、動力集中では速度が確保できないため動力分散になったといわれています。
このあたり、線路の建設費との関係を考えると、どちらがいいのかは判断がつきかねるところでもあります。
渦電流制動ですけど、先回書いてから、やはりモーターの子分みたいなモノを車軸にくっつけているようなもので、それに動作させる電源装置を載せると結構重たくなるのでは?と思えててきました。
N700には無いのですか。N700は窓が小さく、個人的に好みませんので勉強不足でした。
TGVが動力分散式へ、ですか。時代も変わるものですね。私の頭も変えねばなりませんかな。
ヨーロッパの風土ですと現行技術の延長上での動力分散式も使えましょうけど、熱帯のベトナムでは日本と同じ様な装置設計の思想で大丈夫なのかな?という思いもあるんです。
軌道保守とのかね合い、直接動力費のかね合いもあって、この辺りは微妙なところですね。