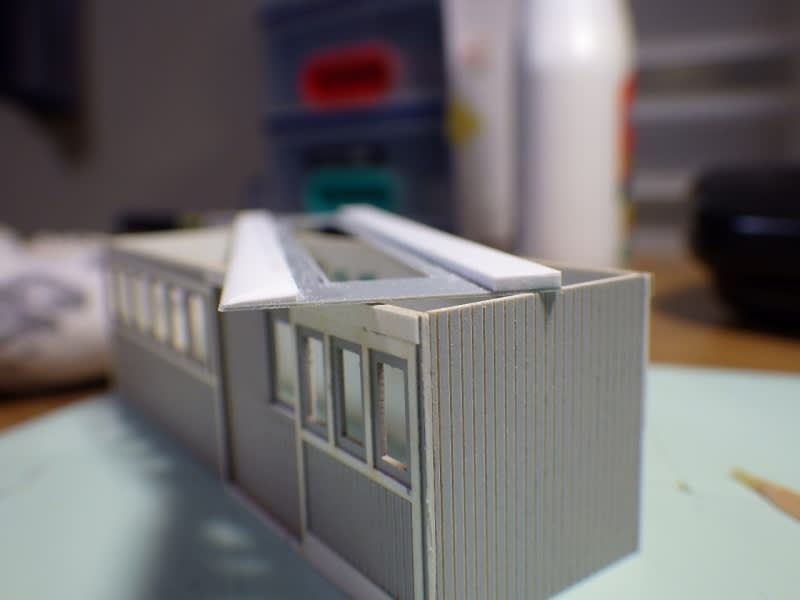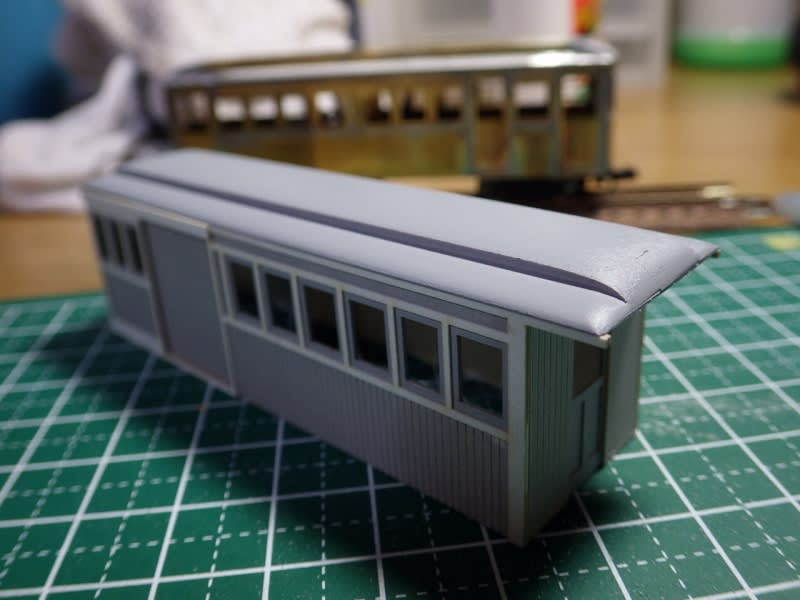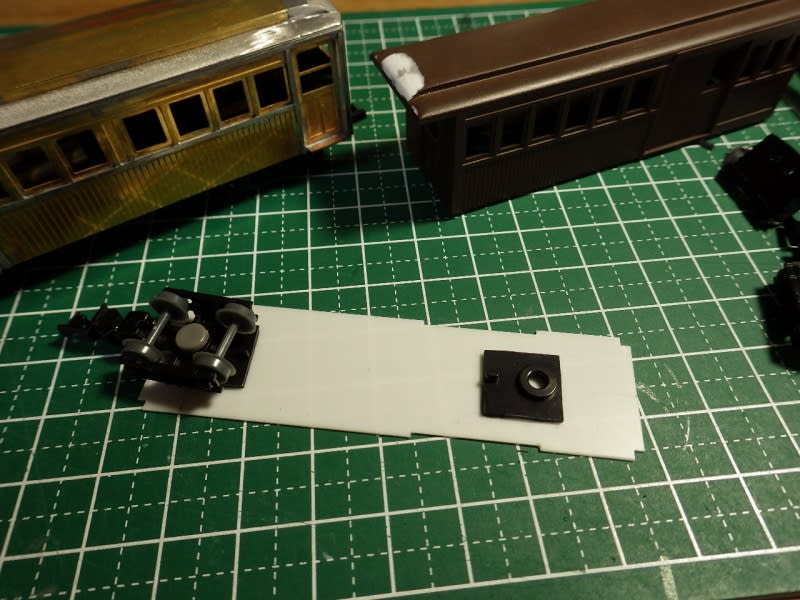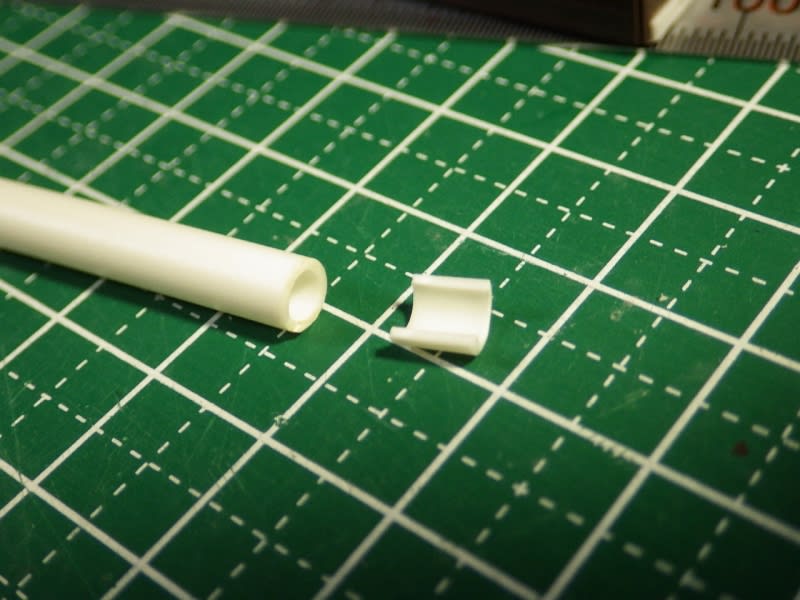七年に一度の下伊那の大イベント「お練りまつり」が25~27日の日程で開催された。

「七年に一度」というと、諏訪の御柱祭が全国的にも有名であり絶対の存在である。「それに隠れてしまいマイナー」とは地元民の弁だが、宣伝不足も大いにありそうである。とても盛況なので、もうちょっと知れててもいいように思う。
市内の大宮諏訪神社の式年大祭に併せて開催される。
大宮神社のお祭り自体は24日に神輿が町の中を廻るというもの。その後に町内の衆が様々な出し物を催したのが起こりのようだ。「せっかくなのでオラホも」というノリだろうか?如何にもお祭り好きなこの地域の人々の考えそうなことである。



お練りまつりの主役は「獅子舞」
市内だけでなく周辺の町村からも「保存会」が参加し、40余りの獅子が出現する。
後ろに胴体が付いており、普通の人のイメージする「獅子舞」より相当大がかりなのがここの獅子の特徴である。
タイヤの付いた台車になっており、中で楽器が演奏される。
それぞれの獅子には異なるエピソードがついており、形や色が異なる。
・・・興味のある方は調べてみてください(良く知らないので・・・


中でも特大の物が「東野大獅子」で、サイズ的には大型の路線バスくらいあろうかというもの。
狭い商店街を進む姿は圧巻。


出し物は獅子舞だけではない。
大名行列に使われる道具は江戸時代の本物なんだとか。とにかくすごい人気である。

この週末は丘の上(要は旧市街)は今まで見た事が無い程の人出。
「いったいどこから?」とみんな言うが、ちょっと考えてみた。
恐らく、下伊那在住者以外は多くが帰省者なのである。
下伊那地域の人以外で「お練りまつり」を知っている人は民俗学者や祭り、獅子舞に興味がある人に限られてくるだろう。
実際「何年振り!?」という偶然の再開に喜ぶ人々に度々出くわした。
個々ではもっと頻繁に帰省するのだろうが、それが一堂に会する機会というのは中々少ないのではなかろうか?
伝統だの何だのと地元住民が大事にしている事だが、実は故郷を離れた人間にこそ大事なイベントなのかもしれない。