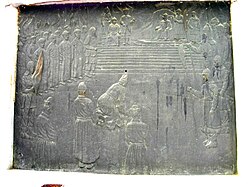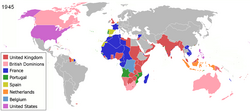福島原発から漏れ出した放射性物質、その影響について
事故により本当は何が起きたのか、ということに関しては現時点では
MIT研究者Dr. Josef Oehmenによる福島第一原発事故解説
↑から「辿れる情報」がもっとも信頼性は高いと判断されます。訂正され続けているし。
そのためこれを読みこなす力のある人はそちらを読んだ方がよいと思われるし、
おおよそ13日時点での当方の見解を訂正する必要もなさそうです。
福島原発の放射能を理解する:追加・pdfの見やすい解説
それくらい、チェルノブイリ原発事故には遠く及ばない規模の事故ではあるし、
(未だに放射能による死者がいないことからも)住民や東電作業員の退避も
「健康に被害を及ぼしかねない」という比較的悠長な理由で行われている状況です。
スリーマイルと比べれば、それが4機だし、人里近くなので重篤な事故ですが。
放射線の検出は各地で相次ぎ、それは一体どれだけの影響を及ぼすのか、というと
これは確かに本当に限定的です。何故ならば現在観測される放射能は大部分が
半減期が「日」から「時間」単位の放射性物質に由来するためです。そのような
放射線量が福島県内ですら「基準を超える」という程度に収まっているので。
放射性物質の放つ放射線量は半減期に、ほぼ反比例します。
「減る」ときに放射線を出す形になるので。原子炉での核分裂により生成されるのは
さまざまな種類の物質がありますが、現在特に放射能を出しているのは、
収率の関係から同じヨウ素でも131(半減期8日)よりも135(半減期6時間)。
セシウムの方も137(30年)より136(13日)が強く、こちらは133(安定)も大量なので。
原爆が広島に投下された時、大量の放射性物質がばらまかれましたが、
その放射線量は思いのほか急速に減衰したという事実もあります。
今回放出された量はそれよりははるかに少なく、中国での核実験で届いたもの
(日本では)と比べてすら、まさしく「微量」ではあるのです。
あのチェルノブイリですら流出した放射性物質は、狭い範囲に集中しているため
大問題となってはいますが、20世紀に数々実行された核実験と比べれば
ほんの微々たる量に過ぎないのです。一般に流布されているイメージと違って。
そう、地球環境は今回の災害をも吸収できます。その後に起きることも、今のところは。
放射性元素の大部分をなす重金属とて、いつかは無害化されます。水俣病等のように。
大事なことは正しく多角的に理解し、必要以上に恐れないこと。
現状では花粉と同様の対策も有効です。似たような大きさのエアロゾルになるので。