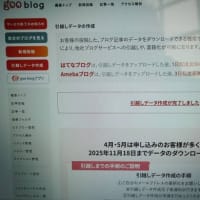昨年2月末の九州全県駈足旅行に続いてまたもや九州に、でも今回は宮崎と鹿児島に絞って前回となるべく重ならないプランのツアーを選んだのだが、でも二回目になると要領が分かって上手く立ち回れるということもあるから多少の重複は許しましょうと。
ここ数回のツアーに比べて集合時間が8時15分と頃合なので、いつも通りの朝食を食べてから愛犬の散歩も済まして7時少し前に我家を出発、東横線で横浜に出てYCATからリムジンバスで羽田へ。初めてYCATを利用したけれど、ここからは乗客がズラッと列を作っていてバスも次々と出て行くのですねぇ、これに比べたら我が駅前からは数えるほどの人数で止めちゃったのが分かりますよ。飛行機は今渦中にあるJALじゃなくて久しぶりのANAだから終点駅の第2タミナルで、8時には旅行社団体搭乗3番カウンターで手続、すぐにチェックインして九州方面は一番遠くの待合ロビーまでは歩かされるなぁ。
外は雲で何も見えないからとズーッと本を読んでいたら突然にドーンと荒っぽくジェット機が舞い降りた宮崎空港、天気予報では関東の雨は午後からといっていたがこちらではもう止んでいてこれはラッキー。到着ロビーを出れば添乗員が二人いてこのツアーはバス2台とか、こちらは28名の参加者で、久しぶりに20代の若いバスガイドの旗の後に従ってバスに乗込む。本当は鹿児島空港の方が時間に余裕ができたのに、こういう格安ツアーは空いているフライトを直前になって当てるからよくこういう不都合は生じるのだ。
最初の目的地は鹿児島南部まで一気に走ることになって昼食は各自で搭乗前に買ってきた弁当を車内で食べ、途中では桜島SAでのトイレタイムをとっただけ。この日は曇り空で霧島連峰や桜島の遠望は望めずバスガイドから案内があったのは田野地区の漬物用大根干しの風景ぐらい、そのほかは自称由希さゆり似というガイドさんの楽しい闊達なおしゃべりを聞きながらということに、そのガイドさん、自己紹介でまずは自慢させてと地毛の睫毛が長いことを横顔で見せて、マスカラでぐいぐいと上げてバッチリ決めてきましたと笑わす、いやなかなかに観光案内だけでなく工夫した話題と話しぶりで宮崎交通のバスガイド教育がシッカリしているのが分かります。このツアー中に見かけたガイドさん達は皆さん若手が多くて、南九州ではまだ若手健在ということでしょうかね。ちなみに運転手さんは再雇用じゃなかなと思われる小柄で温厚な人でした。また毎日車内で毎日一回のお茶のサービスというのもこういうツアーでは初めて、なかなか会社の姿勢がよろしい。
 田野の大根干し風景
田野の大根干し風景
宮崎自動車道から九州自動車道に入り、昨年も車中から見た加治木龍門の滝を過ぎて桜島SAで休憩、そして鹿児島で高速を出て、海岸沿いをかなり走って喜入地区にある屋久杉工芸のアリヨシ民芸品店が最初の立寄り場所。1000年以上の樹齢のものを屋久杉というそうで、現在では伐採禁止だから今後は値段は上がることはあっても下がることはないというこの工芸品は、島だけでなくこちらでも加工業者はかなりあるという。ここではロクロでコケシみたいに加工して首輪も同時に削り込むという技を実演してあとはお土産タイム。まぁ記念だからと木目がキレイな小皿を一つだけお買上げ。焼酎樽なるものを宣伝していて、これに入れたものと瓶から直のものと飲み比べさせていましたが、確かにまろやかになるのは分かるけれど、僕は焼酎は普段ほとんど飲まないからね。
アリヨシ民芸品店 ロクロの実演
樹齢1800年の屋久杉 これでも立派な材がとれるという
次は第一日目のメインの観光地である知覧に峠越えで入る。薩摩島津藩では各地に家臣団を配していたそうで、ここ知覧も60石から70石代の武士達が暮していた土地、その武家屋敷群が今でも残っていて重要伝統的建造物群保存地区に指定、両側の石積みの上にイヌマキと足元にもお茶を植えた生垣が並んでいて屋敷内側が見えないようになった道は昔のそのまま、いくつか鍵の手があるのも防備を考えたものである。特に外からは覗えない屋敷内の庭園が見事で、今は7庭園が公開されていて、一つの池泉庭園を除いて他は全て枯山水の庭で白い火山灰の土は雪を見立てているのだそうだ。石積みには切石と丸い野面積みの2種類があって、これも積み方の変化がいい景観を醸しだしている。総じて切石の方が身分が高いのだそうだが沖縄の玉石積みの影響もあるらしい。表通り(冒頭写真)にも水路があって鯉を泳がすなど修景に努力していて、一帯を歩いて巡るにはこういうツアーでは時間が足りないのが残念。唯一の池泉式の森重堅庭園では知覧茶をサービス、これが100gで600円のお茶なのだが、入れ方でこんなにも変るものかとガイドさんが感心するからと喋っていたように、ぬるい湯で入れたお茶は香りが立って味も申し分なく美味しい、静岡出身の僕も一袋だけだけれど買ってしまった。
 立て看板
立て看板
 公開は7庭園
公開は7庭園

茅葺で残された屋敷は食事処となっている
軒樋立樋ともに竹が使われる 右から2番目の600円のお茶でも充分に
バスは知覧の街中を通り、戦時中特攻の母といわれた鳥浜トメさん経営の食堂を復元して記念館となった富屋食堂と戦後築の旅館建物を車中から眺めてから、本日最後の観光場所の知覧特攻平和会館に。
 再建富屋食堂は資料館に
再建富屋食堂は資料館に
ここは観光見物というのは憚れます、戦争の悲劇から学ぶ場所というべきであるなと。本土最南端の航空基地で大戦末期にここから多くの特攻機が沖縄戦線に飛び立った場所であるからこの記念施設ができた。館内には主にここから出撃して散った隊員にそれ以外も加えた11次に渡る陸海編成隊全ての特攻戦没者1036人のあまりにも若い遺影写真と共に遺書、日記、手紙類を展示、特に20歳前後の隊員達の筆跡の立派なのには驚かされる、還暦過ぎの自分でもあれだけ達筆には書けない。海底から引揚げられた零戦などの特攻機や軍服や装備品から遺品なども、TV放映ではアメリカ軍が写したであろう特攻機の戦艦への突入シーンや戦後に当時を語る鳥浜トメさんの映像も流されている。内部は撮影不可というのは鎮魂の施設でもあるだろうから当然だね。外には復元された当時の隊員の宿舎だった三角兵舎を廻って、胎内に隊員の名前を書いた巻物を納めた小さな特攻平和観音像を祀る御堂を経て、屋外の映画のために復元された隼機などを巡る。
特攻平和会館玄関 映画のために復元した隼機
参道風道路だけでなく周辺道路まで並ぶ石灯篭も寄付募金者名簿が書かれて1036基、著名人の名前も見られるのだそうだ。またこの敷地の前を南に向って伸びる道路は当時の滑走路だったそうで、今は真直ぐに走る立派な道になっているのだが、これが覚悟の道だったとはバスガイドから聞いて感迫るものがある。これは地元の人は皆さん知りながら車を走らしているのだろうかと、はるか開聞岳上空で翼を振って別れの挨拶しながら飛び去っていったという話が切ないね。
護国神社参道が会館への入口 この道路が特攻機離陸滑走路だった