この本を読んで一番うれしかったのは、高校時代の友人野地澄晴の研究成果が詳しく紹介されていたことだ。
何も知らずに読んだ徳さん、びっくりするやら、嬉しいやら、励ましを貰った気分になったりした。
高校卒業後も彼の研究室に入り浸ったり、一緒に広島の低い山地に遊んだり、小旅行をしたり、様々な思い出が一挙に吹き出してきた。
当時は二人共稚拙だったが、妙に生真面目だった。
その後、徳さんだけ一方的に崩れ散った、という訳。
紹介されていた彼の研究は、人間の胃癌の細胞から取り出した線維芽細胞増殖因子を初期のニワトリの胚移植すると、そこに、本来の設計図には無い足が一本生えてきたという事実の発見だった。
種を超えて遺伝子を操るものがいる、という事だ。
人間は、偶然にして生まれた一つの生命から始まった。
それからの進展を免疫学の立場から解説してくれるのが本書である。
なにやら、日頃嫌悪しているバイ菌や見るもおぞましい生き物たちが親しみを込めて眺められる様になるのが不思議。
免疫学の話はとてつもなく面白い。
今までの、生き物に対する知見を物の見事に裏切ってくれる。
個々の細胞たちは己れの使命を知らない。
その時その時で自分に課せられた状況に応じて反応のみ。
自殺しなきゃならない時は、なんの躊躇もなしに自殺する。
その理由は、隣にいる細胞の状態だけだ。
徳さんたちの脳の中ではそんな振る舞いは出来ない。
でも、徳さんたちがどう思おうと、細胞さんたちは勝手にやって仕舞うのだ。
免疫学の話は面白い。
が、とてつもなく難しい。
科学の中にあいまい性、偶然性を持ち込んだのだ。
そして、その理由とからくりを解明しようとしている。
そんな、難しさへの理解は本書を読むしかない。
という事で、徳さんは関係のない気になる箇所の抜粋。
紀元前430年という大昔の話だ。
ギリシャで黒死病と呼ばれるペストの大流行があった。
当時のアテネ市民の三分の一が亡くなったという。
人々は何も打つ手立てが無く、恐慌状態に陥ったのだが、やがてペストはいつの間にか身を引いた。
細菌もウィルスも生き延び、子孫に己を引き継ぎたくて彼らなりに努力する。
宿主が壊滅しては困るのは彼ら。
やがて、構造が似た兄弟のような細菌が生まれ、人々の発病を止めるに至る。
エイズもエボラ出血熱もそんな行程を辿るはずだ。
で、徳さんが注目したいのは、当時の世相の動きに反応したツキディデス描写だ。
*****
この病気が流行し始めると、アテネ市民の日常の行動様式が変わってくる。 突然の災厄に動転した人々は、まず病気のもととなった犯人をさがし出し、リンチにかけようとする。それまで友人だった人が、感染を恐れて互いに近づこうとしなくなる。病人を誰も看病しなくなるので、空家同然となった家に、患者は独り残されて死ぬ。(中略)宗教的感情が失われ、道徳が退廃して、死者を弔う儀礼さえ怠るようになった。(中略)
逃亡、差別、犯罪、殺し合い、無秩序、絶望、そして死と隣り合わせの京楽。これが、ツキディデスの描いたペスト猖獗の下での人間の行動様式であった。
*****
あれ!?
これって、今の今の、日本の姿だよね~。
カイロジジイのHPは
http://chirozizii.com/
そして、なんでもブログのランキングというものがあるそうで、以下をクリックするとブログの作者は喜ぶらしい。
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
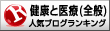
何も知らずに読んだ徳さん、びっくりするやら、嬉しいやら、励ましを貰った気分になったりした。
高校卒業後も彼の研究室に入り浸ったり、一緒に広島の低い山地に遊んだり、小旅行をしたり、様々な思い出が一挙に吹き出してきた。
当時は二人共稚拙だったが、妙に生真面目だった。
その後、徳さんだけ一方的に崩れ散った、という訳。
紹介されていた彼の研究は、人間の胃癌の細胞から取り出した線維芽細胞増殖因子を初期のニワトリの胚移植すると、そこに、本来の設計図には無い足が一本生えてきたという事実の発見だった。
種を超えて遺伝子を操るものがいる、という事だ。
人間は、偶然にして生まれた一つの生命から始まった。
それからの進展を免疫学の立場から解説してくれるのが本書である。
なにやら、日頃嫌悪しているバイ菌や見るもおぞましい生き物たちが親しみを込めて眺められる様になるのが不思議。
免疫学の話はとてつもなく面白い。
今までの、生き物に対する知見を物の見事に裏切ってくれる。
個々の細胞たちは己れの使命を知らない。
その時その時で自分に課せられた状況に応じて反応のみ。
自殺しなきゃならない時は、なんの躊躇もなしに自殺する。
その理由は、隣にいる細胞の状態だけだ。
徳さんたちの脳の中ではそんな振る舞いは出来ない。
でも、徳さんたちがどう思おうと、細胞さんたちは勝手にやって仕舞うのだ。
免疫学の話は面白い。
が、とてつもなく難しい。
科学の中にあいまい性、偶然性を持ち込んだのだ。
そして、その理由とからくりを解明しようとしている。
そんな、難しさへの理解は本書を読むしかない。
という事で、徳さんは関係のない気になる箇所の抜粋。
紀元前430年という大昔の話だ。
ギリシャで黒死病と呼ばれるペストの大流行があった。
当時のアテネ市民の三分の一が亡くなったという。
人々は何も打つ手立てが無く、恐慌状態に陥ったのだが、やがてペストはいつの間にか身を引いた。
細菌もウィルスも生き延び、子孫に己を引き継ぎたくて彼らなりに努力する。
宿主が壊滅しては困るのは彼ら。
やがて、構造が似た兄弟のような細菌が生まれ、人々の発病を止めるに至る。
エイズもエボラ出血熱もそんな行程を辿るはずだ。
で、徳さんが注目したいのは、当時の世相の動きに反応したツキディデス描写だ。
*****
この病気が流行し始めると、アテネ市民の日常の行動様式が変わってくる。 突然の災厄に動転した人々は、まず病気のもととなった犯人をさがし出し、リンチにかけようとする。それまで友人だった人が、感染を恐れて互いに近づこうとしなくなる。病人を誰も看病しなくなるので、空家同然となった家に、患者は独り残されて死ぬ。(中略)宗教的感情が失われ、道徳が退廃して、死者を弔う儀礼さえ怠るようになった。(中略)
逃亡、差別、犯罪、殺し合い、無秩序、絶望、そして死と隣り合わせの京楽。これが、ツキディデスの描いたペスト猖獗の下での人間の行動様式であった。
*****
あれ!?
これって、今の今の、日本の姿だよね~。
カイロジジイのHPは
http://chirozizii.com/
そして、なんでもブログのランキングというものがあるそうで、以下をクリックするとブログの作者は喜ぶらしい。










