
安楽死数が増えている背景について、オランダ政府は「理由を明確に説明できない」としているが、同国内では“安楽死専門クリニック”の活動がその一因と考えられている。
オランダ第3の都市デン・ハーグにある「レーフェンスアインデ・クリニク(死ぬためのクリニック)」には、昨年3月のオープン後、患者が殺到している。同院では、患者とカウンセリングを重ねた後、自宅に専門ユニットを派遣して安楽死処置を行なっている。ディレクターのスティーブン・プレイター氏がいう。
「開院以来1年半で、約1100人の申請があり、そのうち、医師の判断を経て安楽死にいたったのは約200件。現在でも180人がウェイティング・リストに入っている状況です。安楽死基金の援助もあり、処置はすべて無料です」
クリニックを訪れるのは、かかりつけ医に安楽死処置を拒まれた患者が多いという。法律で定められているのは“医師が刑事罰に問われない”ということだけで、処置は義務ではない。信条や経験の有無から処置を拒む医師も多いのだ。クリニックはまさに、死に場所を求める人々の“駆け込み寺”なのである。
処置数が急増する背景はそれだけではない。2011年11月、重度のアルツハイマー病を患っていた64歳の女性に安楽死が行なわれたことが明らかになった。それまで、認知症が進んだ患者に「自発的な意思表示」ができるのかが疑問視されてきたため、処置は行なわれてこなかったが、初めての事例になった。女性は8年前から「老人ホームに入ったら、その際には安楽死を望む」と紙に書き残していたという。
また、今年6月には、死に直面している新生児を見るに耐えられない親は、医師に安楽死を求めることができるようになった。同国の年間出生数約17万5000人のうち、およそ650人が、その例にあたるとされる。社会学者の立岩真也氏(立命館大学教授)はこう指摘する。
「本来は“本人の意思”が安楽死の適用条件なのに、意識の確認のできない子供、障害者、認知症患者などにも対象が拡大しています。オランダでは、年を取って生きるのが嫌になった高齢者にも認めようという動きもある。“終末期”や“耐えがたい苦痛”という条件も外れてきています」
※週刊ポスト2013年10月25日号
現在、積極的安楽死を認めている国は、スイス、アメリカ(オレゴン州、ワシントン州)、オランダ、ベルギー、ルクセンブルクと聞いている。
この記事は、そのなかのオランダの話である。
「死ぬためのクリニック」というのもすごい名前だが、この病院では200人がウェイティングリストに入っており、すべて措置は無料と言うのがすごい。
オランダでは年間の死亡者数の3%が安楽死であるらしい。
正式な「安楽死」ではなく、事実上はそれに近い死の迎え方と言う意味で言えば、もっと多くなるのだろう。
「安楽死」や「尊厳死」をめぐる小説や自伝や映画などをたくさん見てきた。
日本でもようやく、周防正行が朔立木の短編をもとにして2012年『終の信託』という映画を発表し、30万人を動員、日本映画大賞を受賞している。
女医役の草刈民代は患者役の役所広司の安楽死に結果として手を貸す形になるのだが、検事である大沢たかおは激しく彼女の罪を糾弾するのである。
僕は、本人希望がはっきりすれば、安楽死は受け入れるべきだと思う。
けれども、本人が認知症で意思表示が不明であったり、障害を持ったこどもに対して親が判断できるかなど、迷うところもある。
もし日本で「死ぬためのクリニック」が無償で設立されたなら、もしかしたら希望者が殺到するかもしれないと思ったりもする。











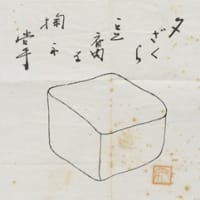


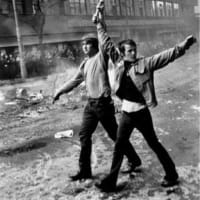



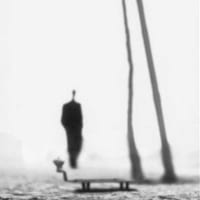

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます