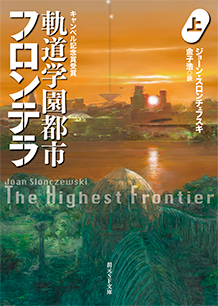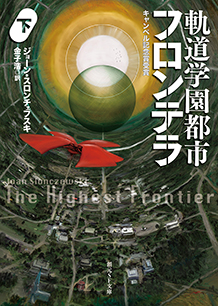『ユートロニカのこちら側』 小川哲 (ハヤカワSFシリーズ Jコレクション)

第3回「ハヤカワSFコンテスト」 大賞受賞作。
ユートロニカとは、すべてが思い通りになるような楽園のこと。たとえば、扉を開けるときにいちいちドアノブを意識するか。すべてのことが無意識にできるようになると、人々は意識を失うかもしれない。
物語の中心は、すべての個人情報、行動履歴を把握することにより犯罪に走るような危険な兆候を見つけ出し、事前にこれを阻止するシステム、BAP。すべての個人情報の提供と引き換えに生活を保障するというアガスティア・リゾートを取り巻く人々を背景に、BAPの誕生とその功罪が語られる。
P・K・ディックの『マイノリティ・リポート』が下敷きにあるのは明示されている。言うまでも無く、楽園(ユートピア)において個人の意識が喪失するというのは伊藤計劃の『ハーモニー』でも描かれている。犯罪の事前阻止といえば、そのものずばりのアニメ『PSYCHO-PASS サイコパス』がある。それらの影響を受けた上で、その先を描くことができたか。
たとえば新潮社や文藝春秋などではなく、ハヤカワの新人賞を受賞して出版されたということは、必然的にSF的な考察に関してはそれだけハードルが上がるということだ。著者がそれを応募時に意識していたかどうかは関係なく。
タイトルどおり、この物語はユートロニカの“こちら側”でとどまっている。そして、物語が進むにつれれて、“こちら側”にとどめようとする人々の想いが主眼になっていく。
この物語では“こちら側”へのこだわりが強く見える。すべてをシステムにゆだねてしまうのではなく、人間が人間として、システムにはじかれそうな人間を人間のままで救い出そうとする努力。システムの前に、人間として人間のまま立ち向かおうとする戦い。
システムによって世界が住みやすい楽園となる期待感と、すべてをシステムにゆだねてしまうことへの不信感のジレンマ。その葛藤が生む物語。しかし、どうあがこうとも、“エントロピーの法則”には逆らえない。
神林長平がコンテストの選評で「なぜ日本を舞台にしないのか」と書いていた。読み終わってみれば、人権意識の強さと、キリスト教的な倫理感が物語の大きな背景となる以上、日本を舞台にすることができなかったのが良くわかる。
しかし、逆に、日本でこのアガスティア・リゾートが始まっていたらどうなっていたかという考察もおもしろい。日本人の横並び意識、お天道様が見ているという倫理感、人権意識の違い、それらは、おそらく違った物語をつむぎ出すに違いない。
すべての個人情報、プライバシーを買い取る企業と言うと、世界的にはGoogleが思い浮かぶのだけれど、日本のCCC(TSUTAYA)もなかなかのものだ。しかし、日本人のCCCに対する意識は両極端だ。便利になったと喜ぶ人もいれば、セキュリティ面の杜撰さを声高に叫ぶひともいる。さて、GoogleやCCCがユートロニカへの第一歩なのだとしたら……。
はたして、すべての個人情報、行動履歴からビッグデータ解析によって、個人の行動すべてが推測可能なのであれば、自由意識はどこにあるのか。あるいは、自由意識が存在しないことは何が問題なのか、なぜ問題なのか。
この手のネタ的にはまだまだ掘れそうで、ひとつの分野になるポテンシャルがありそう。