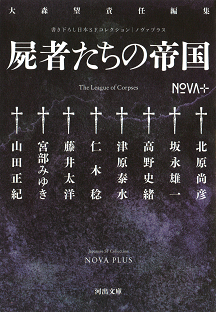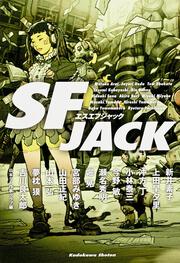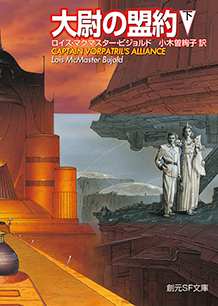伊藤計劃が残したわずか30ページの序章。それが円城塔の長編小説となり、ノイタミナムービーとしてアニメにもなった。
魂を失った死体へ“霊素”をプログラムのように書き込み、屍者として復活させる。そのゾンビは奴隷であり、労働者であり、ペットであり……。
屍者=プログラマブル・ゾンビを扱った作品だけに、「伊藤計劃という死者を無理矢理動かそうとする悪ふざけ」というのは、円城塔の弁だが、これほどまでに愛情あふれた言葉は無いかもしれない。
この短編集は、それらを下敷きにしたシェアワールド短編集である。
最初に企画を聞いた時には、それぞれの作家が、伊藤計劃の序章の続きを書くのかと思ったのだけれど、さすがにそれはなかった。あくまでも、世界観を共通の下敷きにしたシェアワールド。
我々のよく知る(歴史上や他作品の)キャラクターが、伊藤計劃(と円城塔)が作り上げた魅力的な世界で生き生きと動き出すというのが面白さのひとつ。
架空の19世紀を舞台とし、歴史上の実在人物、フィクションの登場人物が次々と関わっていくヒーロー大決戦的な展開はスチームパンクの典型でもある。
そうか、19世紀というと既に著作権切れなのでこういうことができるのだな。
とはいえ、あちこちで出てくるあの博士の設定とか、もうちょっと作品間での横のつながりも欲しかった気がする。しかし、そこまで厳密なシェアワールドでもないし、いいか。
○「従卒トム」 藤井太洋
主人公はアンクル・トムの孫。世界SF大会でアメリカ人にストーリーを話したら大爆笑だったというネタ。屍者と奴隷の相違、および、支配者と被支配者の逆転がツボなのだろうが、日本人としては幕末の登場人物の造形が楽しい。
○「小ねずみと童貞と復活した女」 高野史緒
ロシア文学の『白痴』(未読)を下敷きにしているが、『アルジャーノン(略)』をはじめとしたSF作品からのネタがそこら中に散りばめられている。そうか、ドウェル教授はのちにサイモン・ライトになったのか!
○「神の御名は黙して唱えよ」 仁木稔
屍者とイスラム神秘主義を重ね合わせた作品。宗教と科学の比較論ってわけでもないか。
○「屍者狩り大佐」 北原尚彦
円城版『屍者の帝国』の正当な枝篇。いろいろ無茶な事件は、すべてあの博士の仕業か!
○「エリス、聞えるか?」 津原泰水
タイトルから別な小説へのオマージュかと思ったけど、そうでもなさそう。藤井氏の作品もそうだが、“屍者”を十把一絡げの労働力として位置付けるのではなくて、こういう視点の方が日本人的感性に合うのかも。
○「石に漱ぎて滅びなば」 山田正紀
なんだか一番“屍者”の設定や意味から離れていそうだが、それだけに、収録作の中ではいちばん破天荒な作品になった。
○「ジャングルの物語、その他の物語」 坂永雄一
主人公のアランって誰かと思ったら……。ここでもあの博士が登場とか、歴史や名作に繋がっていく設定を読み解いていくのが読みどころ。小説内には直接は関係ない歴史のその後も描かれているのも、想像が膨らんで良い。
○「海神の裔」 宮部みゆき
単純にうまいなという感想。これも新たな視点の“屍者”の捕らえ方だと思うけれど、やっぱり、こっちの方が短編に仕立て上げやすいのだろうね。