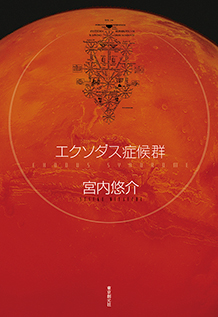やってくれました。藤井太洋。こりゃすごい。脱帽だ。
近未来ものかと思いきや、描かれているのは正に現在、今この瞬間。そして、先見性がどうのとか予見的がどうのとかではなく、現時点で問題になっていることをわかりやすく整理してストーリー化している。これは関係者必読。
関係者というのはSFファンだけじゃなくって、コンピュータ、データ処理、IT技術に関わる人すべて。もっと言えば、それらのユーザを含むすべての人。スマホを使い、ATMを使い、電子マネーを使うあなたにも、けしてヒトゴトではない。
露骨に元ネタとして描かれているのは、ゆうちゃん事件こと、パソコン遠隔操作事件。そして、一部で悪名高い武雄市図書館の官民連携システムだ。
パソコン遠隔操作事件では警察の無能サイバー捜査によって冤罪被害者を量産し、杜撰な証拠固めによって、あやうく真犯人を不起訴にするところだった。
そして、武雄市図書館のシステムはTSUTAYAやスタバの併設が好評な反面、情報の流れの不透明さに対する懸念が今でも払拭されていない。
もし、パソコン遠隔操作事件の容疑者が本当に無罪であり、官民連携システムが意図的に作られたセキュリティホールだったら。それをフィクションとして描いたのがこの小説。
さらに特筆すべきは、最大12次にも達するというシステム案件。通称、IT土方とも呼ばれる悲惨なデスマーチの現場がリアルに描かれていること。これもフィクションとして多少の誇張はされているものの、現場を知るものにとっては悲哀あふれる、あるあるネタが満載で、リアル感が半端無い。
さらには無能な警察、人権無視の密室取調べ、デリカシーの無いマスコミ……。物語はフィクションであっても、数々のネタにはすべて元ネタがあり、リアルだ。
本来、ビッグデータとは特定個人の情報を含まない(というか必要としない)大量のデータ(行動履歴、センシングデータ、ネットの書き込みなど)から新たな知見を発見するための手法であったにも関わらず、言葉だけが独り歩きし、バズワードと化して、口先だけのコンサルやマーケッターがほざく意味不明な世迷言に成り下がりつつある。そして、ビッグデータの名の下で行われる情報収集がセキュリティホールとなる懸念は現実のものになりつつある。というか、現実になっている。
ひとりひとりの開発者には悪意は無く、善意からの利便性追求のためであっても、結果的に悪用される危険性は充分に認識しなければならない。
けして危機感を煽るわけではないが、世間の無関心や無理解に多少イラつく昨今である。だからといって、こんな形で命を掛けようとは思わないけれど……。
【追記1】
「ITを知る者だけが書ける21世紀の警察小説」
え、マジで。続編企画あんの!
トラに勝つってすごいな、武岱!!(たぶん違)
【追記1.5】
なるほど、武岱別人説があるのか!
【追記2】
「個人情報のディストピア小説を政府マイナンバー担当者が読んでみた」
おい、お前、自分がディスられてるのがわかってるのか?
それだけ問題点がわかっているならば、ニンマリしてる場合じゃねーだろ!
【追記3】
自分が直接知っているのは3次請まで。それ以上は、それこそこっちが名刺を切らしておりましてと言われる立場だからわからん。デスマーチはせいぜい2ヶ月遅れくらいのもんだろ。特許庁? 俺は知らんよ!
【追記4】
他のひとの感想を巡回してみて、これを「いずれやってくる近未来」としているのが多くてびっくりした。確かに舞台設定は2017年以降かもしれないけれども、これは今、この瞬間に起こっていておかしくないことだよ。けして未来の話じゃない。