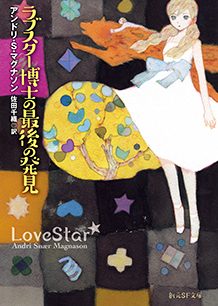『SFマガジン2015年2月号』

創刊55周年記念号というわりに、特別な記事は無かったような気が。隔月刊刊行に移行した一発目でもあるが、先月号が出ているので、実際に2か月空くのは次号の4月号からだし、いまいち実感が無く。
特集記事の「PSYCHO-PASS サイコパス2」も映画の宣伝レベルで終わり。まがりなりにも文芸誌としては、もっと突っ込んだ記事が欲しかったかもと思いつつ、映画を見に行けていないので、ネタバレされてもという気も。
サイコパス2のテーマは "What's color?" なのだけれど、横山えいじ『おまかせ!レスキュー』の巻頭カラーネタがいい感じでかぶっていておもしろかった。鹿矛囲が「お前の色は何色だ?」と問いかけるシーンで、「白黒」って表示を出して欲しい(笑)
それよりも、この号は、冲方丁『マルドゥック・アノニマス』の連載がついに開始された号として記録されることになるだろう。新カトル・カールともいうべきクインテットの出現と、新しい仲間の登場、そして、あっさり退場とか、厳しすぎる。『ベロシティ』を超える壮絶な戦いが待ち受けるであろうことが予感され、喜ぶべきか、おののくべきか。
そもそも、ウフコックの死が描かれることは予告済みで、プロローグもガス室の描写から始まるのだからネタバレも糞も無いわけだが、やはり、愛すべきキャラクターとの別離がカウントダウンされ始めるのは心が痛い。
川端裕人『青い海の宇宙港』も連載開始。これ、まだ初回だけれど、これ絶対おもしろいやつだよ。王道の少年×冒険×科学文学。
円城塔『エピローグ』は、世界の大きな構成が見えてくる感じだけれど、あまりに支離滅裂すぎて、詳細がどうなっているのかよくわからない。『NOVA+』の短編「Φ(ファイ)」も、もしかしたら関係あるかもしれない。
○ 「製造人間は頭が固い "The Institutional Man"」 上遠野浩平
SFマガジン初登場ながら、まさかの統和機構ネタ。しかも、強化人間の出自をめぐるキーとなる小道具もあり、なぜこれがSFマガジンに載ったのかをいろいろと邪推してしまう。
△ 「どこかまったく別な場所でトナカイの大群が」 ケン・リュウ/古沢嘉通訳
なんだか合わなかった。仮想空間ならではの時間の流れの速さをうまく使っているのとは思うのだけれど。
○ 「影が来る」 三津田信三 《TSUBURAYA×HAYAKAWA UNIVERSE》
著者も言うように、ウルトラQというよりは怪奇大作戦とか、トワイライト・ゾーンネタ。そういえば、新聞記者って探偵と並んでこの手のミステリで主人公になることが多かったのだけれど、昨今のマスゴミ的な風潮からか、主人公が新聞記者というだけで昭和レトロを感じてしまう。
- 「長城〈中篇〉」 小田雅久仁
前篇だけで完結でもよかった気がするのだが、さらに連載は続く。この世界の論理的説明はつけられるのか、それとも、不条理な幻想で終わってしまうのか、雰囲気は嫌いじゃないだけに、結末のつけ方に期待したい。
- 「PSYCHO-PASS GENESIS(予告篇)」 吉上 亮
あまりに予告篇すぎて、拍子抜け。
○ 「と、ある日の兄と弟」 宮崎夏次系
最近、時々掲載されるコミック枠。なんで主人公は、親ではなく、兄だったんだろう。