昨年末のボクシングの感想です。続いてテレビ東京の試合です。
WBA世界スーパーフライ級タイトルマッチ
テーパリット・ゴーキャットジム(王者) vs 河野公平(同級8位)
河野はこれが3度目の世界挑戦。1度目(名城戦)と2度目(ロハス戦)では豊富なスタミナと手数を見せたが小差の判定負け、その後日本人ホープにも2連敗、気持ちが強く良い選手なのだがいまいち決定力に欠けるというイメージで、世界チャンピオンになるとは思えなかった。対するチャンピオンのテーパリットも日本で有名で亀田大毅、清水智信、名城信男などと対戦しいずれも勝利している。こちらも豊富なスタミナと手数が武器の日本人キラーだ。河野に訪れた3度目の挑戦だが、テーパリットが楽な挑戦者を選んだなという思いだった。おそらく本人以外は勝てると予想した人は少なかったのではないか。
この日のテーパリットはガードが甘く、KOを意識してか前のめりで戦っていたように思う。4R河野の左フックがテーパリットのあごをとらえると、テーパリットは前のめりにダウン。その後、ラッシュし2度のダウンを追加しKO勝利。これぞ番狂わせという一戦だった。
思えば2度目の挑戦(ロハス戦)でも素晴らしいパンチでKO寸前まで追い込んだ。河野はパンチ力があるのだと思う。もう少しパンチの精度が上がれば、豊富なスタミナを武器に面白いチャンピオンに化けるかもしれない。最後にテレビ中継の解説が苦労人だった「坂田健史」と「西岡利晃」だった。両者とも世界チャンピオンになるまで苦労したが、世界チャンピオンになってから強くなった。河野も同じ道を歩んで欲しい。
WBC世界スーパーフライ級タイトルマッチ
佐藤洋太(王者) vs 赤穂亮(同級5位)
佐藤はこれが2度目の防衛戦。「マジカルボックス」という独特なファイトスタイルで日本チャンピオンを5度防衛、世界戦でも判定ながら圧勝している。この選手の魅力はどこからパンチが出るかわかりにくいところ、そしてディフェンス技術にも自信があり、時にガードを下げて上半身の動きだけでパンチを避けることもある。対する赤穂は思い切りの良いパンチが魅力の典型的なファイター。戦前の大口なコメントはボクシングファンを期待させた。佐藤がうまくさばくか、赤穂がとらえるか、アウトボクサーvsファイターという真逆のスタイルの戦いとなった。
試合は佐藤の圧勝。佐藤のジャブが効果的に入り、赤穂の前進を止めた。また、佐藤がカウンターを狙う仕草を見せるため、これも赤穂の前進を止めたように思う。赤穂は終盤こそ思い切り攻撃したが、前半は全く手数が出なかった。そのためポイントで有利となった佐藤は気分よく試合を展開出来たのではないか。赤穂は戦前のビックマウスからすると、あまりにも慎重な試合振りには落胆した。今はまだ日本チャンピオンレベル、また再度やり直して欲しい。
12Rに発生した停電というアクシデント、難しい判断だが試合続行させたのは疑問が残る。また、これほどの白熱した試合をラウンドカットしたテレビ局には不満だった。佐藤が「勝ちに徹する」と負けにくいチャンピオンになりそうだ、まるで安定王者だった徳山昌守のように。
WBA世界スーパーフェザー級タイトルマッチ
内山高志(チャンピオン) vs ブライアン・バスケス(暫定王者)
これが6度目の防衛戦、世界戦でも相変わらずの倒しっぷりである。「ノックアウト・ダイナマイト」と呼ばれるKOパンチャーだが、過去に見てきたブンブンと振り回す選手ではない。アマチュアでの実績があり、左ジャブから丁寧に展開する実にスマートなボクシングだ。相手のバスケスは同級暫定王者で無敗の選手である。
試合は内山がプレッシャーをかけ、バスケスが足を使う展開。何度が内山のパンチがバスケスをとらえるも、バスケスは瞬間的に反らす技術があり、なかなか決定打を当てられない。しかし8Rに内山のパンチが1発当たると、それから約30秒のめった打ち。レフリーが試合を止めた。
内山は倒れない選手をKOする方法もよく知っている。最後の怒濤のラッシュは素晴らしかった。左右のパンチに力があり、顔面ボディー両方、全てのパンチに倒す力があるのは実に魅力的。ただどれだけ強くとも「阪東ヒーロー戦」「三浦隆司戦」でみせた打たれ弱さはどの試合でもつきまとう。相手が強ければ強いほど集中力は増すもの、今後も強豪を相手にスリリングな試合を見せて欲しい。
しかし暫定王者という仕組みは改めていらないと思った。統一戦とはいえ、今回のバスケスもやはり世界ランカーレベルの実力だった。あとボクシングでは過度な演出はいらないと思う。有名人が国歌斉唱を歌ったり、有名人がラウンドガールしたり、そんなところで貴重な番組時間を取るのであれば、カットした佐藤vs赤穂戦の1ラウンドでも放送して欲しい(後日、深夜放送でカットされたラウンドを放送したらしいが、その姿勢は素晴らしい)。
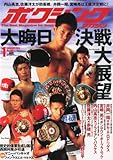 |
ボクシングマガジン 2013年 01月号 [雑誌] |
| クリエーター情報なし | |
| ベースボール・マガジン社 |
以上。














