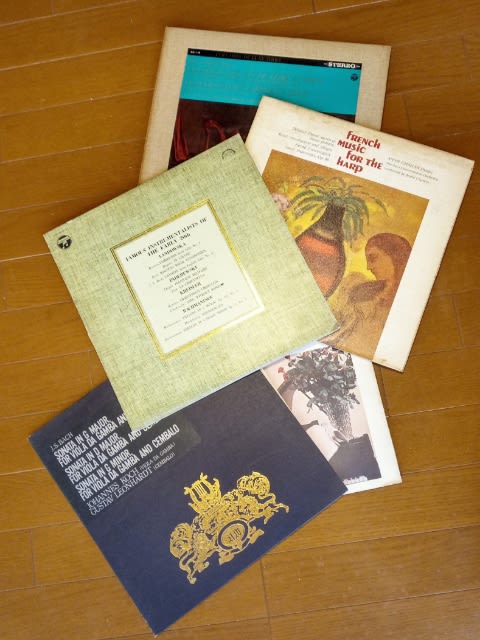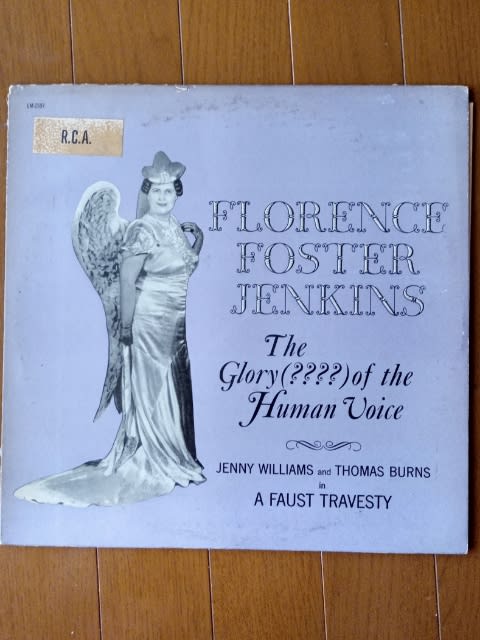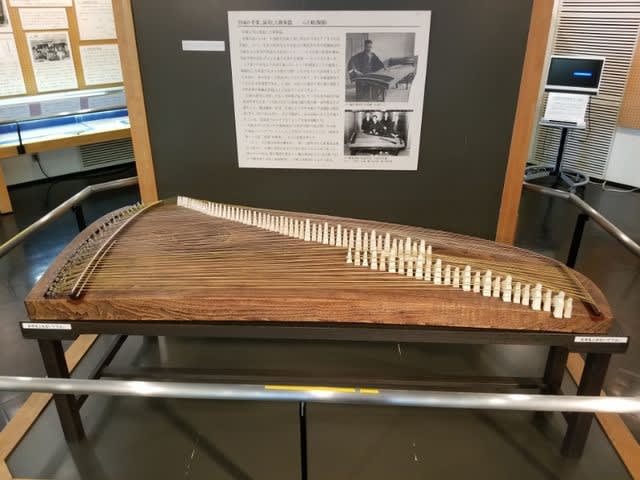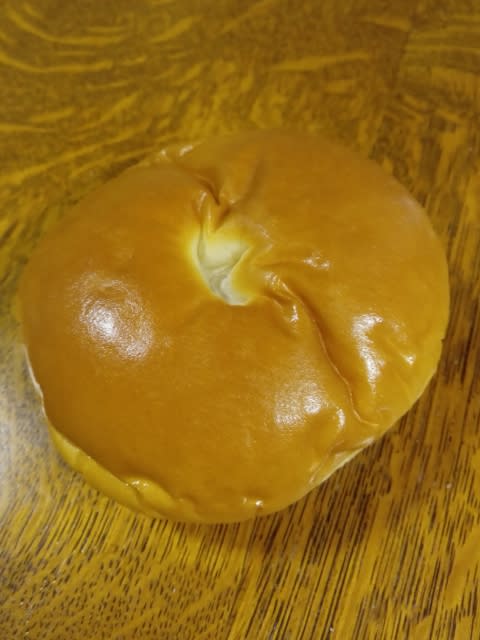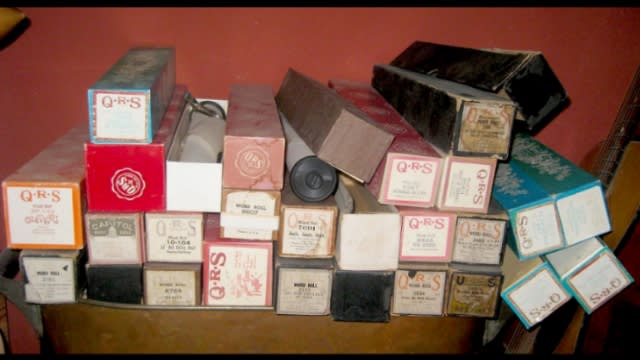昨日に引き続き、今日も冷たい雨の降る生憎のお天気となりました。つい一週間前までソメイヨシノが満開だったことなど信じられないような寒さで、小学校の子どもたちも震え上がっていました。
ところで、今日4月15日は天才レオナルド・ダ・ヴィンチの誕生日です。

レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452〜1519)のフルネームは『レオナルド・ディ・セル・ピエロ・ダ・ヴィンチ(Leonardo di ser Piero da Vinci)』といいます。因みによく略称で使われる『ダ・ヴィンチ』というのは『ヴィンチ村出身の』ということを意味なので、個人名の略称としては『レオナルド』と呼んだ方がより適切です。
1452年4月15日、レオナルド・ダ・ヴィンチは、フィレンツェ共和国から20kmほど離れた郊外のヴィンチ村で、当地の有能な公証人だったセル・ピエーロ・ダ・ヴィンチと農夫の娘カテリーナとの間に非嫡出子として誕生しました。幼少期に十分な教育を受けられなかったうえに左利きだったレオナルドは文字を書くと左右反転の鏡文字になってしまい、そのことが生涯にわたってコンプレックスだったといいます。
さて、《受胎告知》《東方三博士の礼拝》《岩窟の聖母》《聖アンナと聖母子》《洗礼者ヨハネ》《モナ・リザ(ラ・ジョコンダ)》といった数々の名作で知られるレオナルドですが、今日はそんな天才の初期の活動にスポットをあててみようと思います。
1466年頃、レオナルドは当時フィレンツェにおいて最も優れた工房の一つを主宰していた画家で彫刻家でもあったアンドレア・デル・ヴェロッキオ(1435〜1488)が運営する工房に入門しました。ヴェロッキオは入門当時のレオナルドをモデルにして

この《ダヴィデ》を制作したといわれています。
そんなヴェロッキオ工房が1472年から75年にかけてフィレンツェのサン・サルヴィ修道院より依頼を受けて制作されたのが

《キリストの洗礼》という宗教絵画です。

《キリストの洗礼》という宗教絵画です。
ヴェロッキオは、絵画や版画、鋳造、機械工学や、数学、音楽の才にも恵まれた当時のフィレンツェにおける一流の芸術家であったため、彼の工房には大勢の有望な若い弟子たちが集まっていました。その中にはレオナルドの他に、若き日のサンドロ・ボッティチェリ(1445〜1510)らもいたといいます。
ヴェロッキオの工房では絵画や彫刻など多岐にわたる分野の作品を制作していたため、弟子たちとの共同での制作が頻繁に行われていましたた。この《キリストの洗礼》も、そのうちのひとつにあたる作品です。
この絵でも様々な弟子が制作に関わっていると伝わりますが、その中の

画面左端に跪いてキリストを見上げている天使をレオナルドが担当したといわれています。因みに

レオナルドの天使の隣の天使を描いたのはボッティチェリだともいわれています。
この作品について、ジョルジョ・ヴァザーリ(1511〜1574)が1550年に出版した『画家・彫刻家・建築家列伝(芸術家列伝)』によると、この天使の出来栄えに驚嘆したヴェロッキオは筆を折ることを決めてしまい、以後二度と絵を描かなくなったという逸話が残されています。もっともこの逸話は現在では真実ではないとされていますが、この天使がヴァザーリにそんなことを書かせてしまうほどの出来栄えであることを示していることに違いはありません。
様々な伝説に事欠かないレオナルドですが、その天才ぶりは少年期から発揮されていたわけです。レオナルドの誕生日である今日、そんなことに思いを馳せてみるのもいいのではないでしょうか。