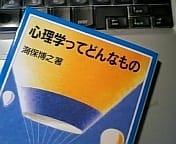
リテラシー(literacy)は、社会の中に、新しくて強力な道具が出てきて、その使い方や使える力を広く一般の人々が身につけることが必須になってきたときに、その使い方や使える力を意味する言葉として使われてきた。
リテラシーの本来の意味が「読み書き能力」なのは、紀元前3千年前頃に発明されたシュメール文字が、コミュニケーションの道具としての役割の重要性が認識されたことと無関係ではないであろう。
また、情報化社会の今は、「情報リテラシー」、「コンピュータ・リテラシー」、あるいは、「メディア・リテラシー」のように合成語としてリテラシーが使われているのも、情報、コンピュータ、メディアが、道具として重要な役割を果たしていることを反映している。ちなみに、出版本のサイト「アマゾン・コム」で「リテラシー」を検索すると、ヒットした245冊の8割以上がこの3つの合成語である。あと20年もすると、どんな新しいリテラシー合成語が生まれるのであろうか。
閑話休題。やがてその社会に出て活躍することになる子どもに、あらかじめ学校で、さまざまなリテラシーを身につけてほしいと考えるのは当然である。「確かな学力」として、リテラシーを想定するのも、これまた当然である。
そこで、本稿では、リテラシーについて、あらためてその意味、とりわけ、教育的な意味を考えてみた後に、「確かな学力」の一部としての「どんな」リテラシーを「いかに」子どもに身につけさせるか,さらに、そこにはどんな問題点が発生してくるかを考えてみたい。
リテラシーの本来の意味が「読み書き能力」なのは、紀元前3千年前頃に発明されたシュメール文字が、コミュニケーションの道具としての役割の重要性が認識されたことと無関係ではないであろう。
また、情報化社会の今は、「情報リテラシー」、「コンピュータ・リテラシー」、あるいは、「メディア・リテラシー」のように合成語としてリテラシーが使われているのも、情報、コンピュータ、メディアが、道具として重要な役割を果たしていることを反映している。ちなみに、出版本のサイト「アマゾン・コム」で「リテラシー」を検索すると、ヒットした245冊の8割以上がこの3つの合成語である。あと20年もすると、どんな新しいリテラシー合成語が生まれるのであろうか。
閑話休題。やがてその社会に出て活躍することになる子どもに、あらかじめ学校で、さまざまなリテラシーを身につけてほしいと考えるのは当然である。「確かな学力」として、リテラシーを想定するのも、これまた当然である。
そこで、本稿では、リテラシーについて、あらためてその意味、とりわけ、教育的な意味を考えてみた後に、「確かな学力」の一部としての「どんな」リテラシーを「いかに」子どもに身につけさせるか,さらに、そこにはどんな問題点が発生してくるかを考えてみたい。



















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます