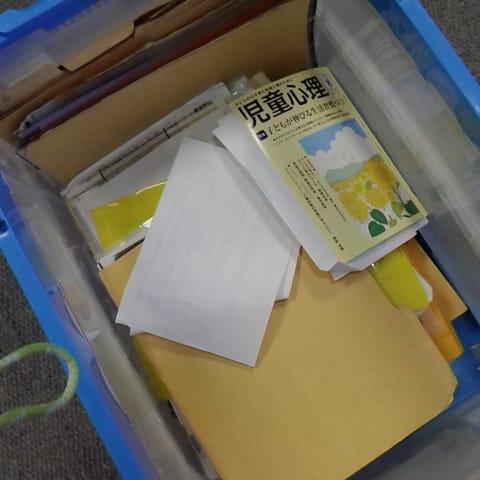心理学出身者の企業での活動分野
●人事関係
企業にとって人は宝です。採用から適材適所、さらに能力開発や心理面のケアまで、人事管理の仕事は多彩で重要です。こうしたところに、心理学が蓄積してきた知見はそのまま使えます。たとえば、テスト理論は採用人事に、教授・学習心理学は研修に、臨床心理学は心理ケアに、というように。
●企画関係
商品やイベント企画にしても、人の心、感性を無視しては消費者に受け入れてもらえません。心理学を学んだことが、どれほど心、感性をつかむのに役立つかは未知のところがありますが、少なくとも、それをつかむ観点や手法についての蓄積があります。もっと、こうした分野で活躍してほしいと思います。
●物作り関係
技術者と一緒に製品作りをするわけにはいきませんが、消費者ニーズを製品に反映させたり、製品が消費者に受け入れられるか、使いこなせるかをチェックする(ユーザビリティ検査)仕事は、心理学の実験室で使われている諸手法がそのまま使えます。ただ、心理学の卒業生に、こうした仕事の中に入っていくのを恐れるようなところがあります。もっと積極的に飛び込んでいってほしい分野です。

●人事関係
企業にとって人は宝です。採用から適材適所、さらに能力開発や心理面のケアまで、人事管理の仕事は多彩で重要です。こうしたところに、心理学が蓄積してきた知見はそのまま使えます。たとえば、テスト理論は採用人事に、教授・学習心理学は研修に、臨床心理学は心理ケアに、というように。
●企画関係
商品やイベント企画にしても、人の心、感性を無視しては消費者に受け入れてもらえません。心理学を学んだことが、どれほど心、感性をつかむのに役立つかは未知のところがありますが、少なくとも、それをつかむ観点や手法についての蓄積があります。もっと、こうした分野で活躍してほしいと思います。
●物作り関係
技術者と一緒に製品作りをするわけにはいきませんが、消費者ニーズを製品に反映させたり、製品が消費者に受け入れられるか、使いこなせるかをチェックする(ユーザビリティ検査)仕事は、心理学の実験室で使われている諸手法がそのまま使えます。ただ、心理学の卒業生に、こうした仕事の中に入っていくのを恐れるようなところがあります。もっと積極的に飛び込んでいってほしい分野です。