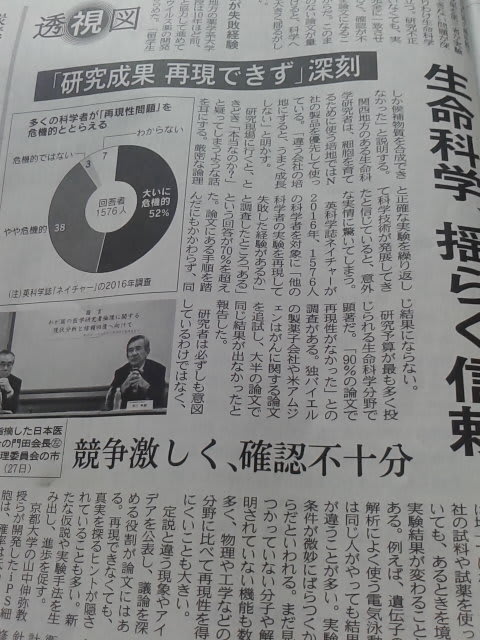忌まわしい記憶は、はやく忘れ去りたい。
とりわけ、当事者にとっては。
しかし、一方では、その忌まわしさを将来、再び起こさせてはならないという社会的な責務も感じる。
それが、記念日やモニュメントとして、あるいは歴史として残されることになる。
でも、その記念日、モニュメントも、年月ととも、風化する。
それでいいのだと思う。
風化したあとに残るものが、歴史である。
とりわけ、当事者にとっては。
しかし、一方では、その忌まわしさを将来、再び起こさせてはならないという社会的な責務も感じる。
それが、記念日やモニュメントとして、あるいは歴史として残されることになる。
でも、その記念日、モニュメントも、年月ととも、風化する。
それでいいのだと思う。
風化したあとに残るものが、歴史である。