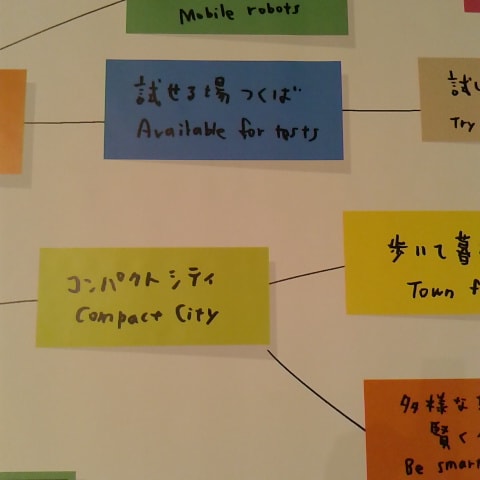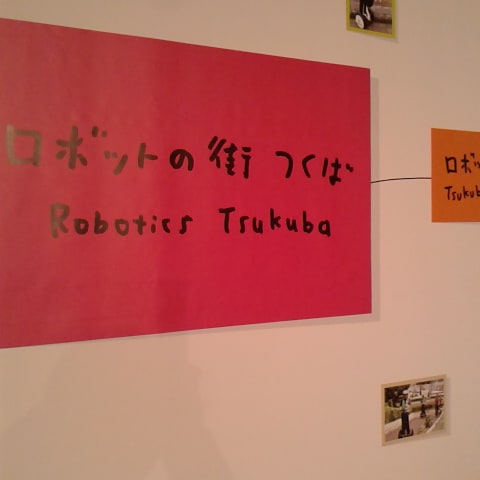あなたは「有用性のない厳密さ」をめざしますか?
それとも「有用性のある曖昧さ」をめざしますか?
(中原淳)
@@
前者は、基礎、理論志向の研究、は
後者は、応用、技術志向の研究となる。
両者は、研究活動の車の両輪のようなものだと思うが、
一人の研究者がこの両輪を動かすのはなかなか難しい。
いずれかを選ぶことになる。
これが、時には、基礎グループ対応用グループの対立図式となることがある。
それとも「有用性のある曖昧さ」をめざしますか?
(中原淳)
@@
前者は、基礎、理論志向の研究、は
後者は、応用、技術志向の研究となる。
両者は、研究活動の車の両輪のようなものだと思うが、
一人の研究者がこの両輪を動かすのはなかなか難しい。
いずれかを選ぶことになる。
これが、時には、基礎グループ対応用グループの対立図式となることがある。