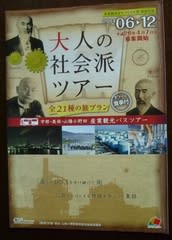津和野を歩く2回目 (2016.11)
山口に滞在中 堀庭園の紅葉が見ごろと聞いて再び津和野行く
奥津和野、昔は石見の国畑迫村、山から銀銅が取れたので徳川の天領だった
堀家は銅山年寄り役を世襲、300年続く名家 現在は国指定の名勝となっている

 クリック
クリック
建物内部も凝っていて立派だった


客殿「楽山荘」は庭の紅葉が見ごろ美しかった


この堀家が明治に建てた「畑迫病院」は地元の為の私立病院
その内部が展示(写真不可)
診察室、手術室、検査室、外科室、看護婦控室、病室など昭和まで続いた地域の病院を見る


前回行けなかった「森鴎外記念館」に行く
軍医として文筆家として名を成した鴎外の資料を展示
遺言で「石見人森林太郎として死せんと欲す」と言ったそうだ



隣に生家が残る

津和野川の鉄の橋を渡り 「西周旧居」に行く 国の史跡指定
西周は哲学者、西洋の思想啓蒙家、「理性」「主観」「哲学」「化学」「心理」等の言葉を創造した人
今、当たり前に使っている言葉が江戸時代には無かった訳

津和野名物「源氏巻」の店

期待して行った「杜塾美術館」は休館 津和野藩の庄屋屋敷だったから見たかったのに

郷土館も休館で見れず 残念だった どうも日にちが悪かった


太鼓谷稲荷神社の大鳥居 ここからJR津和野駅までの通りが有名な鯉の泳ぐ道で景観保存地区
鷺舞の像が建つ


多胡家老門もここにある


津和野は大きな町ではないが、2回目でやっと全体が判った気がする
安野光雅美術館まで見物したら2日から3日は必要だろう
津和野を歩く (2016.8)
津和野は島根県だけど、山口から車で行ったので「山口を歩く」に入れた
昔行ったことがあるが久しぶりである
国道9号線で北に向かう 途中の「徳佐」はリンゴの産地 寒いので山口県でもリンゴが実る


県境に道の駅「願成就温泉」がある 温泉に入れるので人気


この先のトンネルを通ると島根県
国道9号沿いに赤い鳥居があり、ここから津和野に向かう
急なカーブの道を下って、先ずは稲荷神社に向かう
正式名称は「太鼓谷稲荷神社」車で社殿下まで行くことが出来る
手洗い側にお供え用の「お揚げ」を売っている


本殿は立派だった 町を見渡せる高台にある
でも、稲荷神社は赤い鳥居の表門から通らねば価値がない
川沿いの表門近くに車を止めて、登る


鳥居のトンネルがジグザグに続く
歩いて登った表門は厳かだった


本殿下では車のお祓いをしていた

下までおりて、弥生神社へ ここは鷺舞で有名な神社
毎年7月に優雅に鷺が舞うそうだ (画像はインターネットから借用)



駐車場に車を止めて 殿町通りを駅に向かって歩く
鯉で有名な通りだ 整備されている


山陰の小京都言われ 日本遺産に指定された街
住民の協力で街並みを揃えているから観光地になる


カトリック教会は畳式だった ステンドグラスが美しい

JR津和野駅を通り過ぎると「安藤光雅美術館」がある
細密で楽しい安藤の絵が私は好きだが、以前ゆっくり見たので今回はパス

以前行かなかった山側の「乙女峠」と「栄明寺」に行く
乙女峠はキリシタン殉教の地
明治に長崎県浦上で発見された隠れキリシタン153人をこの津和野に連行
収容した場所に教会が建てられ、史跡として残る


栄明寺は古いお寺だった 藁屋根のお寺は珍しいが手入れされてないのが惜しい

木魚 板戸絵 ふすま絵も見応えあるし、お庭も立派


墓所には森鴎外の墓がある


森鴎外の旧宅、記念館には今回は行かず、次回に残した
おわり
山口県を歩く・・長門&下関北部 (2016.5)
5月の連休のさわやかな日に長門市方面をドライブした
目的地は外国雑誌に掲載されて人気の場所を見に行くため
 クリック
クリック
山口県のガードレールは黄色い、夏ミカン色だそうだ
瓦の赤い家も多い 単線の山陰線が走るのに出会えた

千畳敷公園から日本海を眺めるが、波静かで穏やかだった
黄砂ですっきりは見えない

ここからシャトルバスで目指す「元乃隅稲荷神社」に行く
バスは細い道を下り岬の先端へ行く
「元乃隅稲荷神社」は京都の伏見稲荷の迫力はないが、海を背景にする美しさだった

鳥居に上の賽銭箱がある みんなが狙って投げ入れる 入れば幸運

岬の岩の先端に「竜宮の潮吹き」という昔からの名所があるが、波穏やかで潮吹きは見れない


次は日本のキーウエストと言われる「角島大橋」を渡る
立派な橋が無料、観光客で賑わう

島の先端の灯台は日本海初の洋式灯台1875年に建てられた
内部も見たかったが、駐車場所が見つからず車内からの写真のみ

北浦海岸をドライブ 右側に海を見て快適
普段は車も少ないそうだが、休みの今日は対向車も多かった

川棚温泉で「たかせ」で名物「瓦そば」を食べる
西南の役で薩摩軍の兵士たちが瓦を焼いて料理したのをヒントに作ったもの
茶そばに牛肉、錦糸卵を乗せる


終わり