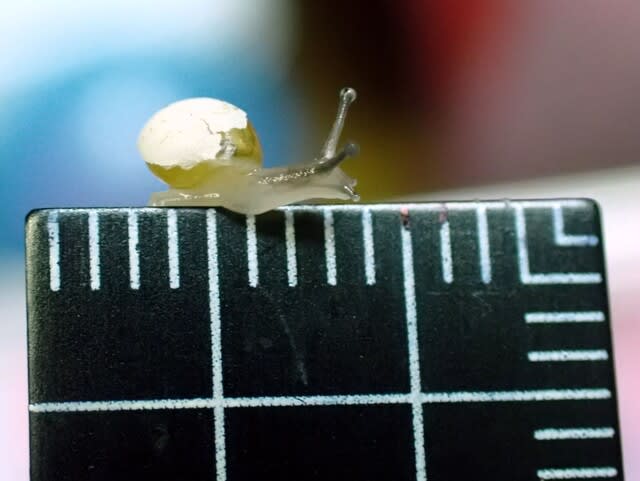庭で、ミカンの葉から転げ落ちて(たぶん)
落ちた先にあった、毒のある葉っぱをかじっていたアゲハチョウの幼虫を
部屋に連れてきて、ミカンの葉っぱで育てていました。

この子は本当にドジな子で
サナギになる時も、糸が切れてケースの底に転げ落ちてしまいました(^^ゞ

自然界なら・・・
食草からはぐれた時点で、幼虫は生き残れません。
サナギが地面に落ちてしまったら、即アリのエサです。
このような視点からすると
弱い(ドジな)遺伝子を持った個体が、人間の手を借りて成虫になると
累々と弱い(ドジな?)子孫を残すことになる、という考え方があるそうです。
確かにそうなのかもしれません。
でも逆に、虫のフンみたいな幼虫のとき人に見つけられて
「飼育してみようか」なんて思われて、安全な環境で餌を与えられ
無事に羽化して蝶になる個体って・・・
何万分の1くらいの「強運」を持っているのでは?運も実力のうちって言うし
なーんて、思ったりして。
ドジな幼虫を飼う事の言い訳にしてしまいます(^^ゞ
落ちたとき、お尻の糸も切れていたので粘着力の弱いマスキングテープで
サナギのお尻をキッチンペーパーに固定しました。
(この写真は、脱皮したあとの抜け殻です)

*
2、3日前からサナギが、翅の色が透けて見えて黒くなってきました。
そろそろかな、と思っていたら
15日の朝、飼育ケースの中で無事に羽化していました\(^o^)/
まだ翅が完全に伸び切っていないようです。
そっとケースから出して、窓の網戸に止まらせました。

翅に赤い模様があるので、メスのようですが
ホントは、これは当てにならないそうです。
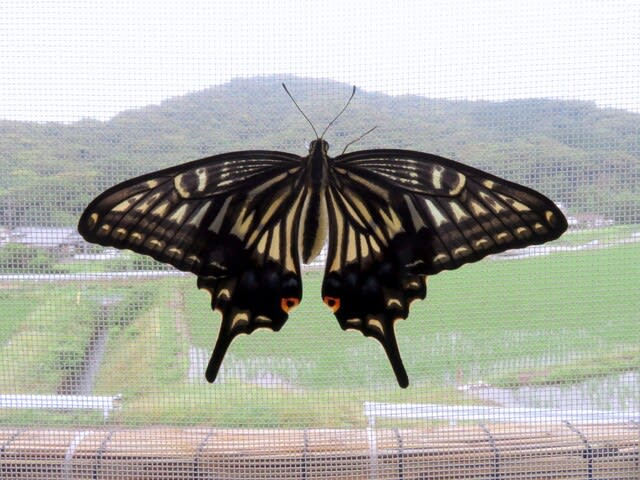
このまま翅が伸び切るまで待って
1時間後、ベランダへ行って空へ放しました。

滑空して、庭に降りると予想して放したのに
蝶はハタハタと羽ばたいて、みるみる間に上空へ昇っていきました。
あーーー、ダメダメ、危ない。
この辺りはツバメがビュンビュン飛び回っているので
見つかったら即エサです(。・Д・)ゞ
生きのびて、強運の子孫を残して欲しいと願い、蝶とお別れしました。
小さな幼虫を見つけてから、サナギになるまでの日数は18日間。
サナギになってから、蝶になるまで7日でした。
成虫と幼虫。
同じ命が入っているのが不思議なくらい、変身しました(#^.^#)

**
蝶になった子は、見つけた葉の名前で「樒ちゃん」(シキミ)でしたが
次にサナギになったのは「八朔ちゃん」
父が切ったハッサクの葉で見つけました。

八朔ちゃんは、クロアゲハの幼虫みたい。

3日前、6月15日に飼育ケースの蓋ウラでサナギになりました。

あと残っている幼虫は・・・
山椒の葉にいた「山椒ちゃん」と
金柑で見つけた「金柑ちゃん」
大きい方が山椒ちゃんです。

こんなにバラバラな食草で幼虫を見つけたのは初めてで
いろんな植物が生えていると、いろんな虫が来るのだと、楽しくなりました。

アゲハチョウの幼虫は、脱皮前と脱皮後の動かなくなる「眠」の状態が
ちょっと長くて心配になることが多いです。
今日も、山椒ちゃんと金柑ちゃんが、ピクリともせず心配です(´A`)
サナギの期間も、無事に羽化するか心配で・・・
心配ばかりするなら、飼育をやめればいいのに
それ以上に、羽化した時が嬉しいから、やめられないのかもです(^m^)
落ちた先にあった、毒のある葉っぱをかじっていたアゲハチョウの幼虫を
部屋に連れてきて、ミカンの葉っぱで育てていました。

この子は本当にドジな子で
サナギになる時も、糸が切れてケースの底に転げ落ちてしまいました(^^ゞ

自然界なら・・・
食草からはぐれた時点で、幼虫は生き残れません。
サナギが地面に落ちてしまったら、即アリのエサです。
このような視点からすると
弱い(ドジな)遺伝子を持った個体が、人間の手を借りて成虫になると
累々と弱い(ドジな?)子孫を残すことになる、という考え方があるそうです。
確かにそうなのかもしれません。
でも逆に、虫のフンみたいな幼虫のとき人に見つけられて
「飼育してみようか」なんて思われて、安全な環境で餌を与えられ
無事に羽化して蝶になる個体って・・・
何万分の1くらいの「強運」を持っているのでは?運も実力のうちって言うし
なーんて、思ったりして。
ドジな幼虫を飼う事の言い訳にしてしまいます(^^ゞ
落ちたとき、お尻の糸も切れていたので粘着力の弱いマスキングテープで
サナギのお尻をキッチンペーパーに固定しました。
(この写真は、脱皮したあとの抜け殻です)

*
2、3日前からサナギが、翅の色が透けて見えて黒くなってきました。
そろそろかな、と思っていたら
15日の朝、飼育ケースの中で無事に羽化していました\(^o^)/
まだ翅が完全に伸び切っていないようです。
そっとケースから出して、窓の網戸に止まらせました。

翅に赤い模様があるので、メスのようですが
ホントは、これは当てにならないそうです。
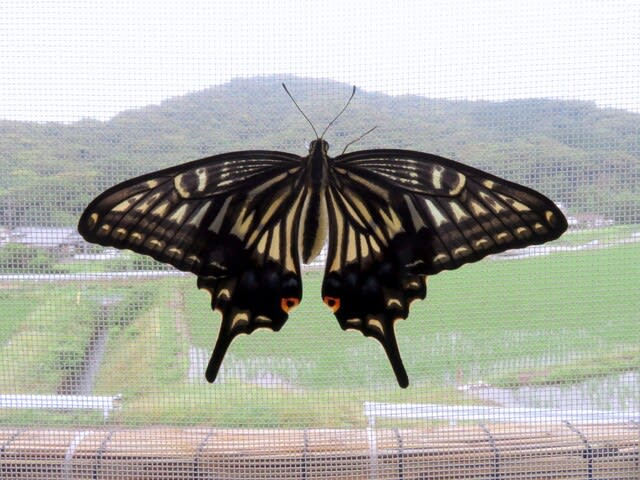
このまま翅が伸び切るまで待って
1時間後、ベランダへ行って空へ放しました。

滑空して、庭に降りると予想して放したのに
蝶はハタハタと羽ばたいて、みるみる間に上空へ昇っていきました。
あーーー、ダメダメ、危ない。
この辺りはツバメがビュンビュン飛び回っているので
見つかったら即エサです(。・Д・)ゞ
生きのびて、強運の子孫を残して欲しいと願い、蝶とお別れしました。
小さな幼虫を見つけてから、サナギになるまでの日数は18日間。
サナギになってから、蝶になるまで7日でした。
成虫と幼虫。
同じ命が入っているのが不思議なくらい、変身しました(#^.^#)

**
蝶になった子は、見つけた葉の名前で「樒ちゃん」(シキミ)でしたが
次にサナギになったのは「八朔ちゃん」
父が切ったハッサクの葉で見つけました。

八朔ちゃんは、クロアゲハの幼虫みたい。

3日前、6月15日に飼育ケースの蓋ウラでサナギになりました。

あと残っている幼虫は・・・
山椒の葉にいた「山椒ちゃん」と
金柑で見つけた「金柑ちゃん」
大きい方が山椒ちゃんです。

こんなにバラバラな食草で幼虫を見つけたのは初めてで
いろんな植物が生えていると、いろんな虫が来るのだと、楽しくなりました。

アゲハチョウの幼虫は、脱皮前と脱皮後の動かなくなる「眠」の状態が
ちょっと長くて心配になることが多いです。
今日も、山椒ちゃんと金柑ちゃんが、ピクリともせず心配です(´A`)
サナギの期間も、無事に羽化するか心配で・・・
心配ばかりするなら、飼育をやめればいいのに
それ以上に、羽化した時が嬉しいから、やめられないのかもです(^m^)