古町にあるホテル「イタリア軒」で行われた「エバンジェリスト(伝道師)来る! iPhone/iPadセミナー」に足を運ぶ。講師はソフトバンクモバイルの中山五輪男さん。なるほど、いろいろな活用方法があるんだな…と感心。
「ついでに…」と古町を散策してみたが、当然のように寂しい人通り…。やはり空きビル状態となっている旧大和デパートがうら悲しさを誘う。新潟島出身、古町全盛時代を知る私としては、やはり、ちょっと辛い光景だった。
まぁ、古町没落の原因は商店街としてのまとまりがない、各店舗の自助努力が足りない、交通機関のマイカーへの移行に対応しきれなかった…とさまざまな分析が可能だし、実際、それら複合的な原因が重なって今の惨状を呈していると思うのだが、商店街、各店舗にも同情の余地は少しはあると思う。(あくまでも少しだが…。)
それは、公共機関の郊外への移転が他の都市に比べて大規模だったことだ。
かつて古町近辺にあって移転していった公共施設と言えば、県庁、(白山から川向こうの新光町に移転)、その跡地に市役所が現NEXT21から移転、市図書館、それに新潟大学などがが挙げられる。(今後、新潟税務署、法務局も県庁近くに移転が予定されている。)
県庁の本庁舎(就労者約3千人)に併せて、周辺にあった各種団体も移転したので、就労人口として県庁移転で約5千人余りの減少を古町は受けたことになる。市役所も白山に止まったとは言え、古町から離れたことは、やはり商業的には痛かったことだろう。
しかし、古町にとって決定的に痛かったのは新潟大学の五十嵐への移転だったのではないだろうか?
新潟大学はかつて1980年始めまで新潟島内の西大畑(現新潟附属小・中学校)・旭町に立地していた。古町まで徒歩5分の位置である。新潟大学はもともと「たこ足大学状態」で、必ずしも全学部が新潟島にあった訳ではなく、学生数も今の約13000人(大学院生含む)に比べれば、ずっと少なかったとは思うが、当時でも人文学部・理学部・医学部・農学部・工学部(長岡市)教育学部(上越、長岡、新潟3分校)を有する総合大学であり、関係する教職員を合わせれば、相当数の関係者がいて、古町に相当なお金を落としていたことは間違いない。(名画座や古本屋は当時、古町に集中していた。)
その新潟大学が新潟市中心部から十数㎞離れた五十嵐キャンパスに移転していったのは昭和50年代中盤。(医学部、歯学部だけは大学病院がある関係で残留。)
当時、首都圏でも中央大学の八王子への移転を始めとして、大学の郊外移転がトレンドだったので、新潟大学(正確に言うと移転を推進した関係者)だけを責める訳にはいかないが、新潟市の都市計画というか、今の郊外化の先鞭を新潟大学がつけた格好になってしまった。
現実問題として、当時の西大畑のキャンパスは相当に手狭で、同地に建て替えることは困難だっただろうし、移転自体はやむを得ない判断だったとは思うのだが、十数㎞郊外の五十嵐(移転当時は本当に何もなく五十嵐砂漠と呼ばれた)に移転…という判断は都市計画上、やはり失敗だったのではないだろうか?せめて、新潟島内か駅から徒歩圏内に立地しておけば、街の中に学生が全く歩いていないという現在のような状況は避けられたのではないか…と悔やまれるこころだ。(あくまでも新潟島出身者の視点だが。)
計画が動き出した昭和40年代から実際に移転し始めた昭和50年代半ば、古町は県内随一の繁華街として栄華を誇っていた。新潟大学が移転してもどうってことないという判断だったのかも知れない。勝者の奢り。まさに栄光の絶頂にあって凋落の芽は蒔かれていた…と言う訳である。
首都圏では、かつて郊外に移転していった大学が中心部に回帰しているという。偏差値的に上位をキープしているのは郊外移転しなかった大学がほとんどだ。都市計画というのは、本当に数十年のスパンで考えなければならない。新潟大学移転問題はそう言う教訓を我々に教えてくれているのかも知れない。(今更教えられても手遅れなのだけど…。)
そんなことを思っての古町散策だった。















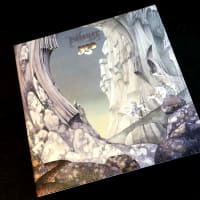



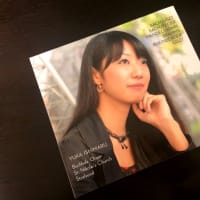


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます