
「値上げしないの?」とお客様に問われ、やむを得ない場合はするでしょうけど、未だ可処分所得が前年比で下回る状況下では、本来するべきじゃないんじゃないかと思いますとお答えしたら、リフレ派的なお説教を頂きました。
基本的に原価を加算して一定の利益を上乗せして販売価格とする、以前はお役所的と言われた方法。構造的にはその通りですし、手段としてその解をそのまま選択するのはごく自然で、否定する気もありません。
ただ構造(経済)と手段(経営)は別物でして、ただ流れに従うのみしか選択肢がないわけではありません。
日本文化の経済的側面を、経営面で特徴づけたとも思える江戸時代の「三方良し」で有名な近江商人十訓。その初訓は、「商売は世の為、人の為の奉仕にして利益はその当然の報酬なり」。ならば世が停滞し困る人が多いのであれば、改善するまで共に辛抱するのも手段の1つかも。勿論、最低限の利益確保は大前提ですから、企業努力は覚悟のうえで。
仁徳天皇は、食事の準備時刻になっても各家から煮炊きの煙が上がらないのを見て、民の困窮を察知し租税を免除。おかげで皇居は荒れ放題になりますが、煮炊きの煙が普通に上がるようになるまで、その状態を続けたという伝承が残るこの国。
中小零細企業における理念的経営への過ぎた執着に、経営管理的視点から批判があるのも承知してますが。
欧米化した経済体制へと移行されたこの国の経営には、やはり画一的な西洋化した経営がマッチしやすく、また求められるのでしょう。
しかしこの国の歴史文化が消去できるものではない以上、互いに駆逐関係というだけではなく、基礎文化と新文化の融合を図った独自の経営を模索する手段もあるはず・・・必ずしも合理的効率的方向にベクトルが向くわけではありませんけど。
若干形を変えながら、時代は巡るものかと。
基本的に原価を加算して一定の利益を上乗せして販売価格とする、以前はお役所的と言われた方法。構造的にはその通りですし、手段としてその解をそのまま選択するのはごく自然で、否定する気もありません。
ただ構造(経済)と手段(経営)は別物でして、ただ流れに従うのみしか選択肢がないわけではありません。
日本文化の経済的側面を、経営面で特徴づけたとも思える江戸時代の「三方良し」で有名な近江商人十訓。その初訓は、「商売は世の為、人の為の奉仕にして利益はその当然の報酬なり」。ならば世が停滞し困る人が多いのであれば、改善するまで共に辛抱するのも手段の1つかも。勿論、最低限の利益確保は大前提ですから、企業努力は覚悟のうえで。
仁徳天皇は、食事の準備時刻になっても各家から煮炊きの煙が上がらないのを見て、民の困窮を察知し租税を免除。おかげで皇居は荒れ放題になりますが、煮炊きの煙が普通に上がるようになるまで、その状態を続けたという伝承が残るこの国。
中小零細企業における理念的経営への過ぎた執着に、経営管理的視点から批判があるのも承知してますが。
欧米化した経済体制へと移行されたこの国の経営には、やはり画一的な西洋化した経営がマッチしやすく、また求められるのでしょう。
しかしこの国の歴史文化が消去できるものではない以上、互いに駆逐関係というだけではなく、基礎文化と新文化の融合を図った独自の経営を模索する手段もあるはず・・・必ずしも合理的効率的方向にベクトルが向くわけではありませんけど。
若干形を変えながら、時代は巡るものかと。


















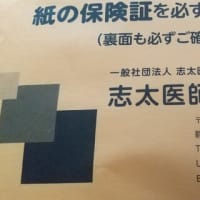

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます