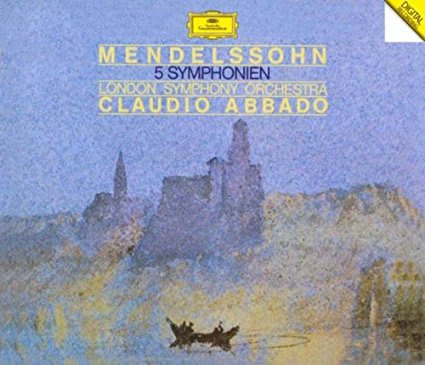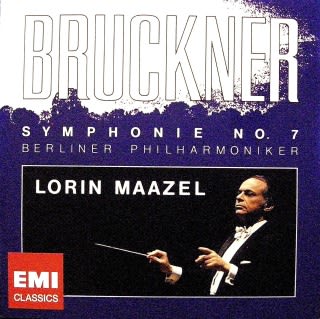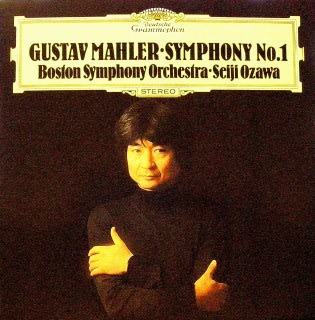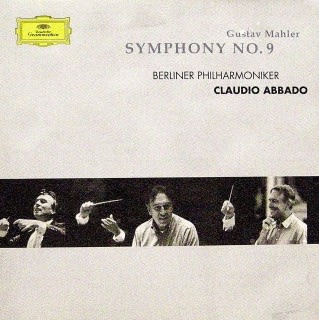R・シュトラウス:アルプス交響曲
夜
日の出
登り道
森に入る
小川に沿って歩む
滝で
幻影
花咲く高原で
牧場で
茂みや藪で道に迷う
氷河で
危険な瞬間
頂上で
幻
霧が立ち上る
太陽が陰り始める
悲歌
嵐の前の静けさ
雷雨と嵐、下山
日没
結尾
夜
指揮:ダニエル・ハーディング
管弦楽:サイトウ・キネン・オーケストラ
オーボエ:フィリップ・トーンドゥル
ホルン:ラデク・バボラク
トランペット:ガボール・タルコヴィ
録音:2012年8月23、25日、キッセイ文化ホール(長野県松本文化会館)<ライヴ録音>
CD:ユニバーサルミュージック UCCD51021
指揮のダニエル・ハーディング(1975年生まれ)は、イギリス、オックスフォード出身。サイモン・ラトルのアシスタントを務め、1994年にバーミンガム市交響楽団を指揮してデビュー。これがクラウディオ・アバドに認められ、1996年ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団を指揮する。同年には、最年少指揮者としてBBCプロムスにもデビューを果たす。2003年マーラー室内管弦楽団初代音楽監督就任。2004年ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団と初共演を行う。2002年シュヴァリエ勲章を受賞。2007年ロンドン交響楽団首席客演指揮者に就任。同年スウェーデン放送交響楽団音楽監督に就任。2016年パーヴォ・ヤルヴィの後任としてパリ管弦楽団音楽監督に就任した。このようにハーディングは、現在、世界の若手指揮者の中の旗手ともいうべき存在に成長を遂げている。日本とも関わりが深く、1993年タングルウッド音楽祭で小沢征爾に師事したほか、2012年軽井沢大賀ホール初代芸術監督に就任、さらに2011年~2016年新日本フィルハーモニー交響楽団のミュージック・パートナーを務めた。
サイトウ・キネン・オーケストラは、長野県松本市で毎年8、9月に開かれる「セイジ・オザワ 松本フェスティバル(旧称:サイトウ・キネン・フェスティバル松本)」で編成されるオーケストラで、公益財団法人サイトウ・キネン財団が運営に当たっている。 桐朋学園創立者の一人である斎藤秀雄の没後10年に当たる1984年、斎藤の弟子の小澤征爾と秋山和慶を中心に、国内外で活躍する斎藤の教え子たちが結集し、同年9月に東京と大阪で開かれた「斎藤秀雄メモリアル・コンサート」で特別編成された桐朋学園斎藤秀雄メモリアル・オーケストラがその母体。設立当初は小澤・秋山の意思に共感した斎藤の門下生100名以上が国内外より集まり演奏会を開催。1992年9月に長野県松本市で「サイトウ・キネン・フェスティバル松本」が開催され、以後同フェスティバルに合わせてオペラ・声楽曲の上演、シンフォニーコンサート、音楽塾を開催するほか、東京でもコンサート活動を行っている。世界的にも高い評価を受けているオーケストラで、2008年グラモフォン誌による「世界のトップ20オーケストラランキング」で19位(日本から唯一の選出)に選出された実績を持つ。 年度ごとに編成されるオーケストラのため、各パートのメンバーは不定期出演。指揮は、小澤征爾(総監督)のほか、秋山和慶、飯守泰次郎、下野竜也がその都度担当している。
R・シュトラウスのアルプス交響曲op.64は、1915年に完成した単一楽章の交響曲である。 初演は、1915年10月28日、ベルリン、フィルハーモニーでR・シュトラウスの指揮、シュターツカペレ・ドレスデンの演奏で行われた。交響曲とはなっているが、実質的には22からなる連作交響詩と言ってもいい内容となっている。R・シュトラウスが若い時に登ったドイツ・アルプスのツークシュピッツェの印象をもとに作曲された作品で、全部で22の場面の情景が描かれている。R・シュトラウスといえば、交響詩については名作を多く遺しており、この得意の手法を基に新たな交響曲をつくり上げようといと意図したもののようだ。22の表題の曲が流れるように進む展開は、リスナーとっては、自分がアルプス山脈を走破する気分でこの曲を鑑賞でききるわけで、特に山が好きなリスナーにとってはこの上ない快適な音楽に違いない。22の各部分は、切れ目なく演奏される。第1曲目の「夜」は、冒頭のゆっくりとした下降音型の夜の動機から始まり、トロンボーンが示す山の動機が荘重に響き渡る。そして、最後は、さまざまな動機が懐かしむように回想される第21曲目の「結尾」を経て、第1曲目の「夜」と同じ「夜」を表現する第22曲目でこの交響曲は終わる。これほど赤裸々に自然のありのままの姿を表現する音楽を聴き終えると、何とも言えない爽快感が感じられる。
このCDは、長野県松本市で行われた2012年の「サイトウ・キネン・フェスティバル松本」のライヴ録音盤である。ちょうど20周年という記念の年に当たっていたため一層の盛り上がりを見せたが、残念ながら小澤征爾総監督は健康上の理由で指揮をすることはなかった。代わって指揮をしたのが、ダニエル・ハーディングであった。サイトウ・キネン・オーケストラは、常設のオーケストラとは異なり、音楽祭の度にメンバーが変わる。このハンディをこれまで小澤征爾総監督の手腕で最高の演奏へとまとめ上げてきたのである。そうなると、ダニエル・ハーディングが、この個性の強いサイトウ・キネン・オーケストラの団員をまとめ上げることができるのか、という一抹の不安が頭をもたげる。ところが、このCDを聴き始めると、その不安は徐々に一掃されることに気付く。私は、これまで何度もアルプス交響曲の演奏を聴いてきたが、これほど感動的な演奏を滅多に聴いたことはない。オーケストラメンバー一人一人の熱気が、火の玉のようになって演奏会場を覆い尽くす。単にスケールの大きい表現と言ったような月並みの演奏内容でなく、指揮者とオーケストラのメンバーが一体となり、神々しいアルプス山脈の細部にわたり、ある時は力強く、ある時は清々しくも、あくまで大らかに表現し尽くすのである。特に、第18曲:嵐の前の静けさ、や第19曲:雷雨と嵐、下山などは、手に汗をかきながら聴く有様。一人一人の楽団員から自然に湧き上がる自然への讃歌が、輝かしくも会場全体に響き渡る様子が生き生きと聴き取れる。全ての歯車が十二分にかみ合った演奏とはこういうものかと感じ入った次第である。サイトウ・キネン・オーケストラ、そしてダニエル・ハーディングの実力や恐るべし。(蔵 志津久)