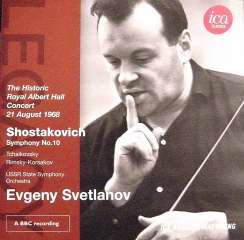フランク:交響曲ニ短調
:交響詩「プシシェ」より
指揮:エマニュエル・クリヴィヌ
管弦楽:国立リヨン管弦楽団
CD:日本コロムビア DENON COCO‐73185
セザール・フランク(1822年―1890年)は、ベルギー出身で、フランスで活躍した作曲家・オルガニストである。パリ音楽院で学び、宗教音楽を中心に音楽活動を展開した。1871年にはサン=サーンスやフォーレらとともにフランス国民音楽協会の設立に加わり、1872年にはパリ音楽院の教授に迎えられている。これだけの経歴を見ると、音楽生活はさぞ順風満帆であったかのように思われるが、今回の交響曲ニ短調の初演の時(フランク68歳)は、「この曲は交響曲ではない」といった辛辣な批評を浴びて、全く評価されなかったというから驚きだ。現在では、フランク:交響曲ニ短調は、フランスの作曲家の交響曲というよりも、交響曲の歴史上、重要な作品であり、その劇的であると同時に、深遠な情緒を湛えた曲想は、今聴いても一際光り輝くほどだ。フランク自身は、大器晩成の典型みたいな作曲家(主要な作品は生涯の最後の10年間に集中している)だ。そして、当時の時代を先取りしたみたいな曲が少なくなく、当時の保守的な音楽家はから見れば、フランクの作品は「取るに足りないもの」と軽んじていた傾向にあったようだ。そんな風潮の中、弦楽四重奏曲がやっと支持を受けたわけだが、フランクは「ようやく時代が私に近づいてきたようだ」と語ったという。
このフランクの代表作である交響曲ニ短調は、現在ではあらゆる交響曲の中でも傑作の一つとして評価が高く、これまで、多くの巨匠指揮者が数多くの録音を残している。フランクの作品は、純フランス音楽というよりは、フランス音楽とドイツ・オーストリア音楽の両方の要素を取り込んだ曲が多いが、この交響曲ニ短調は、その典型的な一曲であろう。このため、これまでドイツ・オーストリア系の指揮者も積極的に取り上げてきている。その典型的な事例がフルトヴェングラーの録音である。一瞬ブルックナーの音楽を聴いているような錯覚に陥るほど、その重厚な音づくりには敬服してしまうのだが、どうしても「確かフランクはフランス音楽の作曲者だったよね」という思いが何時も脳裏を過ぎる。そして、このフルトヴェングラーの残した録音は、その後の指揮者がフランク:交響曲ニ短調を演奏する際に、呪縛のように包み込む。フランス系の指揮者であるシャルル・ミュンシュやポール・パレーでさえ、その指揮するフランク:交響曲ニ短調の録音を今聴いてみると、ドイツ・オーストリア系の交響曲の匂い、というよりフルトヴェングラーの匂いがどうしてもついて回っているように、思えてならない。そんな時、エマニュエル・クリヴィヌが国立リヨン管弦楽団を指揮した今回のCDに出会い、私は思わず「フランク:交響曲ニ短調はこれが本物の響きだ」と感じ入った。
つまり、長年のもやもやがこのCDを聴いたとき初めて霧散して、ようやく本物のフランク:交響曲ニ短調の音に遭遇できた満足感に浸ることができたのだ。フランクは、特定の同一主題が反復使用される、所謂“循環形式”をしばしば作曲に用いているが、この交響曲ニ短調も例外でなく、循環形式が巧みに取り入れられ、効果を挙げている。全体は3楽章からなる。第1楽章を指揮するクリヴィヌは、実に静かに曲に入り込む。従来の指揮者が闇雲に大きな音だけを出すのとは大違いだ。あたかも自然に曲の盛り上がりを待つようでもある。決して音を叩きつけるようなことはしない。それでいて地の底からエネルギーが徐々に盛り上がる様を演出する際の絶妙のタイミングには脱帽させられる。第2楽章は、クリヴィヌの真価が最大限に発揮されている楽章だ。ハープと弦のピチカート、それにイングリッシュ・ホルンの音色が馥郁と香るように演奏される。そして、クリヴィヌと国立リヨン管弦楽団の絶妙の駆け引きは、聴くものをあたかも夢の中にいるかの如く感じさせる。第3楽章もクリヴィヌは、他の指揮者が行進曲を演奏するかのごとく指揮するようなことは決してしない。優雅に音の深い森に自ら分け入るような深淵さがそこにはある。クリヴィヌ&国立リヨン管弦楽団のフランク:交響曲ニ短調は、この曲が限りなく詩的な交響曲であることを、初めて教えてくれた演奏と言っていいのではないか。
エマニュエル・クリヴィヌ(1947年生まれ)は、グルノーブルの生まれのフランスの指揮者。当初はヴァイオリンを学ぶ。16歳でパリ・コンセルヴァトワールを首席で卒業し、エリザベート王妃音楽院でヘンリック・シェリングに師事する。卒業後はシュナイダーハーンとの共演などで話題を集めるなどヴァイオリニストとして活躍。その後カール・ベームと出遭って指揮者への転向を決心する。1976年から1983年までフランス放送新フィルハーモニー管弦楽団(現フランス放送フィルハーモニー管弦楽団)の常任指揮者を務める。その後、1987年から2000年までリヨン国立管弦楽団の音楽監督を務め、そのとき実力派指揮者としてその名を知られる。このCDの録音は1992年で、クリヴィヌがリヨン国立管弦楽団の音楽監督を務めてから5年が経過した時のもので、両者の気心が充分に合っている。交響曲ニ短調と一緒にカップリングされているフランク:交響詩「プシシェ」も交響曲ニ短調に劣らぬ指揮ぶりで秀逸。(蔵 志津久)