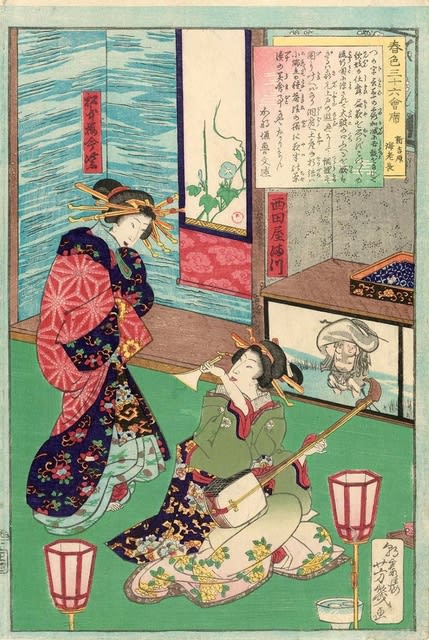これは小林清親(こばやし きよちか・弘化4〜大正4・1847〜1915年)の
浮世絵だ。
制作年は明治17(1884)年、タイトルは「武蔵百景之内 不忍弁天」とある。
池に浮かぶ建物が弁天堂だろう。
芸者がいるのは傍の料理茶屋か。
大鼓があり、三味線のばちがある。
宴の前だろうか、芸者も簡素な着物だ。

浮世絵だ。
制作年は明治17(1884)年、タイトルは「武蔵百景之内 不忍弁天」とある。
池に浮かぶ建物が弁天堂だろう。
芸者がいるのは傍の料理茶屋か。
大鼓があり、三味線のばちがある。
宴の前だろうか、芸者も簡素な着物だ。