繁栄の神学に拠れば、信仰を持つ者は祝福を約束され、更に捧げれば更に富む者となると理解できると思います。そして、その説明にはそれなりな聖書の言葉が根拠として挙げられます。しかし、聖書神学の手法によってもう一度その考えを検討すれば、その結論は不確実なものであると私は考えています。私なりの手順でご説明したいと思います。
先ず、聖書の記述の中で、繁栄の神学の考え方を支持しないと思われる部分について確認をしてみたいと思います。
旧約聖書の始めの方のモーセ五書の中に、神様の言葉として次のような記述が残されています。
貧しい者はいつまでも国のうちに絶えることがないから、わたしは命じて言う、『あなたは必ず国のうちにいるあなたの兄弟の乏しい者と、貧しい者と に、手を開かなければならない』。 (申命記15章11節)
この章では神様の祝福が多く語られているのですが、同時に乏しい者、貧しい者が絶えることはないということにも度々言及しているのです。繁栄が約束された同じイスラエルの民の中に、乏しい者や貧しい者が絶えることはないと神様が断言しているのです。彼らは約束の民ではないのでしょうか。彼らは神を信じていないのでしょうか。少なくとも、出エジプト第二世代で神の力有る業を見てカナンに定着した人々は忠実に神に従った様子がヨシュア記二十四章三十一節や士師記二章七節などからうかがえます。それでも神様は皆が繁栄するとは限らないことを断言しておられます。
翻って教会で語られる繁栄の神学はどうでしょうか。誰でも祝され、捧げれば更に祝されて豊になるかのように説かれることが多くはないでしょうか。そして、そのような生活にならないと失望したり、そうならない人が軽んじられたりということが起きてはいないでしょうか。
神様はそのような仲間には施し、助けなければならないことを述べておられます。そうすることによって、民全体として豊かで祝された存在となり、他の民族に神が共におられることを示すことを求めておられます。教会での実践がそのようなものになっていないとしたら、その信じている繁栄の神学は聖書的ではなく、神様の御心にも沿ってはいないということになります。
次に、新約聖書におけるイエス・キリストの教えから考えてみたいと思います。マタイによる福音書六章二十五節から三十四節において「何を食べようか、何を飲もうか、また何を着ようかと思い煩うな」ということが述べられています。このような内容は、豊かな人や繁栄した人に語るような言葉でしょうか。富んでいる人たちならば、そのようなことは最初から心配したり思い煩ったりしません。そして、神の国と神の義をまず求める者にはこれらのものも与えられるとイエス・キリストは言われたのです。溢れれるばかりに与えて繁栄させるとは言っておられません。
イエス・キリストが分かち合うことによって全体的に豊かな共同体となることを望んでおられたことは、裕福な青年に持ち物を売って施すように言われたこと(マルコによる福音書十章十七節―二十三節)等から明らかであると考えられます。そして、それはペテロやパウロなどの弟子達にも受け継がれています。
更に使徒行伝に見られる初代の諸教会の取組を見てみます。四章三十二節から三十五節の内容を見ると、信仰を持った者たちが金持ちになったというのではなく、お互いに助け合うことで乏しい者がいなかったという記述になっています。繁栄の神学の述べている内容とは異なった状況ではないでしょうか。
パウロを含む弟子たちの取組は使徒行伝十一章二十七節か-三十節に見出されます。飢饉の時に、ユダヤ地方のクリスチャンは繁栄して富んでいたので食料に困らなかったということにはなっていません。弟子達は援助を送ることを決定して、それをパウロとバルナバの手に委ねたというのです。彼らが食料を運んだということは考えにくいので、貨幣なり金銀なりを集めたことであろうと思われますが。
このように聖書箇所を見ていますと、繁栄の神学が述べているような状況が当然で当たり前の状況として聖書中にあらわされていることはないと判断でき、その教えや理解が不確かであると考えることができると思います。
聖書は全体的に調べて確認するものなので、今回の確認で聖書の記述が全体的な方向としては繁栄の神学を確立するものではないという判断できると思います。機会があれば別のアプローチでの考察もアップするかもしれません。
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
↑
よろしかったらクリックにご協力ください。
先ず、聖書の記述の中で、繁栄の神学の考え方を支持しないと思われる部分について確認をしてみたいと思います。
旧約聖書の始めの方のモーセ五書の中に、神様の言葉として次のような記述が残されています。
貧しい者はいつまでも国のうちに絶えることがないから、わたしは命じて言う、『あなたは必ず国のうちにいるあなたの兄弟の乏しい者と、貧しい者と に、手を開かなければならない』。 (申命記15章11節)
この章では神様の祝福が多く語られているのですが、同時に乏しい者、貧しい者が絶えることはないということにも度々言及しているのです。繁栄が約束された同じイスラエルの民の中に、乏しい者や貧しい者が絶えることはないと神様が断言しているのです。彼らは約束の民ではないのでしょうか。彼らは神を信じていないのでしょうか。少なくとも、出エジプト第二世代で神の力有る業を見てカナンに定着した人々は忠実に神に従った様子がヨシュア記二十四章三十一節や士師記二章七節などからうかがえます。それでも神様は皆が繁栄するとは限らないことを断言しておられます。
翻って教会で語られる繁栄の神学はどうでしょうか。誰でも祝され、捧げれば更に祝されて豊になるかのように説かれることが多くはないでしょうか。そして、そのような生活にならないと失望したり、そうならない人が軽んじられたりということが起きてはいないでしょうか。
神様はそのような仲間には施し、助けなければならないことを述べておられます。そうすることによって、民全体として豊かで祝された存在となり、他の民族に神が共におられることを示すことを求めておられます。教会での実践がそのようなものになっていないとしたら、その信じている繁栄の神学は聖書的ではなく、神様の御心にも沿ってはいないということになります。
次に、新約聖書におけるイエス・キリストの教えから考えてみたいと思います。マタイによる福音書六章二十五節から三十四節において「何を食べようか、何を飲もうか、また何を着ようかと思い煩うな」ということが述べられています。このような内容は、豊かな人や繁栄した人に語るような言葉でしょうか。富んでいる人たちならば、そのようなことは最初から心配したり思い煩ったりしません。そして、神の国と神の義をまず求める者にはこれらのものも与えられるとイエス・キリストは言われたのです。溢れれるばかりに与えて繁栄させるとは言っておられません。
イエス・キリストが分かち合うことによって全体的に豊かな共同体となることを望んでおられたことは、裕福な青年に持ち物を売って施すように言われたこと(マルコによる福音書十章十七節―二十三節)等から明らかであると考えられます。そして、それはペテロやパウロなどの弟子達にも受け継がれています。
更に使徒行伝に見られる初代の諸教会の取組を見てみます。四章三十二節から三十五節の内容を見ると、信仰を持った者たちが金持ちになったというのではなく、お互いに助け合うことで乏しい者がいなかったという記述になっています。繁栄の神学の述べている内容とは異なった状況ではないでしょうか。
パウロを含む弟子たちの取組は使徒行伝十一章二十七節か-三十節に見出されます。飢饉の時に、ユダヤ地方のクリスチャンは繁栄して富んでいたので食料に困らなかったということにはなっていません。弟子達は援助を送ることを決定して、それをパウロとバルナバの手に委ねたというのです。彼らが食料を運んだということは考えにくいので、貨幣なり金銀なりを集めたことであろうと思われますが。
このように聖書箇所を見ていますと、繁栄の神学が述べているような状況が当然で当たり前の状況として聖書中にあらわされていることはないと判断でき、その教えや理解が不確かであると考えることができると思います。
聖書は全体的に調べて確認するものなので、今回の確認で聖書の記述が全体的な方向としては繁栄の神学を確立するものではないという判断できると思います。機会があれば別のアプローチでの考察もアップするかもしれません。
↑
よろしかったらクリックにご協力ください。










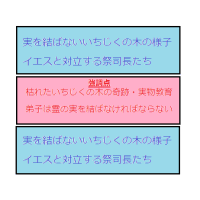





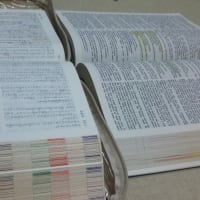
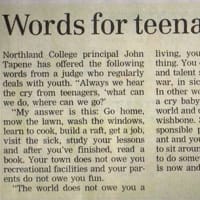







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます