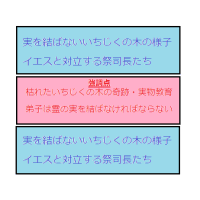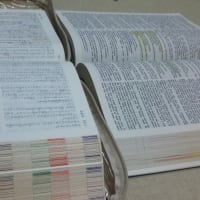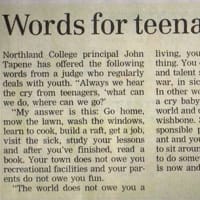導入
この物語の基本的なメッセージは締めくくりの48節~50節に有る。イエスが罪の赦しを宣言する部分である。同様な罪の赦しの宣言と、人々の非難の言葉は5章20、21節に見出される。ユダヤ的文書において、繰り返しは強調を表す。ルカは、「読者の皆さん、再確認しますよ。イエスは罪を赦す権威を持つ、神なるお方ですよ!!」と力強く呼びかけているのである。
人物の対比
パリサイ人、シモン
主な人物が二人いる。一人はイエスを食事に招待したパリサイ人のシモンであり、もう一人は彼の家にイエスを訪ねてきた女性である。
パリサイ人のシモンはイエスを食事に招待した。当時、ラビが人々に教えた後、誰かがそのラビを食事に招待するのは普通のことであった。ラビが会堂で説教した後であれば尚更であった。
しかし、シモンはラビへの尊敬や慰労の気持ちでこれをしたのではないことが彼のイエスに対する扱いから想像できる。おそらく、イエスを試したり、罠にかけたり、弱みを握ったり、もしくは利用するために招待したのであろう。
普通は招待された客は足を洗う水、時には温水をもらうのが当時の習慣であった。足を洗って拭うのは僕や奴隷の仕事であった。また、招待された人に接吻するのが当時の習わしであった。特に相手がラビであれば、尊敬を込めて足に接吻することもあった。そして、乱れた髪を整えるためにオリブ油などを頭につけるのであった。
この「習慣」であり「普通」のことを、シモンは招待した客であるはずのイエスに対して、一つも行わなかった。彼は基本的にイエスを受け入れては居なかったのである。
シモンがイエスに対する尊敬から招待したのではないことは、39節にある彼の心の言葉からもうかがえる。彼はやはりイエスを非難する口実を求めていたのであろう。イエスを訪ねてきた女性が、その町でもよく知られた「罪人」であり、その女性が近づくに任せたことを持って、シモンはイエスを「偽預言者」と断じている。
ユダヤ教の背景では、預言者は常人に無い識別力が有り、近くに来るだけでその人がどんな人物か判るとされていた。ユダヤの文献には「自分は預言者だ。」と言った王の話が出てくるそうだ。側近の者たちが、彼を試すために、良からぬ人物を彼の側に送り込んだのだが、王はそれに気付かなかった。側近の者たちは、偽預言者は殺さなければならないという規定に従って、その王を殺してしまった。シモンもこれと同じ考え方をしていたことになる。
罪深い女性
女性は罪深い女という表現がされている。福音書の記者は具体的なことは一切記録していないが、この女性は娼婦であったろうとする考えもある。29節でイエスはヨハネのバプテスマを受けた民に言及している。その流れから考えると、この女性もヨハネの説教を聞いて悔い改め、バプテスマを受けた人々の中にいたかもしれない。また、イエスの説教にも触れ、この方こそ、神の子羊、メシアだと信じたのであろう。
シモンの家にイエスが来ておられると伝え聞いた彼女は、イエスに感謝の念を表すために石膏の器に入った香油を持ってシモンの家に入って来た。
当時は、食事に招待された者でなくてもその場に来て話をしたりすることはゆるされた。また、貧しい者に施しをするようにと宗教的指導者達は教えていたから、食事をしている家に施しを求めてくる人のために、出入りする者を制止しないということがあった。それで、その町でもよく知られた罪人であるこの女性も入ってくることができたのであろう。
香油は高価であった。ベタニヤのマリヤがイエスの頭に香油を注いだ時、イスカリオテのユダが、「売ったら貧しい者に施しができた」と非難していることからも、香油がそれなりに価値の高いものであったことが判る。香油を買って取って置き、いざという時に売って金に換えるのが当時の財テクでもあった。
石膏と訳されている語は、英語ではアラバスターとなっている。北東部のダマスコで産出される石で、香油の品質を損なわずに保存できるとされた。
この女がシモンの家の食堂に入った時、彼女の目に映ったのは、食事の席に着いた人々の足であった。当時は食事は寝そべってする習慣があった。体の左側を下にして横になり、右手で食事をした。だから、足は食卓とは反対の方向に投げ出される形になった。
彼女は当然見知っているイエスの姿を探したであろう。そして、はっと息を呑んだはずである。イエスの足は汚れたままであった。彼女は愛する主、イエスがシモンに歓迎されていないことを一目で見て取った。そして、胸がつぶれるような気持ちになったのであろう。彼女は泣き出した。「泣きながら」と訳されている語は「哀しんで、嘆き哀しんで、もだえて」というニュアンスを持っている。
彼女には香油の他には何の用意も無かった。その家の主でもない女性にとっては、水の用意を命じる資格も無かった。しかし、自分の主、メシアと仰ぐイエスに自分の気持ちを表したい。それでその涙でイエスの足を濡らし始めたのであろう。
手拭いの用意は無かった。理由はわからないが、衣のすそで拭いたりすることは憚られたのであろう、彼女は自分の髪を解いて、その髪の毛でイエスの足を拭った。当時、女性はその髪の状態が良いことを誇りに思っていた。また、きちんとした髪はしっかり結い上げておくものであった。しかし、彼女はそういう女性の誇りを捨てて、髪を解いてイエスの足を拭いたのであった。
それから、彼女はイエスの足に接吻をした。用いられている動詞から、繰り返し接吻したことがわかる。ラビの足に尊敬の念を込めて繰り返し接吻することは普通であった。彼女はそのことによって、イエスをラビとして認め、それだけではなく、メシアとしても認めていることを表したのであろう。メシア預言を含むとされる詩篇二篇では、「御子(の足に)口づけせよ」と記されている。彼女の実践は、それに従ったものであったかもしれない。
イエスは横たわっているので、頭には手が届かない。彼女は持参した香油をイエスの足に塗った。イエスは、彼女にとって、その高価な香油を、その足に用いることさえためらう必要のない大事な主であった。
イエスのたとえ話
シモンの心中を察して、イエスは彼に向かって一つの例話を語る。二人の負債者がいる。一人は500デナリ、もう一人は50デナリの負債である。1デナリは当時の日当、日給にあたる。現在の東京であれば、前者は最低で二百八十七万六千円、後者は二十八万七千六百円となる。私達の生活感覚でそれがどれぐらいであろうと、とにかく二人は返済能力が無かった。それで貸主は借金の返済を免除してくれたのだが、この場合、どちらがより多く愛するかという質問がなされた。
このたとえ話を、目の前にいる二人に当てはめるならば、前者は罪深い女であり、後者はシモンであろう。この女性はその罪を多く赦されたから、もっと多くの愛を表したという理解のできる話になっている。
それでは、シモンは少し愛した分が有り、彼もキリストにあって救われたということになるだろうか?そうではない、シモンはイエスを必要とはしなかった。それに、愛を示すどころか、当時の習慣にも反する無礼な扱いをしたのである。そんな罪深い扱いをイエスに対してしたにも関わらず、彼には、自分が神に罪の赦しを求めるべき存在であるとは微塵も思っていなかったのだ。
ポイントのまとめ
最初に述べたように、ルカが意図し強調したポイントは第一に、イエスはメシア、救い主であり、罪を赦す権威を持つ神であるということにある。
第二のポイントは、自分はその救い主が必要で、神の赦しを請わなければならない存在だという自覚が必要であるということにある。
第三のポイントは、この女性のようにイエスに仕える姿勢を持たなければならないということにある。
適用
クリスチャンは基本的には先に述べたポイントの第一と第二を心に留めている人間であるから、今回は特に第三のポイントについて考えたいと思う。
1) イエスの足を洗うクリスチャン
現在この世にイエスは肉体を持って存在してはおられない。しかし、イエスを頭とする、主の御体なる教会が存在している。この世の歩みの中でつく私達の霊的な汚れを拭い合う、そういうクリスチャンであることを心掛けよう。
パウロは「キリストのことばを、あなたがたのうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くし互いに教え、互いに戒め・・・」(コロサイ3:16)と言っている。ペテロも「何よりもまず、互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪をおおうからであうる。」(1ペテロ4:8)と言っている。
これは、イエスの足を洗った女性が、純粋にイエスに対する尊敬と愛から、また、女性の誇りとされた髪を汚すことを厭わなかった謙遜の心に倣ってなされるべきである。
イエス自身がヨハネ13章においては、しもべ、奴隷の仕事であった足を洗うということを、弟子達に対してして見せている。そして、「あなたがたも互いに足を洗い合うべきである。」と言っておられる。
この女性が、イエスの足の汚れを見て泣き出したように、クリスチャンも遣わされた教会の状態に敏感である必要があり、また、執り成しの祈りを心掛ける存在である必要がある。
2) イエスの足に接吻するクリスチャン
繰り返し足に接吻するということは、その人を「尊敬する師、ラビ」と認めたということである。この女性がイエスを自分の師、またそればかりではなく、主、メシアと認めとように、また、それを繰り返し接吻することで表したように、クリスチャンも「イエスは私の主、救い主、私の神です。」という宣言を証を何度も何度も繰り返してする存在である。
イエスは復活後、弟子達が「わたしの証人」になると言われた。形はどうあれ、「イエスは私の主、救い主、私の神」という告白と宣言がいつも伴うクリスチャンでありたい。
3) イエスの足に香油を塗るクリスチャン
この女性はイエスを価値あるものを捧げるに値する方であるとして、イエスに栄光を帰したのである。クリスチャンも、様々な形でいつもイエスに栄光を帰する者であるべきである。自分の功績をひけらかすのではなく、自分の栄誉を求めるのではなく。自分のそれまでの労力や努力を惜しんだりしないで。イエスは私達のために、命をも惜しまれなかった方なのだから。
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
↑
よろしかったらクリックにご協力ください。
この物語の基本的なメッセージは締めくくりの48節~50節に有る。イエスが罪の赦しを宣言する部分である。同様な罪の赦しの宣言と、人々の非難の言葉は5章20、21節に見出される。ユダヤ的文書において、繰り返しは強調を表す。ルカは、「読者の皆さん、再確認しますよ。イエスは罪を赦す権威を持つ、神なるお方ですよ!!」と力強く呼びかけているのである。
人物の対比
パリサイ人、シモン
主な人物が二人いる。一人はイエスを食事に招待したパリサイ人のシモンであり、もう一人は彼の家にイエスを訪ねてきた女性である。
パリサイ人のシモンはイエスを食事に招待した。当時、ラビが人々に教えた後、誰かがそのラビを食事に招待するのは普通のことであった。ラビが会堂で説教した後であれば尚更であった。
しかし、シモンはラビへの尊敬や慰労の気持ちでこれをしたのではないことが彼のイエスに対する扱いから想像できる。おそらく、イエスを試したり、罠にかけたり、弱みを握ったり、もしくは利用するために招待したのであろう。
普通は招待された客は足を洗う水、時には温水をもらうのが当時の習慣であった。足を洗って拭うのは僕や奴隷の仕事であった。また、招待された人に接吻するのが当時の習わしであった。特に相手がラビであれば、尊敬を込めて足に接吻することもあった。そして、乱れた髪を整えるためにオリブ油などを頭につけるのであった。
この「習慣」であり「普通」のことを、シモンは招待した客であるはずのイエスに対して、一つも行わなかった。彼は基本的にイエスを受け入れては居なかったのである。
シモンがイエスに対する尊敬から招待したのではないことは、39節にある彼の心の言葉からもうかがえる。彼はやはりイエスを非難する口実を求めていたのであろう。イエスを訪ねてきた女性が、その町でもよく知られた「罪人」であり、その女性が近づくに任せたことを持って、シモンはイエスを「偽預言者」と断じている。
ユダヤ教の背景では、預言者は常人に無い識別力が有り、近くに来るだけでその人がどんな人物か判るとされていた。ユダヤの文献には「自分は預言者だ。」と言った王の話が出てくるそうだ。側近の者たちが、彼を試すために、良からぬ人物を彼の側に送り込んだのだが、王はそれに気付かなかった。側近の者たちは、偽預言者は殺さなければならないという規定に従って、その王を殺してしまった。シモンもこれと同じ考え方をしていたことになる。
罪深い女性
女性は罪深い女という表現がされている。福音書の記者は具体的なことは一切記録していないが、この女性は娼婦であったろうとする考えもある。29節でイエスはヨハネのバプテスマを受けた民に言及している。その流れから考えると、この女性もヨハネの説教を聞いて悔い改め、バプテスマを受けた人々の中にいたかもしれない。また、イエスの説教にも触れ、この方こそ、神の子羊、メシアだと信じたのであろう。
シモンの家にイエスが来ておられると伝え聞いた彼女は、イエスに感謝の念を表すために石膏の器に入った香油を持ってシモンの家に入って来た。
当時は、食事に招待された者でなくてもその場に来て話をしたりすることはゆるされた。また、貧しい者に施しをするようにと宗教的指導者達は教えていたから、食事をしている家に施しを求めてくる人のために、出入りする者を制止しないということがあった。それで、その町でもよく知られた罪人であるこの女性も入ってくることができたのであろう。
香油は高価であった。ベタニヤのマリヤがイエスの頭に香油を注いだ時、イスカリオテのユダが、「売ったら貧しい者に施しができた」と非難していることからも、香油がそれなりに価値の高いものであったことが判る。香油を買って取って置き、いざという時に売って金に換えるのが当時の財テクでもあった。
石膏と訳されている語は、英語ではアラバスターとなっている。北東部のダマスコで産出される石で、香油の品質を損なわずに保存できるとされた。
この女がシモンの家の食堂に入った時、彼女の目に映ったのは、食事の席に着いた人々の足であった。当時は食事は寝そべってする習慣があった。体の左側を下にして横になり、右手で食事をした。だから、足は食卓とは反対の方向に投げ出される形になった。
彼女は当然見知っているイエスの姿を探したであろう。そして、はっと息を呑んだはずである。イエスの足は汚れたままであった。彼女は愛する主、イエスがシモンに歓迎されていないことを一目で見て取った。そして、胸がつぶれるような気持ちになったのであろう。彼女は泣き出した。「泣きながら」と訳されている語は「哀しんで、嘆き哀しんで、もだえて」というニュアンスを持っている。
彼女には香油の他には何の用意も無かった。その家の主でもない女性にとっては、水の用意を命じる資格も無かった。しかし、自分の主、メシアと仰ぐイエスに自分の気持ちを表したい。それでその涙でイエスの足を濡らし始めたのであろう。
手拭いの用意は無かった。理由はわからないが、衣のすそで拭いたりすることは憚られたのであろう、彼女は自分の髪を解いて、その髪の毛でイエスの足を拭った。当時、女性はその髪の状態が良いことを誇りに思っていた。また、きちんとした髪はしっかり結い上げておくものであった。しかし、彼女はそういう女性の誇りを捨てて、髪を解いてイエスの足を拭いたのであった。
それから、彼女はイエスの足に接吻をした。用いられている動詞から、繰り返し接吻したことがわかる。ラビの足に尊敬の念を込めて繰り返し接吻することは普通であった。彼女はそのことによって、イエスをラビとして認め、それだけではなく、メシアとしても認めていることを表したのであろう。メシア預言を含むとされる詩篇二篇では、「御子(の足に)口づけせよ」と記されている。彼女の実践は、それに従ったものであったかもしれない。
イエスは横たわっているので、頭には手が届かない。彼女は持参した香油をイエスの足に塗った。イエスは、彼女にとって、その高価な香油を、その足に用いることさえためらう必要のない大事な主であった。
イエスのたとえ話
シモンの心中を察して、イエスは彼に向かって一つの例話を語る。二人の負債者がいる。一人は500デナリ、もう一人は50デナリの負債である。1デナリは当時の日当、日給にあたる。現在の東京であれば、前者は最低で二百八十七万六千円、後者は二十八万七千六百円となる。私達の生活感覚でそれがどれぐらいであろうと、とにかく二人は返済能力が無かった。それで貸主は借金の返済を免除してくれたのだが、この場合、どちらがより多く愛するかという質問がなされた。
このたとえ話を、目の前にいる二人に当てはめるならば、前者は罪深い女であり、後者はシモンであろう。この女性はその罪を多く赦されたから、もっと多くの愛を表したという理解のできる話になっている。
それでは、シモンは少し愛した分が有り、彼もキリストにあって救われたということになるだろうか?そうではない、シモンはイエスを必要とはしなかった。それに、愛を示すどころか、当時の習慣にも反する無礼な扱いをしたのである。そんな罪深い扱いをイエスに対してしたにも関わらず、彼には、自分が神に罪の赦しを求めるべき存在であるとは微塵も思っていなかったのだ。
ポイントのまとめ
最初に述べたように、ルカが意図し強調したポイントは第一に、イエスはメシア、救い主であり、罪を赦す権威を持つ神であるということにある。
第二のポイントは、自分はその救い主が必要で、神の赦しを請わなければならない存在だという自覚が必要であるということにある。
第三のポイントは、この女性のようにイエスに仕える姿勢を持たなければならないということにある。
適用
クリスチャンは基本的には先に述べたポイントの第一と第二を心に留めている人間であるから、今回は特に第三のポイントについて考えたいと思う。
1) イエスの足を洗うクリスチャン
現在この世にイエスは肉体を持って存在してはおられない。しかし、イエスを頭とする、主の御体なる教会が存在している。この世の歩みの中でつく私達の霊的な汚れを拭い合う、そういうクリスチャンであることを心掛けよう。
パウロは「キリストのことばを、あなたがたのうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くし互いに教え、互いに戒め・・・」(コロサイ3:16)と言っている。ペテロも「何よりもまず、互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪をおおうからであうる。」(1ペテロ4:8)と言っている。
これは、イエスの足を洗った女性が、純粋にイエスに対する尊敬と愛から、また、女性の誇りとされた髪を汚すことを厭わなかった謙遜の心に倣ってなされるべきである。
イエス自身がヨハネ13章においては、しもべ、奴隷の仕事であった足を洗うということを、弟子達に対してして見せている。そして、「あなたがたも互いに足を洗い合うべきである。」と言っておられる。
この女性が、イエスの足の汚れを見て泣き出したように、クリスチャンも遣わされた教会の状態に敏感である必要があり、また、執り成しの祈りを心掛ける存在である必要がある。
2) イエスの足に接吻するクリスチャン
繰り返し足に接吻するということは、その人を「尊敬する師、ラビ」と認めたということである。この女性がイエスを自分の師、またそればかりではなく、主、メシアと認めとように、また、それを繰り返し接吻することで表したように、クリスチャンも「イエスは私の主、救い主、私の神です。」という宣言を証を何度も何度も繰り返してする存在である。
イエスは復活後、弟子達が「わたしの証人」になると言われた。形はどうあれ、「イエスは私の主、救い主、私の神」という告白と宣言がいつも伴うクリスチャンでありたい。
3) イエスの足に香油を塗るクリスチャン
この女性はイエスを価値あるものを捧げるに値する方であるとして、イエスに栄光を帰したのである。クリスチャンも、様々な形でいつもイエスに栄光を帰する者であるべきである。自分の功績をひけらかすのではなく、自分の栄誉を求めるのではなく。自分のそれまでの労力や努力を惜しんだりしないで。イエスは私達のために、命をも惜しまれなかった方なのだから。
↑
よろしかったらクリックにご協力ください。