この例話は、祈りというテーマで前の悪徳裁判官と寡婦の例話とつながっています。また、義、救いというテーマで、その前の人の子の日への備えにもつながっています。
十節
二人の人が祈るために神殿に行きました。当時は午前九時、午後三時、日没の時間と、日に三回祈る習慣が有りました。もしかしたら、そのいずれかの時間という想定かもしれません。場所は必ずしも神殿でなくても良いのでした。しかし、それ以外にも、自分の祈りたい時間に神殿に行くことが有りました。
この話を聞いた人は、この二人がパリサイ人と収税人だと聞いた時点で、前者が義人で後者が罪人ということであろうと想像したはずです。収税人が神殿に祈りに行くというのも、稀なことであったでしょう。
十一節、十二節
立ってと断ってありますが、立って祈るが当時の習慣でした。「心の中で」と訳されている語句は、自分自身に向かってとも訳せるもので、黙祷したという解釈することができます。それが当時の習慣だったからだとする注解も有ります。一方で、ルカは、彼が実際には神に祈るということではなく、自己満足のための独白をしていたに過ぎないということを表現している可能性を指摘する注解も有ります。そう思われても仕方が無い祈りの内容でした。彼は五回も「私」を繰り返す自己意識中心の祈りをし、神に感謝するとは言いましたが、神の下さる恵みや憐れみを感謝する言葉は一つも有りませんでした。
先ず、パリサイ人は、「ほかの人々」のようでないことを感謝しています。「ほかの人々」というのは、異邦人やパリサイ人の考える罪人達を表すのにも用いられた表現です。ゆする者、不正な者、姦淫する者でないといのがその具体的な内容として記されています。
次に彼は、具体的に、目の前に居る収税人と比較して、ことにこの収税人のようでないことを感謝すると祈りました。同じ神殿に祈りに来た同胞のことを、このように言うことが果たして霊的指導者の在るべき姿でしょうか。しかし、当時の人達にとっては、当たり前のことのように聞こえたようです。また、自分が義人であることを神に感謝することを、ラビ達は指導していたということです。
更に彼は自分のしていることを自慢するかのように述べます。週に二回断食するというのは、パリサイ人達は月曜日と木曜日に断食していたことを指します。その日には、水も飲まなかったそうです。しかし、日没になれば彼らは豪勢な食事をしましたし、それも、鱈腹食べて良いということでした。ですから、そんなに自慢できることでは無かったのです。また、律法の断食の規定は、年に一度贖いの日に断食するというものでした。彼らは必要以上に断食して、それを自分の義だと思っていたのでした。また、全ての十分の一を奉げていることを自慢しています。律法では実際は、穀物の十分の一という規定だったり、家畜の十分の一の規定だったりしましたが、彼らはそれ以上になんでも十分の一を奉げました。
彼らの考えは、律法以上に断食したり奉げたりすることで、自分達はもっと神に受け入れられる義人だと思っていたのです。しかし、実際に律法でもっと大事なのは、断食や十分の一ではなく、天の父が慈悲深いようにあなた方も慈悲深くあることなどでしたが、彼らそちらは無視していました。
このパリサイ人は、自分が「ゆする者、不正な者、姦淫する者」でないことを感謝していますが、実態は、むしろ「ゆする者、不正な者、姦淫する者」そのものでした。キリストが指摘している通り、彼らは寡婦を訪問して長い祈りをし、より多くの礼金をせしめていました。寡婦は貧しい者の代表でしたのに、そんなことをしたら「ゆする者」とかわりがありません。ですから、キリストもそれを「寡婦の家を食いつぶす」と表現しています。また、言い伝えや長老達の伝統を守るために、律法を曲げていたりする部分が有りました。それでは「不正な者」の謗りを免れないのではないでしょうか。そして、彼らは、気に入った女性が居れば、すぐに妻を離縁して、どんどん再婚しました。彼らは、手続きと伝統に従っているので姦淫ではないと思っていましたが、やっていることはまさに姦淫そのものでした。結局、神の目から見れば、彼らの心の態度も実際の行動も少しも義人と認められるものではありませんでした。
十三節
一方収税人の祈り方はどんなものだったのでしょうか。遠く離れて立ったと書いて有ります。これには幾つかの理由が考えられます。彼はこの後悔い改めの祈りをしています。悔い改めの告白をする時は、他の人から四キュビト(176センチぐらい)離れて立つという決まりが有りました。告白の内容が他人に聞かれないようにするためでした。もう一つの理由は、彼が自分の罪の自覚から謙って、前に進むのを憚ったというものです。彼らは異邦人と同じように見下げられていましたから、もしかしたら、彼の立った場所は異邦人の位置だったかもしれないという注解も有ります。
目を天に向けないということですが、天を仰ぐのも下を向くのもどちらも祈りの姿勢でした。下を向くということは、より謙遜な姿勢、もしくは打ちしおれた姿勢と考えることができそうです。
胸を打つというのは、悲しみの表現であり、彼の悔い改めの姿勢を表していると考えられます。
収税人の祈りは、「神様、こんな罪人の私を憐れんでください。」という短いものでした。しかし、この告白は大事なことを表しています。
一つ目は、「こんな罪人の私」という意識です。彼は誰とも比べたりしませんでした。あの人よりましであるなどという意識は有りませんでした。ただ、自分の内側だけを見、自分の罪を見つめていました。実際は責められるべき部分が多く有ったのに、それに気付かなかったパリサイ人と好対照になっています。
二つ目は、「私を憐れんでください」という部分です。ここで用いられている語の字義的意味は「私のなだめ、満足となってください。」というもので、祭壇での動物の血による和解の捧げ物を含意するということです。彼は行いによって自分を義とすることはできないと理解していたと考えられます。また、義は神によってのみ、神の方法によってのみ与えられることを理解していたと考えられます。
このことは、キリストが私達のために十字架で血を流して、贖罪となだめの捧げ物となり、信じる者達を救うというキリスト教の信仰理解につながります。キリストが自らこの例話を通して、そのことを示していたことがわかります。
十四節
キリストは、この収税人が義と認められたと言いました。ここで「義と認められる」と訳された語は、法律用語で、犯罪記録が無い、記録が削除されるというような意味が有ります。彼は罪人でしたが、謙遜に神の憐れみにすがることによって、その罪を帳消しにされたということです。
新改訳は義と認められたのは、「パリサイ人ではありません。」と表現されています。原文では「もう一人の人とは対照的に」というような意味の表現が使われています。どちらの表現にしても、この例話のパリサイ人は、義とされなかったということです。
これは、当時の人達からすると驚くべきメッセージでした。彼らの文化背景からすると、この例話のパリサイ人は律法も伝統も守っており、ラビが教える通りの祈りをしたのですから、当然義と認められるだろうと思ったはずです。それだけ、神の御心よりも律法や行いに人々の心は向いていたということでしょう。キリストは、そんな心を持っている周囲の人々と、自分の弟子達に対して、次のような締めくくりの言葉を与えました。
「だれでも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。」
自分を高くするというのは、自分に「栄誉を与える」という意味が有ります。自分を低くするというのは、自分を「いやしめる、捨て去る」という意味が有ります。例話のパリサイ人は、神に栄誉を帰することをしないで、自分を誇った結果、捨て去られ、義と認められませんでした。一方、収税人は、自分を捨て去って神に栄誉を与え、神に頼り、神にすがって義と認められました。そして、この法則は「誰でも(原文では全ての~する者)」当てはまるのだとキリストは言いました。九節に述べられているこの例話の目的を明確にするまとめになっています。
まとめ
キリストは一節~八節の例話で、キリストの再臨の時にこの地上に信仰が見出されるようにして欲しいという切なる願いを示しました。キリストは、また、このことを教えれば、必ずやそうなるということを知っていてその例話を語りました。
キリストの再臨の時にこの地上に信仰が見出されるための祈りは、
一、私達は無力であり、敵が居るのだから、
二、神の義と守りのために、
三、日夜祈り続けるというものでした。
祈り求めるものは、「神の義と守り」なのですが、これが今回の例話のテーマにつながっています。神の義と恵みと守りを得るための祈りの中核をなすのが、今回の例話で教えられていることです。
それは、
一、自分の力や業、自分の義、自分自身の在り方に信頼せず、
二、私達のための贖罪となだめの供え物となられたキリストと神の慈悲にのみ信頼し、
三、謙った真実な悔い改めの祈りによって、神に義と認められる、ということです。
これは、キリストによる救い、神の王国の王であるキリストに信頼して、神の国、信仰に生きるためには、どしても欠かせないことです。ですから、キリストの再臨の時に地上に信仰が見出されるための必要不可欠な祈りであり、個人レベルにおいても繰り返し祈られるべき内容です。
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
↑
よろしかったらクリックにご協力ください。
十節
二人の人が祈るために神殿に行きました。当時は午前九時、午後三時、日没の時間と、日に三回祈る習慣が有りました。もしかしたら、そのいずれかの時間という想定かもしれません。場所は必ずしも神殿でなくても良いのでした。しかし、それ以外にも、自分の祈りたい時間に神殿に行くことが有りました。
この話を聞いた人は、この二人がパリサイ人と収税人だと聞いた時点で、前者が義人で後者が罪人ということであろうと想像したはずです。収税人が神殿に祈りに行くというのも、稀なことであったでしょう。
十一節、十二節
立ってと断ってありますが、立って祈るが当時の習慣でした。「心の中で」と訳されている語句は、自分自身に向かってとも訳せるもので、黙祷したという解釈することができます。それが当時の習慣だったからだとする注解も有ります。一方で、ルカは、彼が実際には神に祈るということではなく、自己満足のための独白をしていたに過ぎないということを表現している可能性を指摘する注解も有ります。そう思われても仕方が無い祈りの内容でした。彼は五回も「私」を繰り返す自己意識中心の祈りをし、神に感謝するとは言いましたが、神の下さる恵みや憐れみを感謝する言葉は一つも有りませんでした。
先ず、パリサイ人は、「ほかの人々」のようでないことを感謝しています。「ほかの人々」というのは、異邦人やパリサイ人の考える罪人達を表すのにも用いられた表現です。ゆする者、不正な者、姦淫する者でないといのがその具体的な内容として記されています。
次に彼は、具体的に、目の前に居る収税人と比較して、ことにこの収税人のようでないことを感謝すると祈りました。同じ神殿に祈りに来た同胞のことを、このように言うことが果たして霊的指導者の在るべき姿でしょうか。しかし、当時の人達にとっては、当たり前のことのように聞こえたようです。また、自分が義人であることを神に感謝することを、ラビ達は指導していたということです。
更に彼は自分のしていることを自慢するかのように述べます。週に二回断食するというのは、パリサイ人達は月曜日と木曜日に断食していたことを指します。その日には、水も飲まなかったそうです。しかし、日没になれば彼らは豪勢な食事をしましたし、それも、鱈腹食べて良いということでした。ですから、そんなに自慢できることでは無かったのです。また、律法の断食の規定は、年に一度贖いの日に断食するというものでした。彼らは必要以上に断食して、それを自分の義だと思っていたのでした。また、全ての十分の一を奉げていることを自慢しています。律法では実際は、穀物の十分の一という規定だったり、家畜の十分の一の規定だったりしましたが、彼らはそれ以上になんでも十分の一を奉げました。
彼らの考えは、律法以上に断食したり奉げたりすることで、自分達はもっと神に受け入れられる義人だと思っていたのです。しかし、実際に律法でもっと大事なのは、断食や十分の一ではなく、天の父が慈悲深いようにあなた方も慈悲深くあることなどでしたが、彼らそちらは無視していました。
このパリサイ人は、自分が「ゆする者、不正な者、姦淫する者」でないことを感謝していますが、実態は、むしろ「ゆする者、不正な者、姦淫する者」そのものでした。キリストが指摘している通り、彼らは寡婦を訪問して長い祈りをし、より多くの礼金をせしめていました。寡婦は貧しい者の代表でしたのに、そんなことをしたら「ゆする者」とかわりがありません。ですから、キリストもそれを「寡婦の家を食いつぶす」と表現しています。また、言い伝えや長老達の伝統を守るために、律法を曲げていたりする部分が有りました。それでは「不正な者」の謗りを免れないのではないでしょうか。そして、彼らは、気に入った女性が居れば、すぐに妻を離縁して、どんどん再婚しました。彼らは、手続きと伝統に従っているので姦淫ではないと思っていましたが、やっていることはまさに姦淫そのものでした。結局、神の目から見れば、彼らの心の態度も実際の行動も少しも義人と認められるものではありませんでした。
十三節
一方収税人の祈り方はどんなものだったのでしょうか。遠く離れて立ったと書いて有ります。これには幾つかの理由が考えられます。彼はこの後悔い改めの祈りをしています。悔い改めの告白をする時は、他の人から四キュビト(176センチぐらい)離れて立つという決まりが有りました。告白の内容が他人に聞かれないようにするためでした。もう一つの理由は、彼が自分の罪の自覚から謙って、前に進むのを憚ったというものです。彼らは異邦人と同じように見下げられていましたから、もしかしたら、彼の立った場所は異邦人の位置だったかもしれないという注解も有ります。
目を天に向けないということですが、天を仰ぐのも下を向くのもどちらも祈りの姿勢でした。下を向くということは、より謙遜な姿勢、もしくは打ちしおれた姿勢と考えることができそうです。
胸を打つというのは、悲しみの表現であり、彼の悔い改めの姿勢を表していると考えられます。
収税人の祈りは、「神様、こんな罪人の私を憐れんでください。」という短いものでした。しかし、この告白は大事なことを表しています。
一つ目は、「こんな罪人の私」という意識です。彼は誰とも比べたりしませんでした。あの人よりましであるなどという意識は有りませんでした。ただ、自分の内側だけを見、自分の罪を見つめていました。実際は責められるべき部分が多く有ったのに、それに気付かなかったパリサイ人と好対照になっています。
二つ目は、「私を憐れんでください」という部分です。ここで用いられている語の字義的意味は「私のなだめ、満足となってください。」というもので、祭壇での動物の血による和解の捧げ物を含意するということです。彼は行いによって自分を義とすることはできないと理解していたと考えられます。また、義は神によってのみ、神の方法によってのみ与えられることを理解していたと考えられます。
このことは、キリストが私達のために十字架で血を流して、贖罪となだめの捧げ物となり、信じる者達を救うというキリスト教の信仰理解につながります。キリストが自らこの例話を通して、そのことを示していたことがわかります。
十四節
キリストは、この収税人が義と認められたと言いました。ここで「義と認められる」と訳された語は、法律用語で、犯罪記録が無い、記録が削除されるというような意味が有ります。彼は罪人でしたが、謙遜に神の憐れみにすがることによって、その罪を帳消しにされたということです。
新改訳は義と認められたのは、「パリサイ人ではありません。」と表現されています。原文では「もう一人の人とは対照的に」というような意味の表現が使われています。どちらの表現にしても、この例話のパリサイ人は、義とされなかったということです。
これは、当時の人達からすると驚くべきメッセージでした。彼らの文化背景からすると、この例話のパリサイ人は律法も伝統も守っており、ラビが教える通りの祈りをしたのですから、当然義と認められるだろうと思ったはずです。それだけ、神の御心よりも律法や行いに人々の心は向いていたということでしょう。キリストは、そんな心を持っている周囲の人々と、自分の弟子達に対して、次のような締めくくりの言葉を与えました。
「だれでも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。」
自分を高くするというのは、自分に「栄誉を与える」という意味が有ります。自分を低くするというのは、自分を「いやしめる、捨て去る」という意味が有ります。例話のパリサイ人は、神に栄誉を帰することをしないで、自分を誇った結果、捨て去られ、義と認められませんでした。一方、収税人は、自分を捨て去って神に栄誉を与え、神に頼り、神にすがって義と認められました。そして、この法則は「誰でも(原文では全ての~する者)」当てはまるのだとキリストは言いました。九節に述べられているこの例話の目的を明確にするまとめになっています。
まとめ
キリストは一節~八節の例話で、キリストの再臨の時にこの地上に信仰が見出されるようにして欲しいという切なる願いを示しました。キリストは、また、このことを教えれば、必ずやそうなるということを知っていてその例話を語りました。
キリストの再臨の時にこの地上に信仰が見出されるための祈りは、
一、私達は無力であり、敵が居るのだから、
二、神の義と守りのために、
三、日夜祈り続けるというものでした。
祈り求めるものは、「神の義と守り」なのですが、これが今回の例話のテーマにつながっています。神の義と恵みと守りを得るための祈りの中核をなすのが、今回の例話で教えられていることです。
それは、
一、自分の力や業、自分の義、自分自身の在り方に信頼せず、
二、私達のための贖罪となだめの供え物となられたキリストと神の慈悲にのみ信頼し、
三、謙った真実な悔い改めの祈りによって、神に義と認められる、ということです。
これは、キリストによる救い、神の王国の王であるキリストに信頼して、神の国、信仰に生きるためには、どしても欠かせないことです。ですから、キリストの再臨の時に地上に信仰が見出されるための必要不可欠な祈りであり、個人レベルにおいても繰り返し祈られるべき内容です。
↑
よろしかったらクリックにご協力ください。










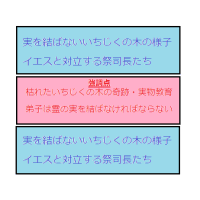





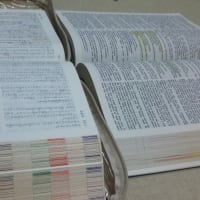
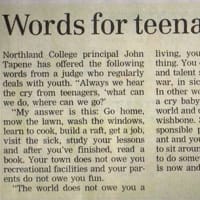

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます