ルカは受胎告知後のマリアの行動を記録しています。ルカがここで順序立てて説明する中で何を伝えたかったのでしょうか。いつもの様に各節の内容を確認しながら考えて行きたいと思います。奥義書(聖書)を開きながらお読みください。
三十九節
日本語訳では、「そのころ」などとするものが多いようですが、どちらかというと「それからすぐに」というニュアンスの方が良いように思われます。外国語の訳においてはそうなっているものも有るということです。身支度が出来次第直ぐという感覚であったろうとする解説も有ります。「立って」という言葉は旅に出るニュアンスが有るということです。
行き先については暗喩的に述べています。山里と訳したり山地と訳したりしていますが、実際にどの町を考えているかによって受け取り方は違うように思います。場所の考え方については諸説有るようです。一つ目は、「山地に有るユダの町」というような表現を慣用的なものとして捉え、広い範囲で考えてエルサレム周辺の町と考えます。二つ目は、その他の条件を加えてより絞りこんで、祭司の町であったヘブロンと考えます。三つ目は、一世紀の教父などの記述から、ヘブロンよりももっとエルサレムに近く、丘に囲まれたアイン・カリムという町だと考えます。いずれにせよ、若い女性の一人旅は山賊などに襲われることを考えると大変可能性は低く、旅の一団や商隊に同行させてもらうということであったろうと考えられます。
「急いだ」という表現が用いられていますが、原語から考えると、旅程を急いで進めたということではなく、マリアの心の持ち方であったのかもしれないとも思います。原語では速度を意味する名詞が用いられていますが、派生的には熱心、勤勉、努力などのような意味が有ります。
四十節
目的地はザカリアとエリサベツの家です。家に着くと挨拶はエリサベツにしたということが記されています。エリサベツに会いに行ったのですから当然ですが、他にも、男性と女性が挨拶をすることは稀であったとか、ザカリアは子供が生まれるまで口が利けなくなっていたなどの事情が重なっていたことも考えられます。
二人が親戚とは言え、面識が無い場合も有ったことでしょうが、マリアには一目でエリサベツがわかったでしょう。それなりに高齢でありながら妊娠六ヶ月の目立つお腹をしていたでしょうから。マリアは天使ガブリエルの言うことを信じて受け入れましたが、自分の未来に起こるであろう不利で難しい状況などを考えると、更に確信と力を得たいという思いが有ったことでしょう。そこでガブリエルが印として伝えたエリサベツが妊娠六ヶ月であるということを、自分の目でも確かめたかったと思われます。そして、この挨拶の瞬間に、その目的の大半は遂げられたと考えられるのではないかと思います。
四十一節
マリアの挨拶がどんなものであったかはわかりません。しかし、そこには普通ではない現象が伴いました。エリサベツの胎内にいたバプテスマのヨハネがおどったということと、エリサベツが聖霊に満たされたということでした。この二つは同時に起こり、また、胎内のヨハネとエリサベツの両方に聖霊は働かれたと考えることが多いようです。
胎児は周囲のできごとを理解しており、胎児も罪を犯すことが有るというのが当時の理解でした。それは別にしても、聖霊によってこの状況を理解し、喜びの表現としておどった、跳ねたと考えることは間違ってはいないと思われます。この部分をもって、ガブリエルが十五節で述べた「母の胎内にいる時から聖霊に満たされており」という預言の成就の一部であると考える注解が有ります。また、バプテスマのヨハネが後にヨハネ伝三章二十九節で「花嫁をもつ者は花婿である。花婿の友人は立って彼の声を聞き、その声を聞いて大いに喜ぶ。こうして、この喜びはわたしに満ち足りている。」と告白したのも、この原体験とも結びついていると考える注解も有ります。
とにかく、この胎児においてさえ、ガブリエルの伝えた二つの奇跡が真実であり、霊的な一致の証を持っていたということを理解することができると思います。
一方のエリサベツも聖霊に満たされて、この一連の出来事とガブリエルが伝えたこれから起こることが、神の業であり確かなことであるということを預言する言葉を神から授かりました。
ルカはこのような記述を通しても、書き記されている事柄やキリストについて教会内で語られていることが本当のことであるという論証を重ねようとしている姿勢がうかがえます。
四十二節
聖霊に満たされたので、エリサベツは自分自身では知らなかったのではないかと思われる預言の言葉を語ります。大声を上げたというのは、その霊の感動と喜びが大きかったからだと思われます。
最初に出てきた言葉は「女の中の祝福された人」ということでした。ガブリエルの「恵まれた女」という内容と合致していると思います。次いで、「胎の子供も祝福されている」ということでした。これも、ガブリエルを通して伝えられた内容に合致しています。こうして、聖霊の働きによるエリサベツの言葉を通して、先に示されたことが確認されることになりました。
四十三節
続くエリサベツの言葉は「なんということでしょうか。」という語調のものです。実際には、「どうしてこのような恵が与えられたのでしょうか。」という雰囲気に近く、謙遜の表現であるという説明をする注解も有ります。聖霊に啓示されたその内容を考えれば、そう言わないではいられなかったであろうと思います。その内容とは、「主の母が私のところに来るとは。」という驚くべきものでした。天使ガブリエルの言葉の通りであれば、生まれてくる子供は神なのですから、主と呼ばれるべき存在ですし、その子を宿している女性ですから、マリアは主の母と言える状況でした。人間の考えでは決して起こりえないことですが、それがエリサベツに実現した驚きが現れています。そして、そればかりではなく、この言葉によって、ガブリエルの語った中心的で重要な内容についても確認がされたことになるのです。
四十四節
原語では理由を導く接続詞と理解できる言葉が入っています。マリアの挨拶の声を聞いてエリサベツの胎の子供が喜び踊ったから知る事ができた、というような意味合いが含まれているのかもしれません。ユダヤ的背景の有る人にとっては、この部分も神の業が起きていたことを強調する意味を持ち得るようです。ユダヤ人の伝統によると、神が紅海の水を開いて、モーセに導かれてユダヤ人達がそこを渡り終えてエジプト軍に勝利した時、胎児達も歌を唱って神をほめたたえたということです。ですから、胎内にいたバプテスマのヨハネの喜び跳ねた様子だけは関係無いとは言えないのではないかという主張が背後に有るようです。
四十五節
聖霊に満たされたエリサベツの預言を締め括る言葉は、「主が語られたことは成就すると信じる者は幸いです。」というものでした。エリサベツはマリアの話しを聞く前にこのようなことまで聖霊によって知り得たわけです。
この部分は特別な奇跡的で不思議な事柄は含まれていません。そして、それはマリアの信仰についての神による評価の記述であるのみならず、私達信じる者たちに関わる普遍的な法則である部分が有ります。締め括りに語られた言葉でありますから、私達が心に留めるべき重要な要素であると考えることもできるでしょう。
まとめ
ルカがこの箇所から伝えたかったことを、次のように考えてみました。
1) 神の与えてくださった印や恵は、同じ霊と恵を分かち合った仲間を通して確認することができる。
2) 天使ガブリエルの言葉と聖霊によるエリサベツの預言は内容の一致が有り、教会で伝えられているキリストの福音は本当のことである。
3) マリアのように、神が語られたことを信じる者は幸いである。キリストの福音を信仰によって受け入れる者の幸いも同様である。
このように見ますと、繰り返し同じ要点を確認し続けているように思います。現代に生きる私達キリシタン忍者達も、これらのことを心に留めることに意味が有ると思います。特に、締め括りで語られ、受胎告知の時にも確認された、神の言葉を信じ、疑わず委ねる信仰を繰り返し修行しようではありませんか。
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
↑
よろしかったらクリックにご協力ください。
三十九節
日本語訳では、「そのころ」などとするものが多いようですが、どちらかというと「それからすぐに」というニュアンスの方が良いように思われます。外国語の訳においてはそうなっているものも有るということです。身支度が出来次第直ぐという感覚であったろうとする解説も有ります。「立って」という言葉は旅に出るニュアンスが有るということです。
行き先については暗喩的に述べています。山里と訳したり山地と訳したりしていますが、実際にどの町を考えているかによって受け取り方は違うように思います。場所の考え方については諸説有るようです。一つ目は、「山地に有るユダの町」というような表現を慣用的なものとして捉え、広い範囲で考えてエルサレム周辺の町と考えます。二つ目は、その他の条件を加えてより絞りこんで、祭司の町であったヘブロンと考えます。三つ目は、一世紀の教父などの記述から、ヘブロンよりももっとエルサレムに近く、丘に囲まれたアイン・カリムという町だと考えます。いずれにせよ、若い女性の一人旅は山賊などに襲われることを考えると大変可能性は低く、旅の一団や商隊に同行させてもらうということであったろうと考えられます。
「急いだ」という表現が用いられていますが、原語から考えると、旅程を急いで進めたということではなく、マリアの心の持ち方であったのかもしれないとも思います。原語では速度を意味する名詞が用いられていますが、派生的には熱心、勤勉、努力などのような意味が有ります。
四十節
目的地はザカリアとエリサベツの家です。家に着くと挨拶はエリサベツにしたということが記されています。エリサベツに会いに行ったのですから当然ですが、他にも、男性と女性が挨拶をすることは稀であったとか、ザカリアは子供が生まれるまで口が利けなくなっていたなどの事情が重なっていたことも考えられます。
二人が親戚とは言え、面識が無い場合も有ったことでしょうが、マリアには一目でエリサベツがわかったでしょう。それなりに高齢でありながら妊娠六ヶ月の目立つお腹をしていたでしょうから。マリアは天使ガブリエルの言うことを信じて受け入れましたが、自分の未来に起こるであろう不利で難しい状況などを考えると、更に確信と力を得たいという思いが有ったことでしょう。そこでガブリエルが印として伝えたエリサベツが妊娠六ヶ月であるということを、自分の目でも確かめたかったと思われます。そして、この挨拶の瞬間に、その目的の大半は遂げられたと考えられるのではないかと思います。
四十一節
マリアの挨拶がどんなものであったかはわかりません。しかし、そこには普通ではない現象が伴いました。エリサベツの胎内にいたバプテスマのヨハネがおどったということと、エリサベツが聖霊に満たされたということでした。この二つは同時に起こり、また、胎内のヨハネとエリサベツの両方に聖霊は働かれたと考えることが多いようです。
胎児は周囲のできごとを理解しており、胎児も罪を犯すことが有るというのが当時の理解でした。それは別にしても、聖霊によってこの状況を理解し、喜びの表現としておどった、跳ねたと考えることは間違ってはいないと思われます。この部分をもって、ガブリエルが十五節で述べた「母の胎内にいる時から聖霊に満たされており」という預言の成就の一部であると考える注解が有ります。また、バプテスマのヨハネが後にヨハネ伝三章二十九節で「花嫁をもつ者は花婿である。花婿の友人は立って彼の声を聞き、その声を聞いて大いに喜ぶ。こうして、この喜びはわたしに満ち足りている。」と告白したのも、この原体験とも結びついていると考える注解も有ります。
とにかく、この胎児においてさえ、ガブリエルの伝えた二つの奇跡が真実であり、霊的な一致の証を持っていたということを理解することができると思います。
一方のエリサベツも聖霊に満たされて、この一連の出来事とガブリエルが伝えたこれから起こることが、神の業であり確かなことであるということを預言する言葉を神から授かりました。
ルカはこのような記述を通しても、書き記されている事柄やキリストについて教会内で語られていることが本当のことであるという論証を重ねようとしている姿勢がうかがえます。
四十二節
聖霊に満たされたので、エリサベツは自分自身では知らなかったのではないかと思われる預言の言葉を語ります。大声を上げたというのは、その霊の感動と喜びが大きかったからだと思われます。
最初に出てきた言葉は「女の中の祝福された人」ということでした。ガブリエルの「恵まれた女」という内容と合致していると思います。次いで、「胎の子供も祝福されている」ということでした。これも、ガブリエルを通して伝えられた内容に合致しています。こうして、聖霊の働きによるエリサベツの言葉を通して、先に示されたことが確認されることになりました。
四十三節
続くエリサベツの言葉は「なんということでしょうか。」という語調のものです。実際には、「どうしてこのような恵が与えられたのでしょうか。」という雰囲気に近く、謙遜の表現であるという説明をする注解も有ります。聖霊に啓示されたその内容を考えれば、そう言わないではいられなかったであろうと思います。その内容とは、「主の母が私のところに来るとは。」という驚くべきものでした。天使ガブリエルの言葉の通りであれば、生まれてくる子供は神なのですから、主と呼ばれるべき存在ですし、その子を宿している女性ですから、マリアは主の母と言える状況でした。人間の考えでは決して起こりえないことですが、それがエリサベツに実現した驚きが現れています。そして、そればかりではなく、この言葉によって、ガブリエルの語った中心的で重要な内容についても確認がされたことになるのです。
四十四節
原語では理由を導く接続詞と理解できる言葉が入っています。マリアの挨拶の声を聞いてエリサベツの胎の子供が喜び踊ったから知る事ができた、というような意味合いが含まれているのかもしれません。ユダヤ的背景の有る人にとっては、この部分も神の業が起きていたことを強調する意味を持ち得るようです。ユダヤ人の伝統によると、神が紅海の水を開いて、モーセに導かれてユダヤ人達がそこを渡り終えてエジプト軍に勝利した時、胎児達も歌を唱って神をほめたたえたということです。ですから、胎内にいたバプテスマのヨハネの喜び跳ねた様子だけは関係無いとは言えないのではないかという主張が背後に有るようです。
四十五節
聖霊に満たされたエリサベツの預言を締め括る言葉は、「主が語られたことは成就すると信じる者は幸いです。」というものでした。エリサベツはマリアの話しを聞く前にこのようなことまで聖霊によって知り得たわけです。
この部分は特別な奇跡的で不思議な事柄は含まれていません。そして、それはマリアの信仰についての神による評価の記述であるのみならず、私達信じる者たちに関わる普遍的な法則である部分が有ります。締め括りに語られた言葉でありますから、私達が心に留めるべき重要な要素であると考えることもできるでしょう。
まとめ
ルカがこの箇所から伝えたかったことを、次のように考えてみました。
1) 神の与えてくださった印や恵は、同じ霊と恵を分かち合った仲間を通して確認することができる。
2) 天使ガブリエルの言葉と聖霊によるエリサベツの預言は内容の一致が有り、教会で伝えられているキリストの福音は本当のことである。
3) マリアのように、神が語られたことを信じる者は幸いである。キリストの福音を信仰によって受け入れる者の幸いも同様である。
このように見ますと、繰り返し同じ要点を確認し続けているように思います。現代に生きる私達キリシタン忍者達も、これらのことを心に留めることに意味が有ると思います。特に、締め括りで語られ、受胎告知の時にも確認された、神の言葉を信じ、疑わず委ねる信仰を繰り返し修行しようではありませんか。
↑
よろしかったらクリックにご協力ください。










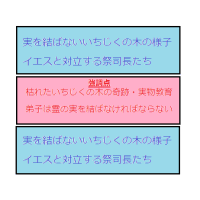





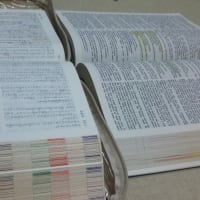
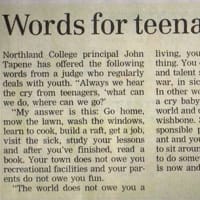

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます