万人祭司の教義は次のような聖書個所に根拠が有ります。(引用は新改訳)
しかし、あなたがたは、選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それは、あなたがたを、やみの中から、ご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方のすばらしいみわざを、あなたがたが宣べ伝えるためなのです。(ペテロ第一の手紙二章九節)
また、私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力とが、とこしえにあるように。(黙示録一章六節)
万人祭司であるから、牧師無しに教会もしくは信徒の共同体を運営するのが聖書的であるというような主張を目にすることが有ります。この理解には、祭司職と牧師職の理解の不足、もしくは混同が有ると思います。ですから、第一段階として、祭司の職務と牧師の職務が何であるかを再確認して見るのがよろしいかと思います。
祭司と牧師の区別
祭司の務めは旧約に規定等が見出されます。彼らの仕事の中心は、手っ取り早く言えば、民の礼拝・奉納を神に取り次ぐことでした。民が全焼のささげ物、穀物やぶどう酒のささげ物をする時も、民が直接ささげることがなく、祭司が受け取って実際の処理や祭壇への奉納などを行い、礼拝を神に取り次ぐ仕事をしたのです。
牧師の務めは、新約聖書では長老の務めと同じです。彼らの仕事の中心は、神の言葉を教え、それに従うように導く教師となることであり、間違った教えが教会に入り込むのを防ぐことでした。
そういうわけで、祭司の職務と牧師のは別のものですから、それをきちんと区別する必要が有ります。この二つが別の職務である以上、万人祭司であるという理由で、牧師が不要であるとか、牧師無しに信徒の共同体を運営するのが聖書的であるという主張は、非聖書的で、見当違いと言わざるを得ません。
誤解の要因
宗教改革の時にプロテスタントによって万人祭司が強く主張されたのは、当時一般の信徒には聖書を読むことや祈ることが許されておらず、教育を受けた司祭や神父がだけがそれを取り次げるという体制になっていたからです。宗教改革の先駆者達は、民衆に解かり易い説教をし、民衆に解かり易い言葉に聖書を翻訳したということで火炙りの刑に処されました。そのような過去、そのような体制に対するプロテスト、抗議の意味が、万人祭司の主張には有りました。(勿論聖書的にも万人祭司ではあります。)
司祭や神父無しに聖書を読めるという自由の問題が、いつの間にか教育を受けた牧師や教師は不要だという考え方と勘違いされたか、摩り替わった部分が有るように思われます。そして、それを当たり前のように用いる人が多くなったという面が有るように思います。
もう一つの誤解の要因は、用語に有ると思います。日本語で考えた場合は、カトリックの「司祭」という用語は「祭司」のそれと同じ漢字を用い、その順番が逆転しただけです。考え無しにさっと見れば、同じもののように思えるかもしれません。また、英語で考えますと、priestという言葉は、旧約の祭司に用いられるばかりでなく、いろいろな宗教の聖職者、神官、僧侶などを表すのにも用いられます。そこから、一般の言語感覚もしくは生活感覚として、祭司と牧師を同列に見る考え方が生まれた部分も有ると思います。しかし、我々キリスト教徒にとっては、そういう言語感覚や生活感覚が大事なのではなく、聖書がその二つをどう定義しているかということの方が遥かに大事なのです。
次回は、引用される二つの聖書個所が、どんな意味を持つのかを確認してみます。
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
↑
よろしかったらクリックにご協力ください。
しかし、あなたがたは、選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それは、あなたがたを、やみの中から、ご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方のすばらしいみわざを、あなたがたが宣べ伝えるためなのです。(ペテロ第一の手紙二章九節)
また、私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力とが、とこしえにあるように。(黙示録一章六節)
万人祭司であるから、牧師無しに教会もしくは信徒の共同体を運営するのが聖書的であるというような主張を目にすることが有ります。この理解には、祭司職と牧師職の理解の不足、もしくは混同が有ると思います。ですから、第一段階として、祭司の職務と牧師の職務が何であるかを再確認して見るのがよろしいかと思います。
祭司と牧師の区別
祭司の務めは旧約に規定等が見出されます。彼らの仕事の中心は、手っ取り早く言えば、民の礼拝・奉納を神に取り次ぐことでした。民が全焼のささげ物、穀物やぶどう酒のささげ物をする時も、民が直接ささげることがなく、祭司が受け取って実際の処理や祭壇への奉納などを行い、礼拝を神に取り次ぐ仕事をしたのです。
牧師の務めは、新約聖書では長老の務めと同じです。彼らの仕事の中心は、神の言葉を教え、それに従うように導く教師となることであり、間違った教えが教会に入り込むのを防ぐことでした。
そういうわけで、祭司の職務と牧師のは別のものですから、それをきちんと区別する必要が有ります。この二つが別の職務である以上、万人祭司であるという理由で、牧師が不要であるとか、牧師無しに信徒の共同体を運営するのが聖書的であるという主張は、非聖書的で、見当違いと言わざるを得ません。
誤解の要因
宗教改革の時にプロテスタントによって万人祭司が強く主張されたのは、当時一般の信徒には聖書を読むことや祈ることが許されておらず、教育を受けた司祭や神父がだけがそれを取り次げるという体制になっていたからです。宗教改革の先駆者達は、民衆に解かり易い説教をし、民衆に解かり易い言葉に聖書を翻訳したということで火炙りの刑に処されました。そのような過去、そのような体制に対するプロテスト、抗議の意味が、万人祭司の主張には有りました。(勿論聖書的にも万人祭司ではあります。)
司祭や神父無しに聖書を読めるという自由の問題が、いつの間にか教育を受けた牧師や教師は不要だという考え方と勘違いされたか、摩り替わった部分が有るように思われます。そして、それを当たり前のように用いる人が多くなったという面が有るように思います。
もう一つの誤解の要因は、用語に有ると思います。日本語で考えた場合は、カトリックの「司祭」という用語は「祭司」のそれと同じ漢字を用い、その順番が逆転しただけです。考え無しにさっと見れば、同じもののように思えるかもしれません。また、英語で考えますと、priestという言葉は、旧約の祭司に用いられるばかりでなく、いろいろな宗教の聖職者、神官、僧侶などを表すのにも用いられます。そこから、一般の言語感覚もしくは生活感覚として、祭司と牧師を同列に見る考え方が生まれた部分も有ると思います。しかし、我々キリスト教徒にとっては、そういう言語感覚や生活感覚が大事なのではなく、聖書がその二つをどう定義しているかということの方が遥かに大事なのです。
次回は、引用される二つの聖書個所が、どんな意味を持つのかを確認してみます。
↑
よろしかったらクリックにご協力ください。










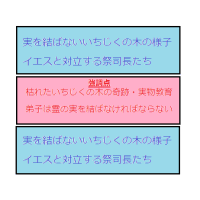





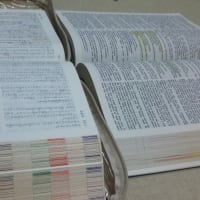
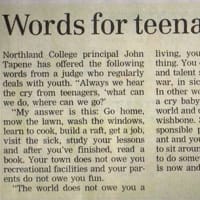








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます