先日、国際日本学部設立記念講演会を聞いてきて興味深い話があったのでメモを。
当日、講演されたのは漫画家のかわぐちかいじ氏と国際日本学部教授2人。そのなかで一番興味深い講演をされていたのが、国際日本学部の高山宏教授。昨年まで首都大学東京にいらっしゃったそうで、いろいろあって明治にきたそうです。専門は文化史学、視覚文化論。講演テーマは「メディアの近代史-イグナチウス・デ・ロヨラとマーシャル・マクルーハン」でした。
話はまず高山教授が上智大学の教授に知り合いがいて、その方の名刺になにかアルファベットの省略語があったことから始まります。高山教授は聞いたそうです。「これはなんの名前の略なんですか?」。するとその方は言いました。「先生、これは名前の略ではなくて、イエズス会の組織名の略なんでよ」。イエズス会…日本人からするとイエズス会がいまだにあるという風に感じる(高山教授曰く日本史だとザビエルが日本にきて終わってその後について教育していないから。正直、私もこのときまで上智がイエズス会だとしらなかった)。
次に高山教授はなんでこのイエズス会がこんな極東にある日本にまできたのかを考えてほしいと話を進めました。そもそもイエズス会の発足・発端はなんだったか。ヨーロッパにおける宗教戦争の結果…もといカソリックとプロテスタントのバランスが問題で、カソリックの信者獲得の巻き返しだった。イエズス会は今までの布教活動の形を一変させ、キリストの一生を劇・芝居仕立てにして行った。この結果、聖書という言語的な障害を乗り越え、世界中に広まった。そしてそれが日本にきたというわけだ、と教授は説明していました。
イエズス会はこの型破りな方法によって世界中にキリスト教を伝えた。教授は語りませんでしたが、私はこれがメディアというものなんだなと思いました。
それから教授は出雲の阿国について話をしました。なぜ田舎の巫女が社会問題になるほど人気を博したのか。それはかぶきものだったから。まーこれが今の歌舞伎になるのだから当たり前か。じゃなぜ、かぶいていたか、かぶいているからといって全国に伝播するわけではない、どうして全国へと伝わったか。ここから教授の推論が始まります。
出雲の阿国の絵には金の十字架を下げているものがある。彼女がキリシタンかどうかは別として、出雲の阿国がイエズス会の布教活動、劇を見ていたんではないだろうか。それをヒントに派手な装飾に身を包み、芝居を思いついたと考えられないだろうか。そしてそれがキリスト教のごとく広く伝わっていったんではないか、と仮説を立てていました。
確かにいわれてみるとなんとなくそんな気がしてきます。歌舞伎の発祥がイエズス会…うーん、興味深い。
まーそんなことを中心に語っていた高山教授ですが、余談として以下のことを話していました。
・スピーシーズとスペクタクルは語源が同じ
・シアターとセオリーは語源が同じ
・スペクタクルは日本語に訳せない
・ビジョンとピクチャーの意味の違いは日本語・日本人において説明は困難
・辞書はオックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリーを使え
まーとにかく不思議な先生でした。
当日、講演されたのは漫画家のかわぐちかいじ氏と国際日本学部教授2人。そのなかで一番興味深い講演をされていたのが、国際日本学部の高山宏教授。昨年まで首都大学東京にいらっしゃったそうで、いろいろあって明治にきたそうです。専門は文化史学、視覚文化論。講演テーマは「メディアの近代史-イグナチウス・デ・ロヨラとマーシャル・マクルーハン」でした。
話はまず高山教授が上智大学の教授に知り合いがいて、その方の名刺になにかアルファベットの省略語があったことから始まります。高山教授は聞いたそうです。「これはなんの名前の略なんですか?」。するとその方は言いました。「先生、これは名前の略ではなくて、イエズス会の組織名の略なんでよ」。イエズス会…日本人からするとイエズス会がいまだにあるという風に感じる(高山教授曰く日本史だとザビエルが日本にきて終わってその後について教育していないから。正直、私もこのときまで上智がイエズス会だとしらなかった)。
次に高山教授はなんでこのイエズス会がこんな極東にある日本にまできたのかを考えてほしいと話を進めました。そもそもイエズス会の発足・発端はなんだったか。ヨーロッパにおける宗教戦争の結果…もといカソリックとプロテスタントのバランスが問題で、カソリックの信者獲得の巻き返しだった。イエズス会は今までの布教活動の形を一変させ、キリストの一生を劇・芝居仕立てにして行った。この結果、聖書という言語的な障害を乗り越え、世界中に広まった。そしてそれが日本にきたというわけだ、と教授は説明していました。
イエズス会はこの型破りな方法によって世界中にキリスト教を伝えた。教授は語りませんでしたが、私はこれがメディアというものなんだなと思いました。
それから教授は出雲の阿国について話をしました。なぜ田舎の巫女が社会問題になるほど人気を博したのか。それはかぶきものだったから。まーこれが今の歌舞伎になるのだから当たり前か。じゃなぜ、かぶいていたか、かぶいているからといって全国に伝播するわけではない、どうして全国へと伝わったか。ここから教授の推論が始まります。
出雲の阿国の絵には金の十字架を下げているものがある。彼女がキリシタンかどうかは別として、出雲の阿国がイエズス会の布教活動、劇を見ていたんではないだろうか。それをヒントに派手な装飾に身を包み、芝居を思いついたと考えられないだろうか。そしてそれがキリスト教のごとく広く伝わっていったんではないか、と仮説を立てていました。
確かにいわれてみるとなんとなくそんな気がしてきます。歌舞伎の発祥がイエズス会…うーん、興味深い。
まーそんなことを中心に語っていた高山教授ですが、余談として以下のことを話していました。
・スピーシーズとスペクタクルは語源が同じ
・シアターとセオリーは語源が同じ
・スペクタクルは日本語に訳せない
・ビジョンとピクチャーの意味の違いは日本語・日本人において説明は困難
・辞書はオックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリーを使え
まーとにかく不思議な先生でした。















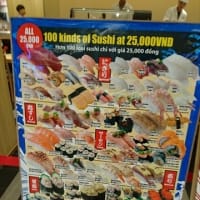




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます