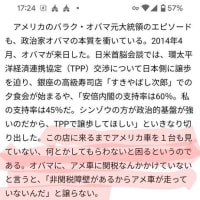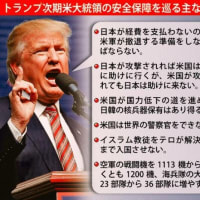赤峰和彦の 『 日本と国際社会の真相 』(20)
中国の対日外交戦略は上手く機能したのか

中国の対日外交戦略を概観する
中国の政治情勢は一枚岩ではありませんし、軍部の意識も多様なので、単純に中国の対日政策を分析するわけにはいきません。しかし、ここ一連の中国政府の発言を見ると、少なくとも従前の対日政策とは趣を変えてきたように感じられます。
2010年9月の尖閣諸島での中国漁船衝突事件以降、中国は尖閣諸島周辺水域での徘徊と日本の接続水域へ、日本の防空識別圏への侵入と徘徊を常態化させました。また、日本への制裁措置レアアース(希土類)【※1】の輸出を禁止しました。
【※1】2012年3月、日米欧は「中国が、レアアース(希土類)、タングステン、モリブデンに関して、不当な輸出制限をしている」として、WTOに提訴。これに対して、中国は環境や天然資源の保護などを理由に、輸出制限が正当なことを主張してきた。2014年8月、中国のWTO敗訴が最終決定した。
2012年9月の尖閣諸島国有化により、中国国内で反日デモが暴動化しました【※2】。このとき、共産党総書記に内定していた習近平国家副主席も尖閣国有化を激しく批判しました。この時点が、政府主導の反日工作の頂点だったのかもしれません。
【※2】これら一連の動きから、日本企業の間でチャイナリスクが高まり、インド・ASEANへのシフトが加速した。
2013年12月には安倍総理が靖国神社に参拝しました。即座に中国は反発し抗議声明を出しています。しかし、具体的な報復措置もなく、反日デモはすべて却下されたといわれています。この時点で、識者は「対日カードもそのほとんどを使ってしまい、有効な手段が取れずに困っている」と指摘しています。
「法の支配は,われわれすべてのために」
さて、2014年5月末の第13回アジア安全保障会議(シャングリラ・ダイアローグ)の際、安倍総理の演説は国際社会に大きな影響を与えました【※3】。積極的平和主義の推進を通してアジア地域の安定,平和,繁栄を高らかに謳ったからです。同時に、アジア諸国と摩擦を続ける中国を強く念頭においた演説でした。この時点で中国は少なからず国際社会の逆風を感じ取ったに相違ないでしょう。
【※3】安倍総理は演説の締めくくりで「アジアの平和と繁栄よ永遠なれ。日本は,法の支配のために。アジアは,法の支配のために。法の支配は,われわれすべてのために」と述べた。
「法の支配」という考え方が、いまでは国際社会の共通認識になっています。本年(2015)4月14日、15日にドイツ・リューベックで行われたG7外相会合【※4】においてもその趣旨のコミュニケ【※5】が発表されていますし、さらに、海洋安全保障に関する G7 外相宣言【※6】では中国に警告を発するまでになっています。
【※4】フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダとEU外務・安全保障上級代表が参加して開催。
【※5】http://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/pc/page22_001957.html 参照:「民主主義、法の支配、人権の尊重を含む我々にとって共通の価値観や原則に即して、自由、平和及び領土の一体性を守り・・・」
【※6】http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000076374.pdf 参照:「我々は,東シナ海及び南シナ海の状況を引き続き注視し、大規模埋め立てを含む、現状を変更し緊張を高めるあらゆる一方的行動を懸念している。我々は、威嚇、強制又は力による領土又は海洋に関する権利を主張するためのいかなる一方的試みにも強く反対する」
日本への歩み寄らざるをえない中国
本年(2015)4月22日、バンドン会議60周年行事の最中、日中首脳会談が行われました。2014年11月、中国で開催されたAPEC首脳会議のときの習近平主席の表情がうって変わって和らいでいるのが印象的でした。おそらくは、習主席にとっては、日本を無視してばかりはいられない事情がでてきたからでしょう。

その原因はいくつかありますが、前述のアジア安全保障会議の際の「法の支配」を求める安倍総理演説以降の国際社会の中国に対する厳しい視線を感じ取っていること。そして、中国が日米間の分断を狙って画策したこと【※7】がかえって日米同盟の絆を強くしているという事実に気づき、対応の変化を迫られてきたと思われるのです。
【※7】中国はプロパガンダ攻勢で、沖縄の米軍基地問題、集団的自衛権行使反対運動を起して世論喚起を試みたが、中国に追随する人以外にはその広がりを見せていない。
先日の、日米首脳会談でも「対中政策に関して、今後とも日米の様々なレベルで緊密に意見交換を行い、連携を維持していくこと」が確認されています。これら一連の国際社会の動きで、強気に見える中国も、実は、国際社会への対応に苦慮していると判断されるのです。
ADBとAIIB どちらが発展途上国のためになるのか
なかでも、いま一番中国が苦慮しているのがAIIB問題でしょう。AIIBを通じて経済分野で中国がアジア地域の主導権を握ろうとしていますが、思惑通りに動いていません。
5月2日から、67カ国・地域が加盟するADB(アジア開発銀行)の年次総会がアゼルバイジャン【※8】の首都バクーで開催されました。また、この間に、第18回ASEAN+3(日中韓)財務大臣・中央銀行総裁会議【※9】も開催されています。この一連の会合には麻生太郎財務相【※10】と黒田東彦日銀総裁が出席しています。
【※8】カスピ海の西岸に位置し、北はロシア、南はイランに挟まれる。バクー油田など豊富な天然資源がある。ムスリム(イスラム教徒)が95%を占める。米露とのバランスを考慮しつつ、トルコ、イランとも等距離善隣外交を継続中。
【※9】共同声明には世界経済の現状を「成長は緩やかなままで、一様でない道筋をたどっている」と指摘。成長力を高めるため、構造改革に取り組む考えも盛り込んだ。http://www.mof.go.jp/international_policy/convention/asean_plus_3/20150503.htm
【※10】麻生太郎財務相はADBセミナーで「アジアに望ましい成長をもたらす良質なインフラ投資を促進する」と述べ、JICAの活用に加え、国際協力銀行(JBIC)を財務面、人材面で強化。新幹線など日本の技術も活用して投資を拡大する意向を示した。
この一連の会合で日本主導のADBはその融資能力を現在の年間約130億ドルから、2017年に最大で1.5倍の約200億ドル(約2兆4千億円)に拡大すると発表し、資本力を高め、途上国のインフラ整備を加速させる考えを示したものです。
ADB側の新たな方針については専門家筋は、「インフラ整備の国際基準化を進めることと、その基準に満たない低レベルのインフラ投資を排除するものだ」と指摘をしています。要は、中国式援助が「私がやりましょう」型で、現地の企業を参画させず、その国の発展や雇用のために何の役にも立たないと言っているわけです。それよりも、日本式の「やり方を教えましょう」型の援助によって「技術移転を含めて現地の自立を促す方式」の方がその国のためになるという考え方が前面に出たものです。前者がAIIBで、後者がADBなのです。その意味で、今後のアジアのインフラ整備はAIIBの実態が明らかになるとともに、日本とADBへの期待がますます高まることになりそうです。
中国の軍拡は自らの滅びの道になる
中国という国は、弱腰で接近してくる国には高飛車でのぞみます。これは、伝統なのかもしれません。しかし、毅然たる態度でのぞんでくる国には冷静に対応してくるのです。先日の日米首脳会談に対する中国側の見解もおとなしくなっているのはそのいい例でしょう。
しかし、アジアに覇を唱えるには日本という国があり、世界に覇を唱えようとすればアメリカという巨大な壁が存在します。これには中国は「力」で対抗しようとしてきますから、中国の軟化を安易に考えてはなりません。中国は「力」を蓄えるべく、なお一層の軍備拡張に向かうものと見られます。
朝日新聞の2014年3月6日の社説でも「中国の国防費 危うい軍拡をやめよ」と述べているほどに、中国の軍事費の伸びは大きいものがあります。2015年予算案は、8869億元(約17兆円)と前年実績に比べて10.1%増、5年連続しての2桁増となっています。それだけの予算があるのなら、中国国民のための環境整備(PM2.5対策、水対策など)に使って、国民の生命と安全を守った方がいいと思うのですが、国際社会で主導権をとるために国民生活を犠牲にして軍拡をおこなっているのです。
しかし、軍事費拡大のツケは必ず来ます。なぜならば、かつてアメリカと覇権を争ったソ連は、結局崩壊してしまいましたが、原因はアメリカに対抗して軍備拡張に莫大な費用を投入した疲弊によるものです。現在でもアメリカの国防費は2016年度(15年10月~16年9月)の予算案では5000億ドル(約59兆円)に達する見込みで、中国がアメリカに対抗しようとすればするほど、中国の軍事費は跳ね上がり自滅するしかありません。

飽くなき軍拡は国を滅ぼす元となります。しかも、七大軍区といわれる軍部がそれぞれ勝手な動きを起せば、再び前世紀の「内乱の中国」に戻るだけになります。中国の指導部には静かに路線の変更をしていただきたいものです。
お問い合わせ先 akaminekaz@gmail.com
FBは https://www.facebook.com/akaminekaz です
中国の対日外交戦略は上手く機能したのか

中国の対日外交戦略を概観する
中国の政治情勢は一枚岩ではありませんし、軍部の意識も多様なので、単純に中国の対日政策を分析するわけにはいきません。しかし、ここ一連の中国政府の発言を見ると、少なくとも従前の対日政策とは趣を変えてきたように感じられます。
2010年9月の尖閣諸島での中国漁船衝突事件以降、中国は尖閣諸島周辺水域での徘徊と日本の接続水域へ、日本の防空識別圏への侵入と徘徊を常態化させました。また、日本への制裁措置レアアース(希土類)【※1】の輸出を禁止しました。
【※1】2012年3月、日米欧は「中国が、レアアース(希土類)、タングステン、モリブデンに関して、不当な輸出制限をしている」として、WTOに提訴。これに対して、中国は環境や天然資源の保護などを理由に、輸出制限が正当なことを主張してきた。2014年8月、中国のWTO敗訴が最終決定した。
2012年9月の尖閣諸島国有化により、中国国内で反日デモが暴動化しました【※2】。このとき、共産党総書記に内定していた習近平国家副主席も尖閣国有化を激しく批判しました。この時点が、政府主導の反日工作の頂点だったのかもしれません。
【※2】これら一連の動きから、日本企業の間でチャイナリスクが高まり、インド・ASEANへのシフトが加速した。
2013年12月には安倍総理が靖国神社に参拝しました。即座に中国は反発し抗議声明を出しています。しかし、具体的な報復措置もなく、反日デモはすべて却下されたといわれています。この時点で、識者は「対日カードもそのほとんどを使ってしまい、有効な手段が取れずに困っている」と指摘しています。
「法の支配は,われわれすべてのために」
さて、2014年5月末の第13回アジア安全保障会議(シャングリラ・ダイアローグ)の際、安倍総理の演説は国際社会に大きな影響を与えました【※3】。積極的平和主義の推進を通してアジア地域の安定,平和,繁栄を高らかに謳ったからです。同時に、アジア諸国と摩擦を続ける中国を強く念頭においた演説でした。この時点で中国は少なからず国際社会の逆風を感じ取ったに相違ないでしょう。
【※3】安倍総理は演説の締めくくりで「アジアの平和と繁栄よ永遠なれ。日本は,法の支配のために。アジアは,法の支配のために。法の支配は,われわれすべてのために」と述べた。
「法の支配」という考え方が、いまでは国際社会の共通認識になっています。本年(2015)4月14日、15日にドイツ・リューベックで行われたG7外相会合【※4】においてもその趣旨のコミュニケ【※5】が発表されていますし、さらに、海洋安全保障に関する G7 外相宣言【※6】では中国に警告を発するまでになっています。
【※4】フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダとEU外務・安全保障上級代表が参加して開催。
【※5】http://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/pc/page22_001957.html 参照:「民主主義、法の支配、人権の尊重を含む我々にとって共通の価値観や原則に即して、自由、平和及び領土の一体性を守り・・・」
【※6】http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000076374.pdf 参照:「我々は,東シナ海及び南シナ海の状況を引き続き注視し、大規模埋め立てを含む、現状を変更し緊張を高めるあらゆる一方的行動を懸念している。我々は、威嚇、強制又は力による領土又は海洋に関する権利を主張するためのいかなる一方的試みにも強く反対する」
日本への歩み寄らざるをえない中国
本年(2015)4月22日、バンドン会議60周年行事の最中、日中首脳会談が行われました。2014年11月、中国で開催されたAPEC首脳会議のときの習近平主席の表情がうって変わって和らいでいるのが印象的でした。おそらくは、習主席にとっては、日本を無視してばかりはいられない事情がでてきたからでしょう。

その原因はいくつかありますが、前述のアジア安全保障会議の際の「法の支配」を求める安倍総理演説以降の国際社会の中国に対する厳しい視線を感じ取っていること。そして、中国が日米間の分断を狙って画策したこと【※7】がかえって日米同盟の絆を強くしているという事実に気づき、対応の変化を迫られてきたと思われるのです。
【※7】中国はプロパガンダ攻勢で、沖縄の米軍基地問題、集団的自衛権行使反対運動を起して世論喚起を試みたが、中国に追随する人以外にはその広がりを見せていない。
先日の、日米首脳会談でも「対中政策に関して、今後とも日米の様々なレベルで緊密に意見交換を行い、連携を維持していくこと」が確認されています。これら一連の国際社会の動きで、強気に見える中国も、実は、国際社会への対応に苦慮していると判断されるのです。
ADBとAIIB どちらが発展途上国のためになるのか
なかでも、いま一番中国が苦慮しているのがAIIB問題でしょう。AIIBを通じて経済分野で中国がアジア地域の主導権を握ろうとしていますが、思惑通りに動いていません。
5月2日から、67カ国・地域が加盟するADB(アジア開発銀行)の年次総会がアゼルバイジャン【※8】の首都バクーで開催されました。また、この間に、第18回ASEAN+3(日中韓)財務大臣・中央銀行総裁会議【※9】も開催されています。この一連の会合には麻生太郎財務相【※10】と黒田東彦日銀総裁が出席しています。
【※8】カスピ海の西岸に位置し、北はロシア、南はイランに挟まれる。バクー油田など豊富な天然資源がある。ムスリム(イスラム教徒)が95%を占める。米露とのバランスを考慮しつつ、トルコ、イランとも等距離善隣外交を継続中。
【※9】共同声明には世界経済の現状を「成長は緩やかなままで、一様でない道筋をたどっている」と指摘。成長力を高めるため、構造改革に取り組む考えも盛り込んだ。http://www.mof.go.jp/international_policy/convention/asean_plus_3/20150503.htm
【※10】麻生太郎財務相はADBセミナーで「アジアに望ましい成長をもたらす良質なインフラ投資を促進する」と述べ、JICAの活用に加え、国際協力銀行(JBIC)を財務面、人材面で強化。新幹線など日本の技術も活用して投資を拡大する意向を示した。
この一連の会合で日本主導のADBはその融資能力を現在の年間約130億ドルから、2017年に最大で1.5倍の約200億ドル(約2兆4千億円)に拡大すると発表し、資本力を高め、途上国のインフラ整備を加速させる考えを示したものです。
ADB側の新たな方針については専門家筋は、「インフラ整備の国際基準化を進めることと、その基準に満たない低レベルのインフラ投資を排除するものだ」と指摘をしています。要は、中国式援助が「私がやりましょう」型で、現地の企業を参画させず、その国の発展や雇用のために何の役にも立たないと言っているわけです。それよりも、日本式の「やり方を教えましょう」型の援助によって「技術移転を含めて現地の自立を促す方式」の方がその国のためになるという考え方が前面に出たものです。前者がAIIBで、後者がADBなのです。その意味で、今後のアジアのインフラ整備はAIIBの実態が明らかになるとともに、日本とADBへの期待がますます高まることになりそうです。
中国の軍拡は自らの滅びの道になる
中国という国は、弱腰で接近してくる国には高飛車でのぞみます。これは、伝統なのかもしれません。しかし、毅然たる態度でのぞんでくる国には冷静に対応してくるのです。先日の日米首脳会談に対する中国側の見解もおとなしくなっているのはそのいい例でしょう。
しかし、アジアに覇を唱えるには日本という国があり、世界に覇を唱えようとすればアメリカという巨大な壁が存在します。これには中国は「力」で対抗しようとしてきますから、中国の軟化を安易に考えてはなりません。中国は「力」を蓄えるべく、なお一層の軍備拡張に向かうものと見られます。
朝日新聞の2014年3月6日の社説でも「中国の国防費 危うい軍拡をやめよ」と述べているほどに、中国の軍事費の伸びは大きいものがあります。2015年予算案は、8869億元(約17兆円)と前年実績に比べて10.1%増、5年連続しての2桁増となっています。それだけの予算があるのなら、中国国民のための環境整備(PM2.5対策、水対策など)に使って、国民の生命と安全を守った方がいいと思うのですが、国際社会で主導権をとるために国民生活を犠牲にして軍拡をおこなっているのです。
しかし、軍事費拡大のツケは必ず来ます。なぜならば、かつてアメリカと覇権を争ったソ連は、結局崩壊してしまいましたが、原因はアメリカに対抗して軍備拡張に莫大な費用を投入した疲弊によるものです。現在でもアメリカの国防費は2016年度(15年10月~16年9月)の予算案では5000億ドル(約59兆円)に達する見込みで、中国がアメリカに対抗しようとすればするほど、中国の軍事費は跳ね上がり自滅するしかありません。

飽くなき軍拡は国を滅ぼす元となります。しかも、七大軍区といわれる軍部がそれぞれ勝手な動きを起せば、再び前世紀の「内乱の中国」に戻るだけになります。中国の指導部には静かに路線の変更をしていただきたいものです。
お問い合わせ先 akaminekaz@gmail.com
FBは https://www.facebook.com/akaminekaz です