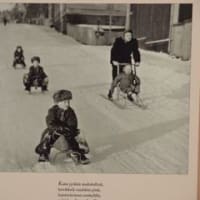5月29日(日)は新宿の麗澤大サテライトキャンパスで上の研究報告会があり、満員の盛況だった。
今回の震災について言語政策や言語サービスを検討してみようという趣旨で行われたものだが、急なことでもあり、聴覚障害者と外国人についての発表となった。
ぼくも4月中動き回っていた浦安調査の報告を行った。手話で博士をとった菊地君も発表してくれた。内容についてはまた改めてご報告したい。
雨が激しく、教室も満員で、湿度はいや増す中だったが、それぞれ発表は中身が濃く、各自20分の持ち時間というのが短すぎたかなと思う。枝野官房長官の横についた手話通訳が技術的な問題で聾者の人にはほとんどわからなかったといった話や、知的障害者が避難所ではいられないといった指摘も重いものだった。発表のタイトルは以下のとおり。
第1部:これまでの活動・研究を踏まえて
1.地方自治体の言語サービス
河原俊昭(京都光華女子大学)
2.聴覚障がい者への情報提供のあり方
中山慎一郎(日本手話研究所)
3.メディアと言語情報,知的障がい者と「やさしい日本語」
野沢和弘(毎日新聞論説委員)
第2部:今回の震災時,情報弱者に対する言語情報
1.地震被災時における外国人居住者の情報取得-浦安市の事例
村岡英裕(千葉大学)
2.震災以後,ろう者はどのようにして情報収集をしていたのか: その手段と伝播
菊地浩平(国立情報学研究所)
3.インターネットによる多言語情報提供
青山亨(東京外国語大学 多言語・多文化教育研究センター)
ぼくは決して言語政策の専門家ではないし、多文化共生とも距離をおいてきた人間だが、外国人との接触場面や言語管理をやってきたものとして、今やらないでいつやるのかと思って調査をしてきた。たいした調査ではないが、先鞭はつけられたかと思う。日本語教育の見知った顔も何人も来ていたので、その方々にバトンを渡せればいいのかなと思っている。
ただし、浦安でお世話になった方から、「これで終わりじゃないでしょうね」と釘を打たれたので、学会や研究者たちには先鞭をつけたと思ってほっとしているが、浦安の皆さんにはこれからまたお世話にならなければならないと思う。
今回の震災について言語政策や言語サービスを検討してみようという趣旨で行われたものだが、急なことでもあり、聴覚障害者と外国人についての発表となった。
ぼくも4月中動き回っていた浦安調査の報告を行った。手話で博士をとった菊地君も発表してくれた。内容についてはまた改めてご報告したい。
雨が激しく、教室も満員で、湿度はいや増す中だったが、それぞれ発表は中身が濃く、各自20分の持ち時間というのが短すぎたかなと思う。枝野官房長官の横についた手話通訳が技術的な問題で聾者の人にはほとんどわからなかったといった話や、知的障害者が避難所ではいられないといった指摘も重いものだった。発表のタイトルは以下のとおり。
第1部:これまでの活動・研究を踏まえて
1.地方自治体の言語サービス
河原俊昭(京都光華女子大学)
2.聴覚障がい者への情報提供のあり方
中山慎一郎(日本手話研究所)
3.メディアと言語情報,知的障がい者と「やさしい日本語」
野沢和弘(毎日新聞論説委員)
第2部:今回の震災時,情報弱者に対する言語情報
1.地震被災時における外国人居住者の情報取得-浦安市の事例
村岡英裕(千葉大学)
2.震災以後,ろう者はどのようにして情報収集をしていたのか: その手段と伝播
菊地浩平(国立情報学研究所)
3.インターネットによる多言語情報提供
青山亨(東京外国語大学 多言語・多文化教育研究センター)
ぼくは決して言語政策の専門家ではないし、多文化共生とも距離をおいてきた人間だが、外国人との接触場面や言語管理をやってきたものとして、今やらないでいつやるのかと思って調査をしてきた。たいした調査ではないが、先鞭はつけられたかと思う。日本語教育の見知った顔も何人も来ていたので、その方々にバトンを渡せればいいのかなと思っている。
ただし、浦安でお世話になった方から、「これで終わりじゃないでしょうね」と釘を打たれたので、学会や研究者たちには先鞭をつけたと思ってほっとしているが、浦安の皆さんにはこれからまたお世話にならなければならないと思う。