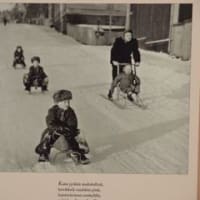昨日は、びっしょりと雨に濡れた早稲田の日本語教育研究センターで第12回の言語管理研究会となりました。そこそこの人数が集まってくれましたし、なつかしい顔もあって、中身の濃い定例研究会だったように思います。参加された方々、ありがとうございました。
昨年10月から始めた多言語話者研究の第4回目となり、今回は早稲田の宮崎さんの発案で、言語政策的な視点からEUの複言語主義を中心に、福島さん(早稲田の博士後期)、宮崎さん、そして私で、話題提供をしました。
政策としての複言語主義がEUでは開始されていて、いまや言語の大所帯となってしまったEUとしては、地域共同体の中で言語レパートリーの共有度を高めたいという思惑なのだと思います。政策としては特にめずらしいとは言えないもので、文化基盤、コミュニケーション基盤が類似している地域共同体であれば、当然、考えることだと思います。しかしやはりこれは上からのエリート主義の臭いが強いと言わざるを得ない。EUに参加してしまった国々に住む母語をもっぱら使って生活している半分の人々にとってはほとんど無関係な話でしょうし、複言語主義はそうした母語話者を地域共同体メンバーの頭の隅に追いやることでもある気がします。
ただ、興味深かったのは、個人としての言語使用者の意識について、複言語主義の主張は、言語管理研究会で展開されてきた流動的な規範の考えと、大きく異なるわけではないということでした。異なるのは、複言語主義がその理念を地域共同体に広げようとするのに対して、言語管理研究ではあくまでもそうした言語使用者が参加する場面のディスコースから言語問題を理解しようとしていることにあります。ディスコースの言語問題から政策へとビルドアップしていくことこそ大切なのだと考えるわけです。
私の発表は、多言語使用者の管理から(1)日本の相手言語接触場面の特徴を再検討し、(2)言語管理モデルの「逸脱」のオルタナティブを検討するというものでしたが、そちらにはついてはべつなところでお話することにします。
話は別になりますが、早稲田では言語管理理論が習得理論の調整として理解されていることが、福島さんや出席した早稲田の学生さんの発言からわかったのは面白い発見でした。ご存じのように、第2言語習得理論における調整は言語管理モデルの調整とは似て非なるものです。もちろん、言語管理は言語問題に対する体系的なアプローチなので、習得についても扱う範囲に入りますが、習得理論に矮小化されるようなものではありません。言語管理がなかなか理解されないことの実例、という印象でしたが、正しいかな。
雨がいよいよ激しくなる中、急いで地下鉄までの帰路を歩きました。雨量の多い雨は悪いものではないです。いろんなものを洗い流してくれますし、雨の中に閉じこめられる感覚もたまになら面白い。モンスーン地帯に特有の気候を味わうことが出来ます。そうそう、発表の準備に疲れて少しだけテレビで見たアジアカップ、ベトナムのスタジアムの湿気と暑さとも、昨日の雨はつながっていたのだと思います。
昨年10月から始めた多言語話者研究の第4回目となり、今回は早稲田の宮崎さんの発案で、言語政策的な視点からEUの複言語主義を中心に、福島さん(早稲田の博士後期)、宮崎さん、そして私で、話題提供をしました。
政策としての複言語主義がEUでは開始されていて、いまや言語の大所帯となってしまったEUとしては、地域共同体の中で言語レパートリーの共有度を高めたいという思惑なのだと思います。政策としては特にめずらしいとは言えないもので、文化基盤、コミュニケーション基盤が類似している地域共同体であれば、当然、考えることだと思います。しかしやはりこれは上からのエリート主義の臭いが強いと言わざるを得ない。EUに参加してしまった国々に住む母語をもっぱら使って生活している半分の人々にとってはほとんど無関係な話でしょうし、複言語主義はそうした母語話者を地域共同体メンバーの頭の隅に追いやることでもある気がします。
ただ、興味深かったのは、個人としての言語使用者の意識について、複言語主義の主張は、言語管理研究会で展開されてきた流動的な規範の考えと、大きく異なるわけではないということでした。異なるのは、複言語主義がその理念を地域共同体に広げようとするのに対して、言語管理研究ではあくまでもそうした言語使用者が参加する場面のディスコースから言語問題を理解しようとしていることにあります。ディスコースの言語問題から政策へとビルドアップしていくことこそ大切なのだと考えるわけです。
私の発表は、多言語使用者の管理から(1)日本の相手言語接触場面の特徴を再検討し、(2)言語管理モデルの「逸脱」のオルタナティブを検討するというものでしたが、そちらにはついてはべつなところでお話することにします。
話は別になりますが、早稲田では言語管理理論が習得理論の調整として理解されていることが、福島さんや出席した早稲田の学生さんの発言からわかったのは面白い発見でした。ご存じのように、第2言語習得理論における調整は言語管理モデルの調整とは似て非なるものです。もちろん、言語管理は言語問題に対する体系的なアプローチなので、習得についても扱う範囲に入りますが、習得理論に矮小化されるようなものではありません。言語管理がなかなか理解されないことの実例、という印象でしたが、正しいかな。
雨がいよいよ激しくなる中、急いで地下鉄までの帰路を歩きました。雨量の多い雨は悪いものではないです。いろんなものを洗い流してくれますし、雨の中に閉じこめられる感覚もたまになら面白い。モンスーン地帯に特有の気候を味わうことが出来ます。そうそう、発表の準備に疲れて少しだけテレビで見たアジアカップ、ベトナムのスタジアムの湿気と暑さとも、昨日の雨はつながっていたのだと思います。