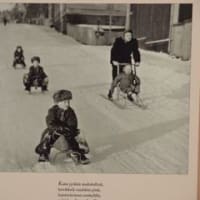Clancy et.al (1996)は英語、日本語、中国語の会話における聞き手の発話の頻度と位置について対照研究した重要な文献です。何が重要かというと、話順交替の位置をComplex Transition Relevance PlaceとしたFord and Thompson (1996)の枠組を使って、それぞれの言語使用者が、聞き手になったときにどのような場所でどのような発話をしているかを明らかにしようとしているためです。
話順交替の位置として、次の4つを想定します。
(a)上の統語的な完成位置、イントネーション的な完成位置の2つが重なった位置をCTRPの位置
(b)統語的完成の位置
(c)イントネーション的完成の位置
(d)どのような完成もない位置
そして、聞き手としての発話を、backchannel(非常に短い非語彙的音声、うん、えー、など)、反応的な表現(短い語彙的な発話)、そのほか3つの分類をしてこれらすべてをReactive Tokensと呼んでいます。このbackchannelと反応的な表現という分け方は日本語の実態をよく理解したすぐれた分類です。
このRTが現れたら話者交替が起きたと判断します。もちろん、それ以外に、何も発話をしない、フルの話順を取って話してとなる、という選択もあるわけです。
さて、3つの言語ではどのような違いが出てくるでしょうか?
(1)RTは日本語と英語で多く、中国語で少ない。
(2)日本語はどのような完成の位置もない、つまり、話し手が話をしている途中で、backchannelが非常に多い。
(3)英語では統語的完成、CTRPの位置で、つまりひとまとまりの話が終わったところで、反応的な表現を使って反応することが多い。
(4)中国語では、RTそのものが少ないが、現れるときはCTRPの位置であり、しかも語彙的に意味のある発話をするか、フルの話順を取って話し手になる。
これがClancyたちの分析です。この対照研究はとても説得的なものだと思います。ただし、ぼくの研究はここから始まります。つまり、こうした規範を持っている日本語と中国語の話者が接触場面に入ったとき、上の規範とは異なる現象が現れてくるということ、それを何とかして表現したいのですね。
話順交替の位置として、次の4つを想定します。
(a)上の統語的な完成位置、イントネーション的な完成位置の2つが重なった位置をCTRPの位置
(b)統語的完成の位置
(c)イントネーション的完成の位置
(d)どのような完成もない位置
そして、聞き手としての発話を、backchannel(非常に短い非語彙的音声、うん、えー、など)、反応的な表現(短い語彙的な発話)、そのほか3つの分類をしてこれらすべてをReactive Tokensと呼んでいます。このbackchannelと反応的な表現という分け方は日本語の実態をよく理解したすぐれた分類です。
このRTが現れたら話者交替が起きたと判断します。もちろん、それ以外に、何も発話をしない、フルの話順を取って話してとなる、という選択もあるわけです。
さて、3つの言語ではどのような違いが出てくるでしょうか?
(1)RTは日本語と英語で多く、中国語で少ない。
(2)日本語はどのような完成の位置もない、つまり、話し手が話をしている途中で、backchannelが非常に多い。
(3)英語では統語的完成、CTRPの位置で、つまりひとまとまりの話が終わったところで、反応的な表現を使って反応することが多い。
(4)中国語では、RTそのものが少ないが、現れるときはCTRPの位置であり、しかも語彙的に意味のある発話をするか、フルの話順を取って話し手になる。
これがClancyたちの分析です。この対照研究はとても説得的なものだと思います。ただし、ぼくの研究はここから始まります。つまり、こうした規範を持っている日本語と中国語の話者が接触場面に入ったとき、上の規範とは異なる現象が現れてくるということ、それを何とかして表現したいのですね。