『三峡好人』
<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=htsmknm-22&o=9&p=8&l=as1&asins=B0013BEC0O&fc1=000000&IS2=1<1=_blank&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>
FILMeX、始まりましたー。
これはもともと今年ヴェネツィアに出品された『東』というドキュメンタリー映画を奉節で撮影していた賈樟柯(ジャ・ジャンクー)が、その土地柄や独特の風土、そこに生きる人々の魅力に惹かれて急遽劇映画として制作することにしたという作品だという。結果的にはこちらもヴェネツィアでサプライズ上映され、見事金獅子賞に輝いた。
確かにその想いは非常によく伝わる映画に仕上がっている。英題『Still Life』とは静物画を意味するが、これは本当は『Landscape(風景画?j』でもよかったかもしれない。中国の古典絵画でよくみかける緑がかった薄墨色に霞んだ山水の合間に、見渡す限り廃屋と瓦礫に埋もれた街?ェ、みるみるうちに寂れ崩壊していく。真っ黒に陽に灼けた苦力(とゆーか仲仕と呼びたい)や解体作業員たち、建設成金、ヤクザ者たち。常?ノ流れ続け、とどまることのない時間そのものの情景だ。
そこへ人探しにやってくるふたりの男女。男(韓三明ハン・サンミン)は16年前に故郷へ帰ってしまった妻子を探しに、女(趙濤チャオ・タオ)は2年間帰ってこない夫に会いに来る。このふたりのエピソードがストーリーの軸にはなっているけど、たぶんメインじゃないんだよね。映画を構成するための骨組みとして機能はしてるけど、見せたかったのはあくまでいつか水底に沈んでいく運命の三峡という土地の魅力だったのだろう。
それはわかるよ。すごく。メチャクチャわかる。ぐりも廃墟とか解体現場とか好きだしさ。映画としてはよくできてると思うし。
けどねー。
なんかイマイチはいりこみにくかったんだよね。なんでかなー。
ディテールはすごく好きよ。ウン。べたっとした蒸し暑さや解体現場のすさまじい粉塵が画面からもわーっと押し寄せてくるような、すごくリアルな情景描写とか、容赦なくがんがん壊されてく街でしか撮れないものすごいシーンの連続とか、田舎のふつうの人たちのえもいわれぬいい表情とか、荒んでるよーでどっかにほろ苦いような甘さも残ってるよーな世間の雰囲気とか、非常に味はあるんだよね。
けど、やっぱちょっとそこに流され過ぎてる感も否めない。できることなら、もう一歩か二歩踏みこんで、もっと強引に賈樟柯なりの視点をはっきりと主張してくれた方が、観客にとっては親切だったかもしれない。
ただ歴史的ともいえる規模の三峡プロジェクトの一側面を活写した映画としては、やはり充分に意義ある作品だと思う。必見であることに違いはないです。ハイ。
上映後にティーチインがあり。登壇者は賈樟柯と趙濤。ぐり的におもしろかった回答のみメモっときます。ネタバレ系回答も今回避けます。あしからず。
(劇中に登場する歌を歌う男の子について)「奉節に着いたときにクルーに話しかけてきた客引きの男の子で、ある日現場にやってきて『俳優として映画に出たい』というので、『何ができるの?』と尋ねたら『歌が歌える』と答えたので歌ってもらった。彼には好きな子がいるのだが今は別の街に住んでいて離れている。『監督、どう演技すればいいの?』と訊かれて、その彼女のために歌ってほしいと頼んだ」
「撮影は3度に分けて行った。これは解体が進んで街の風景が変わることで時間の経過を表現したかったから。最後に撮影したのは趙濤が最後に登場するダムのシーン。あそこはダムの中心部でなかなか撮影許可が下りず、2月に申請して5月に許可が出た(趙濤の髪型が尋常じゃなしに変わっちゃってるのでそこはモロバレだったですよ監督・・・)」
「常連の王宏偉 (ワン・ホンウェイ)はいつもこそ泥やちんぴらといったまともじゃない役ばっかりだったので、今度はまともな役がやりた?「と自ら志願して東明(遺跡調査員)役を演じた。このために彼は10キロもダイエットした」
(趙濤:撮影期間にタイムラグがあったことについて)「奉節はいつも暑かったので、季節が変わることではとくに違和感などはなかった。それよりも、いつも撮影現場のすぐ傍で解体作業が行われているという環境に気を使った。撮影隊の安全がいつもとても心配だった」
とかなんとか。
歌を歌う男の子はホントーに見事な歌いっぷりで、また変声期にさしかかった微妙なハスキーボイスが色っぽくて、強烈に印象的でしたです。
劇中に『男たちの挽歌』の周潤發(チョウ・ユンファ)のマネをする青年が登場したことについて、奉節の刹那的な空気の“渡世”感を象徴したモチーフとしてあの映画を採用したと監督はいってたけど、どうもあの映画の發仔はヤクザとゆーより不良少年がそのまま大人になってしまった男というようなイメージがあったので、微妙に感覚にズレがあるよーな気はしたけど、そういうのはあくまで主観の問題だろう。あれはあれで笑えたし。
ぐりは賈樟柯と趙濤は初めてナマでみたけど、監督はほんとうに若くて小柄で控えめなごく真面目そうな青年、趙濤は思ってたよりもずっと綺麗で落ち着いて、こちらは大人の女性という雰囲気でした。
<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=htsmknm-22&o=9&p=8&l=as1&asins=B0013BEC0O&fc1=000000&IS2=1<1=_blank&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>
FILMeX、始まりましたー。
これはもともと今年ヴェネツィアに出品された『東』というドキュメンタリー映画を奉節で撮影していた賈樟柯(ジャ・ジャンクー)が、その土地柄や独特の風土、そこに生きる人々の魅力に惹かれて急遽劇映画として制作することにしたという作品だという。結果的にはこちらもヴェネツィアでサプライズ上映され、見事金獅子賞に輝いた。
確かにその想いは非常によく伝わる映画に仕上がっている。英題『Still Life』とは静物画を意味するが、これは本当は『Landscape(風景画?j』でもよかったかもしれない。中国の古典絵画でよくみかける緑がかった薄墨色に霞んだ山水の合間に、見渡す限り廃屋と瓦礫に埋もれた街?ェ、みるみるうちに寂れ崩壊していく。真っ黒に陽に灼けた苦力(とゆーか仲仕と呼びたい)や解体作業員たち、建設成金、ヤクザ者たち。常?ノ流れ続け、とどまることのない時間そのものの情景だ。
そこへ人探しにやってくるふたりの男女。男(韓三明ハン・サンミン)は16年前に故郷へ帰ってしまった妻子を探しに、女(趙濤チャオ・タオ)は2年間帰ってこない夫に会いに来る。このふたりのエピソードがストーリーの軸にはなっているけど、たぶんメインじゃないんだよね。映画を構成するための骨組みとして機能はしてるけど、見せたかったのはあくまでいつか水底に沈んでいく運命の三峡という土地の魅力だったのだろう。
それはわかるよ。すごく。メチャクチャわかる。ぐりも廃墟とか解体現場とか好きだしさ。映画としてはよくできてると思うし。
けどねー。
なんかイマイチはいりこみにくかったんだよね。なんでかなー。
ディテールはすごく好きよ。ウン。べたっとした蒸し暑さや解体現場のすさまじい粉塵が画面からもわーっと押し寄せてくるような、すごくリアルな情景描写とか、容赦なくがんがん壊されてく街でしか撮れないものすごいシーンの連続とか、田舎のふつうの人たちのえもいわれぬいい表情とか、荒んでるよーでどっかにほろ苦いような甘さも残ってるよーな世間の雰囲気とか、非常に味はあるんだよね。
けど、やっぱちょっとそこに流され過ぎてる感も否めない。できることなら、もう一歩か二歩踏みこんで、もっと強引に賈樟柯なりの視点をはっきりと主張してくれた方が、観客にとっては親切だったかもしれない。
ただ歴史的ともいえる規模の三峡プロジェクトの一側面を活写した映画としては、やはり充分に意義ある作品だと思う。必見であることに違いはないです。ハイ。
上映後にティーチインがあり。登壇者は賈樟柯と趙濤。ぐり的におもしろかった回答のみメモっときます。ネタバレ系回答も今回避けます。あしからず。
(劇中に登場する歌を歌う男の子について)「奉節に着いたときにクルーに話しかけてきた客引きの男の子で、ある日現場にやってきて『俳優として映画に出たい』というので、『何ができるの?』と尋ねたら『歌が歌える』と答えたので歌ってもらった。彼には好きな子がいるのだが今は別の街に住んでいて離れている。『監督、どう演技すればいいの?』と訊かれて、その彼女のために歌ってほしいと頼んだ」
「撮影は3度に分けて行った。これは解体が進んで街の風景が変わることで時間の経過を表現したかったから。最後に撮影したのは趙濤が最後に登場するダムのシーン。あそこはダムの中心部でなかなか撮影許可が下りず、2月に申請して5月に許可が出た(趙濤の髪型が尋常じゃなしに変わっちゃってるのでそこはモロバレだったですよ監督・・・)」
「常連の王宏偉 (ワン・ホンウェイ)はいつもこそ泥やちんぴらといったまともじゃない役ばっかりだったので、今度はまともな役がやりた?「と自ら志願して東明(遺跡調査員)役を演じた。このために彼は10キロもダイエットした」
(趙濤:撮影期間にタイムラグがあったことについて)「奉節はいつも暑かったので、季節が変わることではとくに違和感などはなかった。それよりも、いつも撮影現場のすぐ傍で解体作業が行われているという環境に気を使った。撮影隊の安全がいつもとても心配だった」
とかなんとか。
歌を歌う男の子はホントーに見事な歌いっぷりで、また変声期にさしかかった微妙なハスキーボイスが色っぽくて、強烈に印象的でしたです。
劇中に『男たちの挽歌』の周潤發(チョウ・ユンファ)のマネをする青年が登場したことについて、奉節の刹那的な空気の“渡世”感を象徴したモチーフとしてあの映画を採用したと監督はいってたけど、どうもあの映画の發仔はヤクザとゆーより不良少年がそのまま大人になってしまった男というようなイメージがあったので、微妙に感覚にズレがあるよーな気はしたけど、そういうのはあくまで主観の問題だろう。あれはあれで笑えたし。
ぐりは賈樟柯と趙濤は初めてナマでみたけど、監督はほんとうに若くて小柄で控えめなごく真面目そうな青年、趙濤は思ってたよりもずっと綺麗で落ち着いて、こちらは大人の女性という雰囲気でした。
















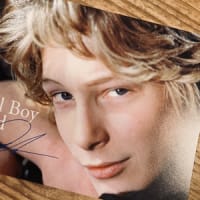



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます