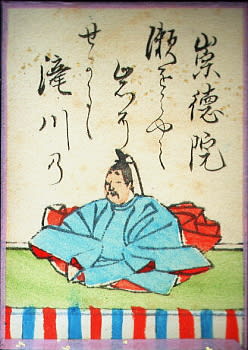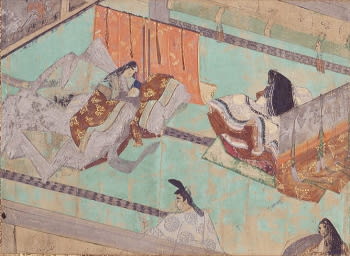「念力のゆるめば死ぬる大暑かな」 (村上鬼城)
出典は、大正6年版鬼城句集(※1)より。
句意は「言語道断の今年の暑さである。常人といえども、もし肝心の念力のゆるむ者がいたら、その者は直ちに病んで死んでしまうに創意ない。」(中村草田男)となるそうだ(.※2参照)
「肝心」は最も大事なことで、「きもごころ」とも読み、兼好法師の『徒然草』八九段(※3)に「肝心(きもごころ)も失(う)せて、防がんとするに力もなく」と出てくるが、この「肝心も失せて」は「びっくり仰天して」と訳されている。暑さに耐える気力のないものなら死んでしまうほどのびっくり仰天するほどのむちゃくちゃ暑い夏の日であることが伝わってくる。
村上鬼城(本名:村上荘太郎)の句は、人生の悲惨事をなめつくして初めて得られるところに特徴があり、これを「境涯の句」と呼んで評価したのは、大須賀乙字という俳句評論家であり、『鬼城句集』の序文で、「明治大正の御代に出でて、能く芭蕉に追随し一茶よりも句品の優った作者がある。実にわが村上鬼城である」と述べている。実際、鬼城の俳句には人生について深く考えさせられる作品が多くある。参考※1で読めるので読まれるとよい。
夏の季語の「大暑(たいしょ)」。この文字、見ているだけで汗が噴出してきそうな名前であり、1年のうちで、最も暑い頃という意味があるのだが、実際の暑さのピークはもう少し後になる。
元来、太陰太陽暦の6月中 (6月後半) のことで,太陽の黄経(黄道座標における経度)が 120°に達した日 (太陽暦の7月 23日か 24日) に始り,立秋 (8月7日か8日) の前日までの約 15日間であるが,現行暦ではこの期間の第1日目をさす。
今年・2015年7月23日はまさにこの日に当たる。神戸など例年このころに梅雨も明け、暑さもいよいよこれからが本番・・・・となるのだが、今年は台風9・10・11号の影響で中旬から連日猛暑が続き、蝉もにぎやかに鳴いていた。そして、台風(11号)一過梅雨も明けた。今年もこれから蒸し暑さで悩まされることになりそうだが、またまた、台風12号接近中とかで連日雨が降り続いている。まるで梅雨のように・・・。可笑しな天候だ。
世間一般で言われる夏の『土用丑の日』も今年は、明日の24日と8月5日と2回ある。今まで夏バテ防止で食べていたウナギも、最近は高くなって、今までの様には食べれない。他の方法で夏バテ対策しなくてはしようがないな~。
ところで、日本記念日協会(※4)に登録されている今日・7月23日の記念日に「カシスの日」がった。
由緒を見ると、「人々の健康に寄与するカシスへの関心を高めてもらおうと、日本カシス協会(※5)が制定。大暑の頃に収穫される果実のカシスは、その成分であるカシスポリフェノールに末梢血流の改善作用がある。日付は大暑となることが多い7月23日に」…とあった。
カシス?・・・・。私は、よく知らない名前なので,女房殿に聞くと名前だけは知っているが、どんなものかはよく知らないというので、Wikipediaや日本カシス協会(※5)その他にアクセスして、調べてみた。
まず、カシスって何か?
「カシス」(Cassis)、はフランス語であり、日本では、クロスグリ(黒酸塊、別名:クロフサスグ学名 Ribes nigrum)と呼ばれているもののことでスグリ科のフサスグリに属するするものであり、英語ではフサスグリ全般を「カラント(currant)」と呼ぶが、カシスは果実の色が濃い紫色でほとんど黒に見えることからブラックカラント (Blackcurrant)と呼ばれている(冒頭の画像がクロスグリ)。果実の色が赤色の系統をアカスグリ(赤すぐり、レッドカーラント)、白色の系統をシロスグリ(白すぐり)と呼ぶが、黒色のクロスグリ(カシス)とは別種だそうである。
カシスは古代からヨーロッパの山奥などに生育していたそうだが、食用に利用されたという古い記録はなく、カシスが食用できることを初めて紹介したのは、ルネッサンス時代の植物学者ガスパール・ポアンといわれているそうだ。さらに1712年にはフランスのバーイ・ド・モンタラン神父がカシスに関する本「'Les Proprietes Admirables du Cassis' (カシスの驚異)」を出版し、"カシスの絞り汁は万病に効く秘薬であり、若返り(不老不死)にも効果がある"と紹介しているという。
このような時期を経て少しずつカシスは一般的になり、18世紀半ば、フランス・ブルゴーニュ地方のワイン畑の一画などで、主に薬用として栽培されるようになり、フランスでは葉を乾燥させたものがリウマチによいとされ、今でも生薬を販売する店で売られているという。
カシスは、ヨーロッパやアジアが原産とされているが、現在カシスの世界最大の産地はポーランドで、毎年10万トンから14万5千トンの収穫高があり、これは世界全体の収穫高の約半分を占めるそうだ(Wikipedia)。また、日本国内では青森県が主な産地で、国産カシスの約90%、年間5.9トンのカシスが生産されているようだ。青森では「クロスグリ」ではなく「黒房スグリ」と呼ぶようだ。以下参照。
青森=りんごじゃない!?実はカシスの生産も盛んな青森県 | 青森でくらす
クロスグリの実はかすかな苦味をもち、ゼリー、ジャム、アイスクリーム、コーディアル、リキュールなどに利用される。また、イギリス、ヨーロッパ、イギリス連邦諸国では、クロスグリの風味を加えたり、干した果実を加えたクッキーなどの菓子が多数存在するそうだが、青森では、「カシスのちらしずし」や「カシスジャムとリンゴの春巻きパイ」などといった、ちょっとおもしろいカシス料理もあるようだ。上掲のページで、レシピを動画で見られるので、興味のある人は覗かれるとよい。
青森市ではカシスの特産品化が進められており、カシス協会主催の「カシスサミット」なるものも開催されているようだ。カシス協会は、カシスの生産者、カシスの研究を進める研究者を中心に構成され、カシスを積極的に食すことによる眼病予防の啓発、また、カシスの香りや美しい色で生活を豊かに彩ることの提案で、健康とキレイの両方を手に入れられるように、カシス産業、カシス文化の確立を目指してるそうで、「カシスの日」を7月23日(大暑)として設けたのは、2006年2月14日に青森で開催された「第一回カシスサミット」だったようだ(※5の活動報告参照)。
カシスはビタミンC、ビタミンEだけでなく、マグネシウム、鉄分などのミネラル類も豊富に含んでおり(栄養成分の説明については※6参照)、 さらにカシスが注目されているのは、これらに加えて抗酸化成分として知られる「ポリフェノール」を多く含み、なかでも、ポリフェノールの1種である、「アントシアニン」の含有量が多いことだという。
「ポリフェノール」の中でも有色野菜や果物の赤紫色を構成する色素成分で、カシスに含まれるアントシアニンは、抗酸化に優れている4種類(※7のアントシアニンって?参照)を含み、特に「D3R」と「C3R」はカシス特有の成分で、ブルーベリーやビルベリーなどには含まれていないものだという。そのため、同業界では、「カシスアントシアニン」と呼んで区別しているようだ。
カシスには目の疾患をはじめに筋肉疲労や動脈硬化など多くの症状に効果が期待できるが、それらの効果の根本を成すのが次の4つの効能だそうだ。
1.活性酸素を除去する効能
2.末梢血管(毛細血管)の血流を改善する効能
3.毛様体筋を弛緩する効能
4.ロドプシンの再合成促進作用
カシスには上記の4つの効能を軸に、視力回復効果や目の疲れ(眼精疲労、※8参照)の緩和効果など他にも目に対する効果を中心に14の効果が期待できるという(※7のカシスが持つ18の効能と効果を参照)。
近年、パソコンやゲーム機、携帯電話やスマホなどの普及に伴い、視力の低下した小中学生が増加しているが、小中学生のような子供だけでなく、若者でも、携帯電話やスマホを片時も.手放せずに使用している者が多い。
あのような小さな画面を長時間、高頻度で「近くを見る作業」を続けていると眼軸長(下図参照)が延長し(眼球がラグビーボールのような形になる)、それが慢性化することで軸性近視(近視は焦点が網膜の手前にある状態.。※8参照)となるが、ヒヨコをモデルに用いた実験でカシスアントシアニンの近視化抑制効果があると発表されているようだ(※5のここ参照)。
 カシスは世界中に広く分布しているが特にニュージーランド産のカシスが有名だそうだ。カシスは紫外線量に比例してアントシアニンが増えるので、日本の約7倍も紫外線量があるというニュージーランドはカシス栽培に非常に適した場所であり、アントシアニンをたっぷりと含んだ良質のカシスが育つのだそうだ(※9参照)。
カシスは世界中に広く分布しているが特にニュージーランド産のカシスが有名だそうだ。カシスは紫外線量に比例してアントシアニンが増えるので、日本の約7倍も紫外線量があるというニュージーランドはカシス栽培に非常に適した場所であり、アントシアニンをたっぷりと含んだ良質のカシスが育つのだそうだ(※9参照)。
歳ののせいもあるが、私もこのブログを書いたりするのに、結構長い時間パソコンの前にいることが多いせいで、ここのところものが少し見にくくなってきている。カシスには目に良いポリフェノール以外にもビタミンC他豊富な栄養素が多く含まれているようなので、適当なものが安く買えれば良いな~と思うのだが、参考※9の商品紹介のページなど見ていると、「本品は特定保健食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。」…とあった。ここのところはちょっと気になるところだな~。
参考:
※1:近代デジタルライブラリー - 鬼城句集
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/905666
※2:村上鬼城の俳句 | 季語と俳句鑑賞ノート
http://anketopia.com/haiku_kigo/node/638
※3:徒然草(吉田兼好著・吾妻利秋訳)
http://www.tsurezuregusa.com/index.php?title=Category:%E5%BE%92%E7%84%B6%E8%8D%89
※4:日本記念日協会
http://www.kinenbi.gr.jp/
※5:日本カシス協会
http://j-cassis.jp/index.html
※6:栄養成分百科 |江崎グリコ
http://www.glico.co.jp/navi/dic/index.html
※7:カシスの効果・効能まとめ
http://cassis.wgjp.net/
※8:目と健康シリーズ-三和化学研究所
http://www.skk-health.net/
※9:カシスの秘密―明治
http://www.meiji.co.jp/health/cassis-i/secret/knowledge.html
クロスグリー.Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%82%B0%E3%83%AA
出典は、大正6年版鬼城句集(※1)より。
句意は「言語道断の今年の暑さである。常人といえども、もし肝心の念力のゆるむ者がいたら、その者は直ちに病んで死んでしまうに創意ない。」(中村草田男)となるそうだ(.※2参照)
「肝心」は最も大事なことで、「きもごころ」とも読み、兼好法師の『徒然草』八九段(※3)に「肝心(きもごころ)も失(う)せて、防がんとするに力もなく」と出てくるが、この「肝心も失せて」は「びっくり仰天して」と訳されている。暑さに耐える気力のないものなら死んでしまうほどのびっくり仰天するほどのむちゃくちゃ暑い夏の日であることが伝わってくる。
村上鬼城(本名:村上荘太郎)の句は、人生の悲惨事をなめつくして初めて得られるところに特徴があり、これを「境涯の句」と呼んで評価したのは、大須賀乙字という俳句評論家であり、『鬼城句集』の序文で、「明治大正の御代に出でて、能く芭蕉に追随し一茶よりも句品の優った作者がある。実にわが村上鬼城である」と述べている。実際、鬼城の俳句には人生について深く考えさせられる作品が多くある。参考※1で読めるので読まれるとよい。
夏の季語の「大暑(たいしょ)」。この文字、見ているだけで汗が噴出してきそうな名前であり、1年のうちで、最も暑い頃という意味があるのだが、実際の暑さのピークはもう少し後になる。
元来、太陰太陽暦の6月中 (6月後半) のことで,太陽の黄経(黄道座標における経度)が 120°に達した日 (太陽暦の7月 23日か 24日) に始り,立秋 (8月7日か8日) の前日までの約 15日間であるが,現行暦ではこの期間の第1日目をさす。
今年・2015年7月23日はまさにこの日に当たる。神戸など例年このころに梅雨も明け、暑さもいよいよこれからが本番・・・・となるのだが、今年は台風9・10・11号の影響で中旬から連日猛暑が続き、蝉もにぎやかに鳴いていた。そして、台風(11号)一過梅雨も明けた。今年もこれから蒸し暑さで悩まされることになりそうだが、またまた、台風12号接近中とかで連日雨が降り続いている。まるで梅雨のように・・・。可笑しな天候だ。
世間一般で言われる夏の『土用丑の日』も今年は、明日の24日と8月5日と2回ある。今まで夏バテ防止で食べていたウナギも、最近は高くなって、今までの様には食べれない。他の方法で夏バテ対策しなくてはしようがないな~。
ところで、日本記念日協会(※4)に登録されている今日・7月23日の記念日に「カシスの日」がった。
由緒を見ると、「人々の健康に寄与するカシスへの関心を高めてもらおうと、日本カシス協会(※5)が制定。大暑の頃に収穫される果実のカシスは、その成分であるカシスポリフェノールに末梢血流の改善作用がある。日付は大暑となることが多い7月23日に」…とあった。
カシス?・・・・。私は、よく知らない名前なので,女房殿に聞くと名前だけは知っているが、どんなものかはよく知らないというので、Wikipediaや日本カシス協会(※5)その他にアクセスして、調べてみた。
まず、カシスって何か?
「カシス」(Cassis)、はフランス語であり、日本では、クロスグリ(黒酸塊、別名:クロフサスグ学名 Ribes nigrum)と呼ばれているもののことでスグリ科のフサスグリに属するするものであり、英語ではフサスグリ全般を「カラント(currant)」と呼ぶが、カシスは果実の色が濃い紫色でほとんど黒に見えることからブラックカラント (Blackcurrant)と呼ばれている(冒頭の画像がクロスグリ)。果実の色が赤色の系統をアカスグリ(赤すぐり、レッドカーラント)、白色の系統をシロスグリ(白すぐり)と呼ぶが、黒色のクロスグリ(カシス)とは別種だそうである。
カシスは古代からヨーロッパの山奥などに生育していたそうだが、食用に利用されたという古い記録はなく、カシスが食用できることを初めて紹介したのは、ルネッサンス時代の植物学者ガスパール・ポアンといわれているそうだ。さらに1712年にはフランスのバーイ・ド・モンタラン神父がカシスに関する本「'Les Proprietes Admirables du Cassis' (カシスの驚異)」を出版し、"カシスの絞り汁は万病に効く秘薬であり、若返り(不老不死)にも効果がある"と紹介しているという。
このような時期を経て少しずつカシスは一般的になり、18世紀半ば、フランス・ブルゴーニュ地方のワイン畑の一画などで、主に薬用として栽培されるようになり、フランスでは葉を乾燥させたものがリウマチによいとされ、今でも生薬を販売する店で売られているという。
カシスは、ヨーロッパやアジアが原産とされているが、現在カシスの世界最大の産地はポーランドで、毎年10万トンから14万5千トンの収穫高があり、これは世界全体の収穫高の約半分を占めるそうだ(Wikipedia)。また、日本国内では青森県が主な産地で、国産カシスの約90%、年間5.9トンのカシスが生産されているようだ。青森では「クロスグリ」ではなく「黒房スグリ」と呼ぶようだ。以下参照。
青森=りんごじゃない!?実はカシスの生産も盛んな青森県 | 青森でくらす
クロスグリの実はかすかな苦味をもち、ゼリー、ジャム、アイスクリーム、コーディアル、リキュールなどに利用される。また、イギリス、ヨーロッパ、イギリス連邦諸国では、クロスグリの風味を加えたり、干した果実を加えたクッキーなどの菓子が多数存在するそうだが、青森では、「カシスのちらしずし」や「カシスジャムとリンゴの春巻きパイ」などといった、ちょっとおもしろいカシス料理もあるようだ。上掲のページで、レシピを動画で見られるので、興味のある人は覗かれるとよい。
青森市ではカシスの特産品化が進められており、カシス協会主催の「カシスサミット」なるものも開催されているようだ。カシス協会は、カシスの生産者、カシスの研究を進める研究者を中心に構成され、カシスを積極的に食すことによる眼病予防の啓発、また、カシスの香りや美しい色で生活を豊かに彩ることの提案で、健康とキレイの両方を手に入れられるように、カシス産業、カシス文化の確立を目指してるそうで、「カシスの日」を7月23日(大暑)として設けたのは、2006年2月14日に青森で開催された「第一回カシスサミット」だったようだ(※5の活動報告参照)。
カシスはビタミンC、ビタミンEだけでなく、マグネシウム、鉄分などのミネラル類も豊富に含んでおり(栄養成分の説明については※6参照)、 さらにカシスが注目されているのは、これらに加えて抗酸化成分として知られる「ポリフェノール」を多く含み、なかでも、ポリフェノールの1種である、「アントシアニン」の含有量が多いことだという。
「ポリフェノール」の中でも有色野菜や果物の赤紫色を構成する色素成分で、カシスに含まれるアントシアニンは、抗酸化に優れている4種類(※7のアントシアニンって?参照)を含み、特に「D3R」と「C3R」はカシス特有の成分で、ブルーベリーやビルベリーなどには含まれていないものだという。そのため、同業界では、「カシスアントシアニン」と呼んで区別しているようだ。
カシスには目の疾患をはじめに筋肉疲労や動脈硬化など多くの症状に効果が期待できるが、それらの効果の根本を成すのが次の4つの効能だそうだ。
1.活性酸素を除去する効能
2.末梢血管(毛細血管)の血流を改善する効能
3.毛様体筋を弛緩する効能
4.ロドプシンの再合成促進作用
カシスには上記の4つの効能を軸に、視力回復効果や目の疲れ(眼精疲労、※8参照)の緩和効果など他にも目に対する効果を中心に14の効果が期待できるという(※7のカシスが持つ18の効能と効果を参照)。
近年、パソコンやゲーム機、携帯電話やスマホなどの普及に伴い、視力の低下した小中学生が増加しているが、小中学生のような子供だけでなく、若者でも、携帯電話やスマホを片時も.手放せずに使用している者が多い。
あのような小さな画面を長時間、高頻度で「近くを見る作業」を続けていると眼軸長(下図参照)が延長し(眼球がラグビーボールのような形になる)、それが慢性化することで軸性近視(近視は焦点が網膜の手前にある状態.。※8参照)となるが、ヒヨコをモデルに用いた実験でカシスアントシアニンの近視化抑制効果があると発表されているようだ(※5のここ参照)。

歳ののせいもあるが、私もこのブログを書いたりするのに、結構長い時間パソコンの前にいることが多いせいで、ここのところものが少し見にくくなってきている。カシスには目に良いポリフェノール以外にもビタミンC他豊富な栄養素が多く含まれているようなので、適当なものが安く買えれば良いな~と思うのだが、参考※9の商品紹介のページなど見ていると、「本品は特定保健食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。」…とあった。ここのところはちょっと気になるところだな~。
参考:
※1:近代デジタルライブラリー - 鬼城句集
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/905666
※2:村上鬼城の俳句 | 季語と俳句鑑賞ノート
http://anketopia.com/haiku_kigo/node/638
※3:徒然草(吉田兼好著・吾妻利秋訳)
http://www.tsurezuregusa.com/index.php?title=Category:%E5%BE%92%E7%84%B6%E8%8D%89
※4:日本記念日協会
http://www.kinenbi.gr.jp/
※5:日本カシス協会
http://j-cassis.jp/index.html
※6:栄養成分百科 |江崎グリコ
http://www.glico.co.jp/navi/dic/index.html
※7:カシスの効果・効能まとめ
http://cassis.wgjp.net/
※8:目と健康シリーズ-三和化学研究所
http://www.skk-health.net/
※9:カシスの秘密―明治
http://www.meiji.co.jp/health/cassis-i/secret/knowledge.html
クロスグリー.Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%82%B0%E3%83%AA