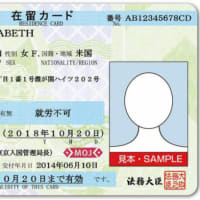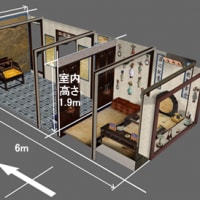5.誤読かどうか判断できないルビ
外国語音で書かれたルビの、
もう一つの弊害として、
正誤の判定ができない、
正解か間違っているか、読んでいる者に判らない、
という問題があります。
例えば、「山田(やすだ)」と書かれていたら
これを読んだ人は、
間違いか?何か理由があるのだろうか?
と思うはずです。
人によっては、見ていて気持ちが悪いと感じるかもしれません。
漢字は、日本人の持つ共通認識の上に成り立って、
使用されているからです。
記憶があやふやな場合は、
『辞書』で検索する事もできます。
しかし、外国語のルビの場合は、
普通の日本人には、
正解なのかデタラメなのか分かりません。
普通、私達は、新聞やテレビ・映画の字幕の漢字ルビを、
信用して見ています。
特に大手新聞やNHKは日本語の基準でもあり、
変な記述があるとは思いません。
それは、外国語でも同じで、
自身が知らない言葉でも、
新聞を信用して「へー、そうなんだ」と考えます。
しかし、それ程信用できる物でしょうか?
例えば、
御存知の方も多いと思いますが、
最近の事件で、
韓国籍の趙永珠(ちょうえいじゅ)という女性が、
不幸にも事件に巻き込まれたという報道がありました。
この女性の名前ですが、
『読売新聞・神奈川 2011年7月6日』版では、
「韓国籍で同市南区、
飲食店経営趙永珠(チョヨンジュ)さん(当時41歳)の
足首が見つかった事件で…」
『毎日新聞 2011年7月5日 東京朝刊』では、
「山口容疑者は知人からの借金返済のため、
妻の飲食店経営、趙永珠(チョウヨンジュ)さん(当時41歳)から
たびたび金を借りていた。」
『読売新聞』と『毎日新聞』は大手新聞社ですが、
「趙」は「チョウ」でしょうか「チョ」でしょうか、
どちらが正しいのでしょう?
日本語音なら「ちょう」です。
例えば、
中国人の「呉中華」(架空の人名です)の場合、
日本語音は(ごちゅうか)一つですが、
中国語音の場合は(Wu zhong hua)の音を、
耳で聞いて表記することになります。
現在、新聞や映画の字幕で採用されている、
この漢字の発音には、それぞれ、
呉の場合(ウ)(ウー)、
中には(チョン)(ジョン)(チュン)、
華には(フア)(ファー)(ホア)などがあります。
すると、一人三文字の名前に対して
最多で十八種の発音が存在する事になり、
例えば、
「ウチョンフア」と「ウージョンファー」はまるで別人で、
これでは、
名前の役割を果たしません。
そもそも、漢字文化圏では、
外国人の人名も地名も、
日本では漢字は日本語音で読む事になっていて、
外国語音で読む必要はありません。
「呉中華」は(ごちゅうか)と読むべきですし、
誤りも少ないはずです。
例えば、
中国語の教科書に、
カタカナで中国語音でルビのふってある出版物があります。
これは、
勉強をする人への便宜としての記述で、
誤った音を書けば、
著者である専門家の見識を疑われますので、
正確な音に近い音が書かれていると思われます。
では、普通の小説はどうでしょう?
最近NHKでもドラマ化された
中国が舞台の小説があります。
この原作本は、
日本の漢字に大量に日本語音以外のルビがふってありますが、
それについて、少し調べてみました。
どれ程正確に書かれた物か、
興味があったからです。
以下は、この本の文章中に示された単語で、
特に目についた物を取り上げ、
説明した物です。
例えば、最初の方に出てくる、
「大哥(ダアコオ)」「二哥(アルコオ)」「阿哥(アコ)」
について、
「哥」は「兄貴」「兄さん」という意味で、
「大哥」とは「長兄」、「二哥」は「次兄」の意。
「阿哥」は、清朝における王子の幼名で、これは特別な単語です。
「哥」という漢字に対して
一人の人が付けたにも関わらず
(コオ)と(コ)という音がある事になります。
どちらが正しいのでしょう?
どちらも誤りです。
そもそも中国語では、「哥」は(ge)の音で、
(e)の音は日本語の中にはありませんが(ge)は、
(グ)や(ガ)の音に近くなります。
(コオ)でも(コ)でもありません。
(ダアコオ)(アルコオ)(アコ)
と発音してみても、
日本人も中国人も、漢字が思い浮かびません。
無駄だと思います。
『漢和辞典』等で検索すれば、
「哥」は(か)、「阿哥」は(あか)です。
「哥」を(か)と日本語音で憶える方が余程 意味があります
(まあ、あまり使いませんが)。
次は
「韃靼(だったん)」
「韃(だつ)」も「靼(たん)」も、
もともとは靴紐(くつひも)の事ですが、
「韃靼」は、蒙古族のこと、「タタール」の音訳です。
日本語音は(だったん)ですが、
この本には「韃靼(タルタル)」と書かれています。
蒙古族については、
例えば「wikipedia」によれば、
語源は古テュルク語の「他の人々」の意のTatar(タタル)で、
中国語は韃靼(dada )、
アラビア語はتتر(タタル)、
ペルシア語は تاتار (タータール)、
ロシア語では Татар(タタール)、
西ヨーロッパの諸言語では Tartar(タルタル)
日本語は、韃靼(だったん)
と書かれています。
この作者は、何故(タルタル)を選んだのでしょう?
語源は同じですが、
「韃靼」の漢字を(タルタル)とは読めません。
「韃靼海峡」(だったんかいきょう)を(タルタルかいきょう)と呼ぶでしょうか?
「韃靼蕎麦茶」(だったんそばちゃ)は(タルタルそばちゃ)でしょうか?
誰かが「タルタル」と発音した時に、
誰の頭に「韃靼」という文字が思い浮かぶのでしょう?
ロシア語 のТатарや
西ヨーロッパの諸言語の Tartarに、
(だったん)とルビをふる事があり得るでしょうか?
「韃靼」の日本語音は
「韃(だつ)」と「靼(たん)」で(だったん)です。
もし作者がどうしても(タルタル)を使いたいのであれば、
単独でカタカナで「タルタル」か「Tartar」と書くべきです。
だいたい「タルタル」を含めた外来語は、
別にカタカナで表記する事は、
小学校一年生で学ぶはずですが、どうしたのでしょう?
また、
「中国皇帝」に(チャイニーズ・エンペラー)
とルビをふっています。
厳密に言えば、中国の「皇帝」と西洋の(エンペラー)は同じではありませんし、
「中国」「皇帝」という字の読めない日本人は、
そうはいないと思います。
それに「チャイニーズ・エンペラー」も外来語ですから、
単独で、カタカナ表記が正解です。
更に
「李鴻章(りこうしょう)」に
中国語音で(リイホンチャン(この表記も如何な物かとは思いますが))とルビをふりながら、
別の章では、
「李鴻章」に(プレジデント・リー)。
例えば、
「仏」に(フランス)
「独」に(ドイツ)
というルビをふることがあります。
これは、『漢和辞典』にも載っていますが、
「仏」は「仏蘭西(フランス)」の略で、
「仏」という漢字に「フランス」という意味があるからです。
「独」もまた「独逸(ドイツ)」の略で、
「独」という漢字に「ドイツ」という意味があります。
しかし、
「李」「鴻」「章」という漢字の中に(プレジデント)という意味は含まれません。
デタラメです。
「プレジデント」という外来語も、
単独でカタカナ表記すべきで、
二重にデタラメであると言わざるを得ません。
私には、この小説家が何を目的にして、
漢字にルビをふったのかは分かりません。
しかし、恐らく最初は、
漢字に中国語音に近いルビをふる事を目的としていたはずで、
ですから、
あまり好い事とは思いませんが、
西太后(せいたいごう)に対して
(シータイホウ)などというルビを付けていたのではないかと思います。
しかし、漢字に外国語音のルビをふろうという人は、
そもそも、漢字という物を知らない為に、その様な事を考えつくわけで、
その様な人が、一見合理的な理論に基づいて漢字をいじったとしても、
往々、不見識を晒す結果になります。
この本の中で、最も不見識なルビは、
「天!地!」(ティエン!チイ!)
これを見たときには驚きました。
(ティエン チイ)は、
日本語音でも中国語音でもありません。
日本語音は言うまでもなく(てんち)
中国語音は(tian di(ティエン ディ))。
「天!地!」(ティエン!チイ!)は、
日本語を中国語風に読んだ、なんちゃって中国語です。
例えば「玄関」を(グゥエン クゥワン)と発音するような物で
タモリさんや次長課長の話す、
あの中国人の物まね芸と同じです。
この様な物なら、
別に勉強しなくても誰でも話せます、
なんちゃって中国語だからです。
他にも
「植民地」(コロニー)
「謝謝」(ありがとう)
「双眼鏡」(スコープ)
「埠頭」(プラットホーム)
「窓」(インヅ)
「汽笛」(ホイッスル)…
漢字のルビとしても、言語としても、文字の表記から見ても、
誤っていると言わざるを得ません。
だいたい、
「埠頭(ふとう)」とは、「はとば」「ふなつきば」の事です、
「Platform」は、
駅の「客車の乗降口」停車場などの「車に乗り降りする所」です。
「埠頭」に「プラットホーム」と言うルビをふる事はできません。
無理があります。
その他、
「窓」(インヅ)に至っては、
何語なのかも分かりません。
ひょっとすると、漢字の方が間違っているかもしれません。
ちなみに
「窓」は中国語音は(chuang(チュワン))です。
加えて、
「コロニー」「スコープ」「プラットホーム」「ホイッスル」等の外来語を、
単独でカタカナで表記する事は、
小学校一年生で、カタカナを学習したときに習います。
結論として、
この本は、日本語音以外のルビばかりで非常に読みにくく、
見ていて気持ちが悪い上に、
肝心のルビが信用できません。
残念ながら、子供には読ませることの出来ない本です。
子供の頭の中の漢字体系を、
破壊してしまう恐れがあるからです。
漢字に外来語のルビをふるようなデタラメも、
小学生にも中学生にも見せられません。
昨日、NHK教育の「手話ニュース」を見ていたら、
韓国の平昌が、オリンピック招致に成功した事を伝えていました。
そのニュースは、字幕つきで、
字幕の漢字にはルビがふってあるのですが、
「五輪」という漢字に(オリンピック)とふってありました。
デタラメです。
「五輪」は(ごりん)
「オリンピック」は外来語なので、
単独で、カタカナで「オリンピック」と表記するのが正解です。
教育チャンネルが、小学生以下では困ります。
これでは、NHK教育から、
日本の文字体系が狂う事にもなりかねません。
「文字体系というものは、
そう簡単に人工的にいじることはできないので、
長らくの民族的経験といいますか、
その集積によって
現代に至っているわけで、
それを一気にこれに変えてしまえと、
合理的な理論というのを持ってきても、
実はやってみたらそれは非常に不合理なのです。」
山本七平著『漢字文化を考える』より。
漢字は、日本人が先祖代々受け継ぎ、
子々孫々に伝えなければならない道具です。
道具は大切に、正しく使い、
できるだけ良い形で、次の世代に残すべきです。
6.国内でもこの原則は生きている
例えば、
ある日突然、
民主党の渡部恒三先生が、
「僕の名前を呼ぶときには、東京弁ではなく、
親が呼ぶように、津軽弁で「渡部(わだなべ)」と呼んで欲しいんだなあ」とか、
名古屋の河村 たかし市長が、
「私の名前を呼ぶときには、
名古屋弁のアクセントでお願いしたいんだなも」などと、
言い出したらどうなるでしょう?
青森の「安達」さんや、
島根の「亀田」さんが…。
まあ、実際にはその様な事を言い出す人はいませんし、
そんな事を言い出せば、
皆から見識を疑われるに決まっています。
医者に行った方がいいと思う人もいるかもしれません。
『砂の器』に登場する「島根」の亀嵩(かめだけ)を引用するまでもなく、
日本国内には、いろいろな方言があり、
「漢字」は各地方の発音で読まれていますが、
漢字にルビをふるときには、
『漢和辞典』や『国語辞典』等の字引の音をふりますし、
東京の人が青森や島根に行けば、
その人は、現地の方言で呼ばれます。
漢字は、漢字文化圏では、
その地域、その国の音で読むという暗黙の了解というか原則があるからです。
この理由に因って、
まあ知らなくても普通に常識として、
民主党の渡部恒三先生も、
名古屋の河村 たかし市長も
青森の「安達」さんや
島根の「亀田」さんも、
「親の呼ぶように呼んで欲しい」とか、
「現地の発音通りに漢字にるびをふって欲しい」とは、
言いませんし、
この人々の名前を、標準語で呼んでも苦情は出ません。
因みに、広東省で死亡説の流れた「江沢民」も、
当然、広東省では広東語音で呼ばれていました。
当然、日本ではこの人物は(こうたくみん)です。
以下に続きます。(もし宜しければ、拡散お願いします)
HQ【Kleiber】Brahms : Symphony No. 4 mvt 3【クライバー:ブラームス/交響曲第4番】
外国語音で書かれたルビの、
もう一つの弊害として、
正誤の判定ができない、
正解か間違っているか、読んでいる者に判らない、
という問題があります。
例えば、「山田(やすだ)」と書かれていたら
これを読んだ人は、
間違いか?何か理由があるのだろうか?
と思うはずです。
人によっては、見ていて気持ちが悪いと感じるかもしれません。
漢字は、日本人の持つ共通認識の上に成り立って、
使用されているからです。
記憶があやふやな場合は、
『辞書』で検索する事もできます。
しかし、外国語のルビの場合は、
普通の日本人には、
正解なのかデタラメなのか分かりません。
普通、私達は、新聞やテレビ・映画の字幕の漢字ルビを、
信用して見ています。
特に大手新聞やNHKは日本語の基準でもあり、
変な記述があるとは思いません。
それは、外国語でも同じで、
自身が知らない言葉でも、
新聞を信用して「へー、そうなんだ」と考えます。
しかし、それ程信用できる物でしょうか?
例えば、
御存知の方も多いと思いますが、
最近の事件で、
韓国籍の趙永珠(ちょうえいじゅ)という女性が、
不幸にも事件に巻き込まれたという報道がありました。
この女性の名前ですが、
『読売新聞・神奈川 2011年7月6日』版では、
「韓国籍で同市南区、
飲食店経営趙永珠(チョヨンジュ)さん(当時41歳)の
足首が見つかった事件で…」
『毎日新聞 2011年7月5日 東京朝刊』では、
「山口容疑者は知人からの借金返済のため、
妻の飲食店経営、趙永珠(チョウヨンジュ)さん(当時41歳)から
たびたび金を借りていた。」
『読売新聞』と『毎日新聞』は大手新聞社ですが、
「趙」は「チョウ」でしょうか「チョ」でしょうか、
どちらが正しいのでしょう?
日本語音なら「ちょう」です。
例えば、
中国人の「呉中華」(架空の人名です)の場合、
日本語音は(ごちゅうか)一つですが、
中国語音の場合は(Wu zhong hua)の音を、
耳で聞いて表記することになります。
現在、新聞や映画の字幕で採用されている、
この漢字の発音には、それぞれ、
呉の場合(ウ)(ウー)、
中には(チョン)(ジョン)(チュン)、
華には(フア)(ファー)(ホア)などがあります。
すると、一人三文字の名前に対して
最多で十八種の発音が存在する事になり、
例えば、
「ウチョンフア」と「ウージョンファー」はまるで別人で、
これでは、
名前の役割を果たしません。
そもそも、漢字文化圏では、
外国人の人名も地名も、
日本では漢字は日本語音で読む事になっていて、
外国語音で読む必要はありません。
「呉中華」は(ごちゅうか)と読むべきですし、
誤りも少ないはずです。
例えば、
中国語の教科書に、
カタカナで中国語音でルビのふってある出版物があります。
これは、
勉強をする人への便宜としての記述で、
誤った音を書けば、
著者である専門家の見識を疑われますので、
正確な音に近い音が書かれていると思われます。
では、普通の小説はどうでしょう?
最近NHKでもドラマ化された
中国が舞台の小説があります。
この原作本は、
日本の漢字に大量に日本語音以外のルビがふってありますが、
それについて、少し調べてみました。
どれ程正確に書かれた物か、
興味があったからです。
以下は、この本の文章中に示された単語で、
特に目についた物を取り上げ、
説明した物です。
例えば、最初の方に出てくる、
「大哥(ダアコオ)」「二哥(アルコオ)」「阿哥(アコ)」
について、
「哥」は「兄貴」「兄さん」という意味で、
「大哥」とは「長兄」、「二哥」は「次兄」の意。
「阿哥」は、清朝における王子の幼名で、これは特別な単語です。
「哥」という漢字に対して
一人の人が付けたにも関わらず
(コオ)と(コ)という音がある事になります。
どちらが正しいのでしょう?
どちらも誤りです。
そもそも中国語では、「哥」は(ge)の音で、
(e)の音は日本語の中にはありませんが(ge)は、
(グ)や(ガ)の音に近くなります。
(コオ)でも(コ)でもありません。
(ダアコオ)(アルコオ)(アコ)
と発音してみても、
日本人も中国人も、漢字が思い浮かびません。
無駄だと思います。
『漢和辞典』等で検索すれば、
「哥」は(か)、「阿哥」は(あか)です。
「哥」を(か)と日本語音で憶える方が余程 意味があります
(まあ、あまり使いませんが)。
次は
「韃靼(だったん)」
「韃(だつ)」も「靼(たん)」も、
もともとは靴紐(くつひも)の事ですが、
「韃靼」は、蒙古族のこと、「タタール」の音訳です。
日本語音は(だったん)ですが、
この本には「韃靼(タルタル)」と書かれています。
蒙古族については、
例えば「wikipedia」によれば、
語源は古テュルク語の「他の人々」の意のTatar(タタル)で、
中国語は韃靼(dada )、
アラビア語はتتر(タタル)、
ペルシア語は تاتار (タータール)、
ロシア語では Татар(タタール)、
西ヨーロッパの諸言語では Tartar(タルタル)
日本語は、韃靼(だったん)
と書かれています。
この作者は、何故(タルタル)を選んだのでしょう?
語源は同じですが、
「韃靼」の漢字を(タルタル)とは読めません。
「韃靼海峡」(だったんかいきょう)を(タルタルかいきょう)と呼ぶでしょうか?
「韃靼蕎麦茶」(だったんそばちゃ)は(タルタルそばちゃ)でしょうか?
誰かが「タルタル」と発音した時に、
誰の頭に「韃靼」という文字が思い浮かぶのでしょう?
ロシア語 のТатарや
西ヨーロッパの諸言語の Tartarに、
(だったん)とルビをふる事があり得るでしょうか?
「韃靼」の日本語音は
「韃(だつ)」と「靼(たん)」で(だったん)です。
もし作者がどうしても(タルタル)を使いたいのであれば、
単独でカタカナで「タルタル」か「Tartar」と書くべきです。
だいたい「タルタル」を含めた外来語は、
別にカタカナで表記する事は、
小学校一年生で学ぶはずですが、どうしたのでしょう?
また、
「中国皇帝」に(チャイニーズ・エンペラー)
とルビをふっています。
厳密に言えば、中国の「皇帝」と西洋の(エンペラー)は同じではありませんし、
「中国」「皇帝」という字の読めない日本人は、
そうはいないと思います。
それに「チャイニーズ・エンペラー」も外来語ですから、
単独で、カタカナ表記が正解です。
更に
「李鴻章(りこうしょう)」に
中国語音で(リイホンチャン(この表記も如何な物かとは思いますが))とルビをふりながら、
別の章では、
「李鴻章」に(プレジデント・リー)。
例えば、
「仏」に(フランス)
「独」に(ドイツ)
というルビをふることがあります。
これは、『漢和辞典』にも載っていますが、
「仏」は「仏蘭西(フランス)」の略で、
「仏」という漢字に「フランス」という意味があるからです。
「独」もまた「独逸(ドイツ)」の略で、
「独」という漢字に「ドイツ」という意味があります。
しかし、
「李」「鴻」「章」という漢字の中に(プレジデント)という意味は含まれません。
デタラメです。
「プレジデント」という外来語も、
単独でカタカナ表記すべきで、
二重にデタラメであると言わざるを得ません。
私には、この小説家が何を目的にして、
漢字にルビをふったのかは分かりません。
しかし、恐らく最初は、
漢字に中国語音に近いルビをふる事を目的としていたはずで、
ですから、
あまり好い事とは思いませんが、
西太后(せいたいごう)に対して
(シータイホウ)などというルビを付けていたのではないかと思います。
しかし、漢字に外国語音のルビをふろうという人は、
そもそも、漢字という物を知らない為に、その様な事を考えつくわけで、
その様な人が、一見合理的な理論に基づいて漢字をいじったとしても、
往々、不見識を晒す結果になります。
この本の中で、最も不見識なルビは、
「天!地!」(ティエン!チイ!)
これを見たときには驚きました。
(ティエン チイ)は、
日本語音でも中国語音でもありません。
日本語音は言うまでもなく(てんち)
中国語音は(tian di(ティエン ディ))。
「天!地!」(ティエン!チイ!)は、
日本語を中国語風に読んだ、なんちゃって中国語です。
例えば「玄関」を(グゥエン クゥワン)と発音するような物で
タモリさんや次長課長の話す、
あの中国人の物まね芸と同じです。
この様な物なら、
別に勉強しなくても誰でも話せます、
なんちゃって中国語だからです。
他にも
「植民地」(コロニー)
「謝謝」(ありがとう)
「双眼鏡」(スコープ)
「埠頭」(プラットホーム)
「窓」(インヅ)
「汽笛」(ホイッスル)…
漢字のルビとしても、言語としても、文字の表記から見ても、
誤っていると言わざるを得ません。
だいたい、
「埠頭(ふとう)」とは、「はとば」「ふなつきば」の事です、
「Platform」は、
駅の「客車の乗降口」停車場などの「車に乗り降りする所」です。
「埠頭」に「プラットホーム」と言うルビをふる事はできません。
無理があります。
その他、
「窓」(インヅ)に至っては、
何語なのかも分かりません。
ひょっとすると、漢字の方が間違っているかもしれません。
ちなみに
「窓」は中国語音は(chuang(チュワン))です。
加えて、
「コロニー」「スコープ」「プラットホーム」「ホイッスル」等の外来語を、
単独でカタカナで表記する事は、
小学校一年生で、カタカナを学習したときに習います。
結論として、
この本は、日本語音以外のルビばかりで非常に読みにくく、
見ていて気持ちが悪い上に、
肝心のルビが信用できません。
残念ながら、子供には読ませることの出来ない本です。
子供の頭の中の漢字体系を、
破壊してしまう恐れがあるからです。
漢字に外来語のルビをふるようなデタラメも、
小学生にも中学生にも見せられません。
昨日、NHK教育の「手話ニュース」を見ていたら、
韓国の平昌が、オリンピック招致に成功した事を伝えていました。
そのニュースは、字幕つきで、
字幕の漢字にはルビがふってあるのですが、
「五輪」という漢字に(オリンピック)とふってありました。
デタラメです。
「五輪」は(ごりん)
「オリンピック」は外来語なので、
単独で、カタカナで「オリンピック」と表記するのが正解です。
教育チャンネルが、小学生以下では困ります。
これでは、NHK教育から、
日本の文字体系が狂う事にもなりかねません。
「文字体系というものは、
そう簡単に人工的にいじることはできないので、
長らくの民族的経験といいますか、
その集積によって
現代に至っているわけで、
それを一気にこれに変えてしまえと、
合理的な理論というのを持ってきても、
実はやってみたらそれは非常に不合理なのです。」
山本七平著『漢字文化を考える』より。
漢字は、日本人が先祖代々受け継ぎ、
子々孫々に伝えなければならない道具です。
道具は大切に、正しく使い、
できるだけ良い形で、次の世代に残すべきです。
6.国内でもこの原則は生きている
例えば、
ある日突然、
民主党の渡部恒三先生が、
「僕の名前を呼ぶときには、東京弁ではなく、
親が呼ぶように、津軽弁で「渡部(わだなべ)」と呼んで欲しいんだなあ」とか、
名古屋の河村 たかし市長が、
「私の名前を呼ぶときには、
名古屋弁のアクセントでお願いしたいんだなも」などと、
言い出したらどうなるでしょう?
青森の「安達」さんや、
島根の「亀田」さんが…。
まあ、実際にはその様な事を言い出す人はいませんし、
そんな事を言い出せば、
皆から見識を疑われるに決まっています。
医者に行った方がいいと思う人もいるかもしれません。
『砂の器』に登場する「島根」の亀嵩(かめだけ)を引用するまでもなく、
日本国内には、いろいろな方言があり、
「漢字」は各地方の発音で読まれていますが、
漢字にルビをふるときには、
『漢和辞典』や『国語辞典』等の字引の音をふりますし、
東京の人が青森や島根に行けば、
その人は、現地の方言で呼ばれます。
漢字は、漢字文化圏では、
その地域、その国の音で読むという暗黙の了解というか原則があるからです。
この理由に因って、
まあ知らなくても普通に常識として、
民主党の渡部恒三先生も、
名古屋の河村 たかし市長も
青森の「安達」さんや
島根の「亀田」さんも、
「親の呼ぶように呼んで欲しい」とか、
「現地の発音通りに漢字にるびをふって欲しい」とは、
言いませんし、
この人々の名前を、標準語で呼んでも苦情は出ません。
因みに、広東省で死亡説の流れた「江沢民」も、
当然、広東省では広東語音で呼ばれていました。
当然、日本ではこの人物は(こうたくみん)です。
以下に続きます。(もし宜しければ、拡散お願いします)
HQ【Kleiber】Brahms : Symphony No. 4 mvt 3【クライバー:ブラームス/交響曲第4番】