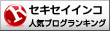南三陸海岸というランプを降りたところは丘陵地帯で、少し走るとちょっとした集落があります。今はその先に町役場があるようです。

町役場までは行かず、海に向かって坂を下りていくと、志津川の集落が見えてきます。かつてはここが中心的な市街地で、町役場もここにありました。

町役場付近に鉄道の駅もあり、集落が展開していたようです。

庁舎はいくつかに分かれていて、鉄骨造り3階建ての建物を防災対策庁舎としていました。職員や近隣住民は3階の屋上に避難しましたが、津波は16.5mに達し、43名が犠牲となりました。

2階が放送室となっていて、若い女性職員が防災無線で避難を呼び掛けている最中、津波に襲われて殉職しました。

このエピソードは震災後、マスコミ等で何度か取り上げられていたのでご記憶の方もおられると思います。
この一連の記事の、一種の通奏低音として流れている、NHKのドキュメンタリー番組ですが、たしかご両親が取材を受けていたような記憶があります。

津波は当初6mの予想と放送していましたが、最後の放送は10mとなっていたそうです。
屋上に避難した人たちも全身濁流に飲まれて、アンテナやどこかにしがみつくことができた人だけが生き残ったそうです。酷寒の中、一夜を明かしたとか。

復興に際し土地のかさ上げ等をしたため、今は地形からして相当変わっています。先ほどの庁舎の北側には商店街(さんさん商店街)が広がり、震災の記念館と駅があります。

鉄道の駅ではなくてBRTです。
この写真で見るとただのバス停みたいですが、画面左側にはかなり大きな駅舎があり、記念館も隣接しています。
BRTは旧線路敷を専用道として走行し、一部区間はここ志津川のように一般道を通り町の中心部に停車します。

もとの鉄道駅も遺構として残っているので行ってみます。
先ほどの庁舎の南側に築堤の一部が残っていて、駅ホームが保存されています。

この駅名標自体は後からの再築のようです。
前述のようにホームは土手の上にあり、地上に駅舎がありました。乗客は階段を登ってホームに上がっていました。

気仙沼線は地方線としては比較的新しく、開通は昭和52年だった由。
この地下道ポータルに埋め込まれた建設年は1976-2となっていました。

駅と、冒頭の防災庁舎の間は公園になっていて、小高い丘ができています。
海はこんな感じで見えます。
右側にビルが見えますが、これも遺構で高野会館という建物です。次の移動先に行くときに脇を通ったのですが、見逃してしまいました。