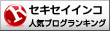南三陸町から海沿いに国道398号線を南下していきます。比較的線形は良く、地元のひとのペースは速めですが、こちらは不案内な旅人なので適当に邪魔にならないように走ってました。
すると、トンネル手前からすごい勢いで追い越していく銀色のプリウス・ワゴンがいました。ちょっとムッとしながら追走していくと、くだんのプリウスが、大型トラックに行く手を阻まれているのが見えました。
大きな橋手前の信号で追いつきました。橋を渡ったところにまた信号があって停車。運転手の姿は良く見えませんが、なんとなくこちらの雰囲気察して💦
っぽい思いをしているようにも思えます。。
前の車は直進、こちらは目的地が左なので左折しました。
この信号の辺りがいわゆる「三角地帯」と地元で呼ばれていたことは後で知りました。
石巻市立大川小学校は北上川の河口ほど近く、石巻市釜谷という地区にありました。北上川の河口は追波湾と呼ばれていますが、そこからは約3.7km離れているとのことです。小学校の辺りの土地は平らで海抜1-1.5mぐらいです。
2011年3月11日の東日本大震災では北上川および地表を遡上してきた津波が学校を襲い、地震後校庭に残っていた生徒78人中70人死亡、4人行方不明、教職員11名中10名が死亡、そのほかスクールバスの運転手、保護者、避難してきた近隣住民も犠牲になりました。
大川小学校の正確な地名は石巻市釜谷字山根1番地です。
釜という地名は東北地方に多いそうで、これは「噛マ」に通じ、津波により侵食された地域に多い地名だそうです。また山根は山の麓を示し、このことから古来津波がこの付近まで到達した地域であることを示唆する地名になっている、という見方もできるそうです(後述書より)。
この特徴的な校舎は震災以来ニュース等で繰り返し映し出され(残念ながら被災後の姿でですが)、印象に残っています。
円柱や扇形を組み合わせたつくりになっていて、体育館との間はガラス張りの渡り廊下でつながっていました。
1985年に建てられました。
設計者の北澤興一氏によると、宮城県沖地震(1978年)の経験や地盤の弱さから、地震対策は特に気を使い、土台の杭を十分に施したそうです。
しかしながら、津波に対する対策は十分ではなかったと述懐しています。
設計段階では裏山にあずやまを建て、遊歩道で結ぶ提案をしましたが、予算面から断念したとのこと。無理しても作るべきだった、と今も繰り返し後悔しているそうです(以上河北新報2016.10より)。
校舎のすぐ裏手に山があります。画面中央、踏み分け道奥に白い標識が見えますが、これは津波到達点を示しています。
震災当日、教務主任や、また生徒たちからも、裏山への避難を提案する声はありましたが、教頭以下教師陣の意見はまとまらず(校長は休暇で不在)、震災後50分余り校庭で待機した末、「三角地点」への退避を開始、その直後に波に飲まれました。
詳細な位置は不明ですが、生徒たちの遺体がもっとも多く見つかったのは「三角地帯」手前の斜面だったそうです。
津波は北上川を遡上すると同時に陸地を伝っても押し寄せており、これらの波がぶつかって渦を巻いていたのではないかという記述も見られます。
生徒たちの多くは折り重なるようにして遺体となって発見されました。
体育館の傍らに野外ステージがあり、その壁に子どもたちの書いた壁画が残っています。卒業制作みたいな感じでしょうか。
震災後、学校側との複数回にわたる保護者説明会、更には文科省からの提案を受けて石巻市が設立した事故検証委員会による検討も進められましたが、遺族らの納得のいく検証が得られなかったことから、2014年に児童の遺族29名が原告となり石巻市、宮城県に対する民事訴訟を起こしました(一審判決は石巻市と宮城県の過失責任を認定、同じく国賠責任を認めた高裁判決に対し宮城県、石巻市が上告するも2019年10月に退けられて判決確定)。
訴訟の経緯とその意義については今読んでいる「水底を掬う」(川上正二、吉岡和弘、斎藤雅弘、信山社2021)にまとめられており、このブログの上記記述でも本書を一部参照しています。ただし実はまだ読了していないので、裁判経緯等については後日機会があれば触れることにします。
その要諦は、一審で争われた「現場責任」に対し、二審では市教委まで含めた学校運営に対する組織的な防災体制の不備が問われたのであり、千年に一度と言われる今回の地震そのもの(の予見可能性)ではない、という所にあるようです。
つまり、災害そのものへの直接対応そのものが問われているのではなく、更には(今回のような)想像を超えるような大災害への対応策を問うているのでもない、という点に意義があるようなのですが、ここでは詳述を避けます。
前回に続き、この10数年の間に記憶に残ったNHKのドキュメンタリーですが、本件でも生徒と共に犠牲となった若い先生のご両親を取り上げた番組を思い出します。
一人息子さんで、念願の教師になって張り切っていたのだそうです。
ご両親からすれば大切な息子さんを喪ったことになりますが、同時に多くの教え子を救えなかったという事もあり、苦悩する姿を描いていました。
自宅の畑で作ったハボタンを、息子さんのために(お墓に持って行ったのかな)選んでいたシーンが印象に残っています。
今回の総走行距離は1,064Km, 往路(女川経由石巻のホテルまで)は449Kmで燃費(満タン法)18.134Km/L、復路(石巻から陸前高田~自宅)615Km、燃費17.744Km/L、全行程の総合燃費17.906Km/Lでした。復路は流れの速い高速で少し燃費を落としたかもしれません。
これで今回の、震災遺構を訪ねる旅行記はおしまいです。
お読みいただいた方々、ありがとうございました。