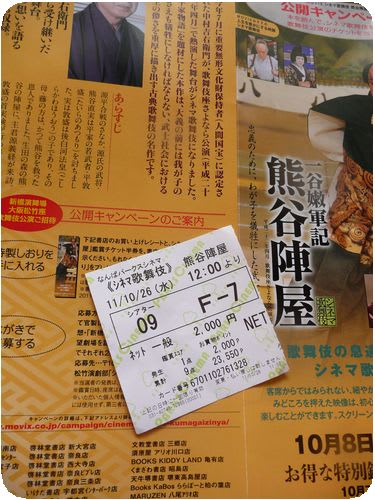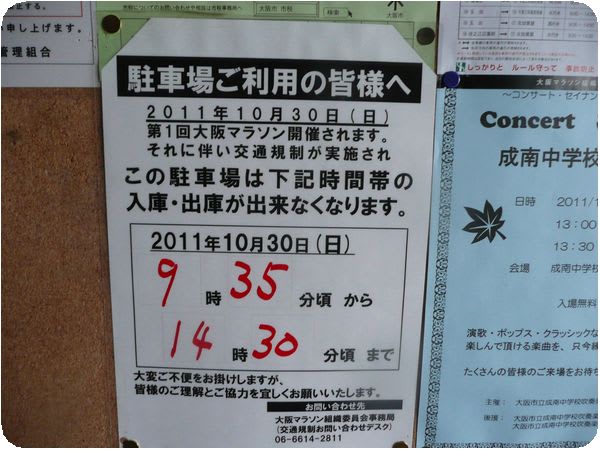11月ももう半ば、昨日から姫へ来ていますが、こちらは着いた途端に暑い感じがしました。大阪でも少しは寒さも増してるものの靴下要らずの生活は続いています。
奈良公園まで来る観光客が必ずと言っていいほど訪れる古刹が三つあり、一つは興福寺、もう一つは東大寺、そして春日大社です。私はこの歳になるまで何度か奈良公園を訪れていますが、一度も春日大社へは行ったことがありませんでした。今回、正倉院展を観るにあたって、一度春日大社へも赴いてみようと思っていたのでした。

奈良公園から表参道を暫らく歩くと、ここは二の鳥居。一の鳥居は奈良公園の中にあります。結構人通りがあり誰もいないところを撮るのは至難の業、後ろから人が歩いてきてるのは知っていましたが、立ち止まってピントを合わせていると、やはり抜かされて左隅に写り込んでしまいました。

石灯籠が並ぶ参道、最初の写真の南門までの距離が結構あります。さすがに広い境内やなぁと思いながら歩きます。

南門をくぐるとあるのは普通なら拝殿、でもここでは幣殿とか舞殿と呼ばれていて、この奥にいろんな社があるのですが、拝観料が500円もかかるので、大概の人はここで帰ってしまうようです。

『砂ずりの藤』と呼ばれる藤の木、今は季節外れなので花は咲いていませんし、枝も地に届くほど長くはありません。いくら砂ずりでも鶏とは関係無いと思いますので、よほど長い花房になるのでしょう。特別にこのようなものを設えてあるのは、やはり藤原氏ゆかりの神社なのでしょうか。そんな話はこの神社のHPには一切触れていません。

シカも参拝に来ています、いや、ただ人に紛れておればエサが貰えるという条件反射だけなのでしょう。
案内板を見ると山内の一番奥に紀伊神社というのがあり、和歌山県に関係ある私としてはとても行ってみたくなりました。

途中にあった若宮社、改築中だそうで真っ暗です。

ここが紀伊神社、御神徳は新たな生気をいただく神様とありました。一人熱心にお参りしている人がいて、終わるまで待っていたのですが、はたして和歌山県人だったのでしょうか、それとも新たな生気が欲しかったのでしょうか。

紀伊神社の手前にあった龍王珠石、どれが珠石なのかよく分かりませんが、丸い石はみな珠石なのでしょうね。
奥まで来るような人は少なく、寂しいながらも写真は撮りやすいのですが、そう思ってる人がいるもんで、撮りたいところは暫らく待っていないといけないこともありました。

来た道を帰るのも無駄なような気がして、あまり人気がない山道を歩いて帰ったのでした。こんなところでシカに出会うとシカも私もびっくりするのでしょうが、シカも分かっていて人気のないところには現れません。