宮中で、人が増えすぎたのかも知れません。
天皇は多くの女性と交わり、その子たちが増えすぎて、地方からの租税の収入だけでは賄いきれなかったのかも知れません。
公卿たちを宮中の外に出す動きがあったかも知れません。
下野した皇子たちには姓名が与えられ、彼は源氏の姓を賜った。
清和天皇の六番目の孫が源の姓を貰い、源経基(つねもと)を名乗り、この地に住まいし、後にはここに祀られている。

神社のパンフによれば、源経基(六孫王)の子、源満仲が住まいし、後に摂津の多田郷に本拠を据えたのでした。

広かった境内が新幹線の開通により、広大な境内の敷地が、現存する僅かな広さになりました。
徳川が源氏の流れであったから、石灯籠など、諸大名が寄進しています。

神社の系図を見ると、満仲の子らが、諸国に散らばって行き、それぞれ河内源氏・奈良の大和源氏などなど全国に広がって行った。
中でも、この系図を見ると頼信の河内源氏系列は、頼義ー義家ー義親ー為義ー義朝…と続き、鎌倉幕府をつくりますね。

さて、六尊王神社の祭神についての記録があります。

台座の牡丹の花が、ここの神社の紋章になっています。

右は、当神社の神輿の蔵の紋章です。


サクラは、この時はまだ1分咲きですね。

六孫王の人となりなどについての表記がある。字が小さいですが、なかなか詳しいですよ。

境内にあったこの桜は、一本の木から紅白の花が咲いているようである。(源平?)

白い椿ですね。源氏の白旗でしょうか。

高架の線路で敷地を削った新幹線700が走る。音は静かですね。

天皇は多くの女性と交わり、その子たちが増えすぎて、地方からの租税の収入だけでは賄いきれなかったのかも知れません。
公卿たちを宮中の外に出す動きがあったかも知れません。
下野した皇子たちには姓名が与えられ、彼は源氏の姓を賜った。
清和天皇の六番目の孫が源の姓を貰い、源経基(つねもと)を名乗り、この地に住まいし、後にはここに祀られている。

神社のパンフによれば、源経基(六孫王)の子、源満仲が住まいし、後に摂津の多田郷に本拠を据えたのでした。

広かった境内が新幹線の開通により、広大な境内の敷地が、現存する僅かな広さになりました。
徳川が源氏の流れであったから、石灯籠など、諸大名が寄進しています。

神社の系図を見ると、満仲の子らが、諸国に散らばって行き、それぞれ河内源氏・奈良の大和源氏などなど全国に広がって行った。
中でも、この系図を見ると頼信の河内源氏系列は、頼義ー義家ー義親ー為義ー義朝…と続き、鎌倉幕府をつくりますね。

さて、六尊王神社の祭神についての記録があります。

台座の牡丹の花が、ここの神社の紋章になっています。

右は、当神社の神輿の蔵の紋章です。


サクラは、この時はまだ1分咲きですね。

六孫王の人となりなどについての表記がある。字が小さいですが、なかなか詳しいですよ。

境内にあったこの桜は、一本の木から紅白の花が咲いているようである。(源平?)

白い椿ですね。源氏の白旗でしょうか。

高架の線路で敷地を削った新幹線700が走る。音は静かですね。

















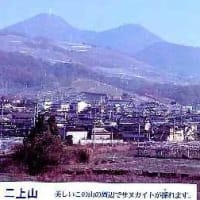
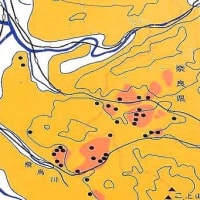


こういう謂れがあったんですか
歴史というのは面白いですね