季節(二十四節気)は小寒
この次には大寒がひかえているけど、もう十分な寒さです。
寒さよりは熱さが苦手な者ぞろいの我が家ですが、それでもさすがに「夜はあったかい鍋料理がいいな」なんてリクエストがあがるようになりました。
よって最近は鍋続き。
寒い寒い外から帰ってきて食べたくなるのは鶏肉と葱を入れた鍋
鶏肉は身体を養い温め、葱(特に白い部分)は寒邪を追い払い体内の気血を通す効果があります。
鶏肉は骨つきだと更に効果が高まります。
食べ終わる頃には身体がじんわりぽかぽかとして、まるでお風呂に浸かっているかの様な感覚になり、「病後や虚弱な人には骨つき鶏肉のスープを飲ませると良い」と中国で言われるのがよくわかる様な気がします。
陽の不足による冷え性の人も、血の不足による冷え性の人も、どちらにもお勧めできる組み合わせです。
好みで生姜や唐辛子を加えるのも良いですが、あまり度を過ぎない様に。
加えなくても十分あたたまりますから。
さて、年始に百合根で茶碗蒸しを作ってからすっかり虜になった私+1名。
2回目、3回目は鰹ダシではなく骨つき鶏肉のスープで作りました。
鰹ダシと違って底力があるというか、パワーを感じ、それでいて身体に負担があると言うわけではないのでこの季節にピッタリ且つ風邪で疲れた身体にはとてもありがたい一品です。
中国に留学するまでは鰹ダシ以外には考えられなかった茶碗蒸しですが、今では鶏、豚、魚色々と自由に楽しんでいます。
そして普段は中国風に具は入れません。
その方がダシの味が濁らずに卵とダシの合わさった優しい味をじっくりと楽しめるのです。ほわほわの食感も具がないからこそです。
百合根は香りが強くなく、そのほこほこねっとりな食感が茶碗蒸しにとても合う具材だと思います。
茶碗蒸しは消化が良いので夜遅い晩ご飯になっても身体への負担が少なく安眠の助けになりますね。
百合根入りならさらに安眠効果が高まるし、鶏肉ダシなら身体も温まりポカポカでよく眠れるでしょう。
身体が冷えてお布団の中に入ってもなかなか眠れない、夜中も寒くて目が覚める、、、なんて人は是非是非
百合根入りの鶏肉ダシの茶碗蒸しを! 大変なら、百合根が美味しいこの季節にぜひ百合根入りの骨つき鶏肉スープとかだけでも作ってみて下さい。
我が家には百合根があと半個残っています。数日中に茶碗蒸しにしてこの冬最後の百合根を楽しみたいと思います。
この次には大寒がひかえているけど、もう十分な寒さです。
寒さよりは熱さが苦手な者ぞろいの我が家ですが、それでもさすがに「夜はあったかい鍋料理がいいな」なんてリクエストがあがるようになりました。
よって最近は鍋続き。
寒い寒い外から帰ってきて食べたくなるのは鶏肉と葱を入れた鍋
鶏肉は身体を養い温め、葱(特に白い部分)は寒邪を追い払い体内の気血を通す効果があります。
鶏肉は骨つきだと更に効果が高まります。
食べ終わる頃には身体がじんわりぽかぽかとして、まるでお風呂に浸かっているかの様な感覚になり、「病後や虚弱な人には骨つき鶏肉のスープを飲ませると良い」と中国で言われるのがよくわかる様な気がします。
陽の不足による冷え性の人も、血の不足による冷え性の人も、どちらにもお勧めできる組み合わせです。
好みで生姜や唐辛子を加えるのも良いですが、あまり度を過ぎない様に。
加えなくても十分あたたまりますから。
さて、年始に百合根で茶碗蒸しを作ってからすっかり虜になった私+1名。
2回目、3回目は鰹ダシではなく骨つき鶏肉のスープで作りました。
鰹ダシと違って底力があるというか、パワーを感じ、それでいて身体に負担があると言うわけではないのでこの季節にピッタリ且つ風邪で疲れた身体にはとてもありがたい一品です。
中国に留学するまでは鰹ダシ以外には考えられなかった茶碗蒸しですが、今では鶏、豚、魚色々と自由に楽しんでいます。
そして普段は中国風に具は入れません。
その方がダシの味が濁らずに卵とダシの合わさった優しい味をじっくりと楽しめるのです。ほわほわの食感も具がないからこそです。
百合根は香りが強くなく、そのほこほこねっとりな食感が茶碗蒸しにとても合う具材だと思います。
茶碗蒸しは消化が良いので夜遅い晩ご飯になっても身体への負担が少なく安眠の助けになりますね。
百合根入りならさらに安眠効果が高まるし、鶏肉ダシなら身体も温まりポカポカでよく眠れるでしょう。
身体が冷えてお布団の中に入ってもなかなか眠れない、夜中も寒くて目が覚める、、、なんて人は是非是非
百合根入りの鶏肉ダシの茶碗蒸しを! 大変なら、百合根が美味しいこの季節にぜひ百合根入りの骨つき鶏肉スープとかだけでも作ってみて下さい。
我が家には百合根があと半個残っています。数日中に茶碗蒸しにしてこの冬最後の百合根を楽しみたいと思います。











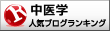


 と言うワケで我が家のウナギ日和はもう少し先に
と言うワケで我が家のウナギ日和はもう少し先に
 がコッテリした食べ物が好きなので、冷凍庫には“たまのご馳走”と称したコッテリ食材(いくら、カラスミ等)がたくさん眠っているのです。それ以上増やしたくないので…
がコッテリした食べ物が好きなので、冷凍庫には“たまのご馳走”と称したコッテリ食材(いくら、カラスミ等)がたくさん眠っているのです。それ以上増やしたくないので…
 。スーパーをマメにチェックする暇は無いし、宅配では鮮魚は扱ってないし、、、あきらめてもらおうかと思っていたのですが、ちょうど所用で出かけた先に美味しいお魚屋さんがあることを思い出し、帰りによってみると
。スーパーをマメにチェックする暇は無いし、宅配では鮮魚は扱ってないし、、、あきらめてもらおうかと思っていたのですが、ちょうど所用で出かけた先に美味しいお魚屋さんがあることを思い出し、帰りによってみると

 に冷えたビールを2本(350ml×2)飲みます。
に冷えたビールを2本(350ml×2)飲みます。 下痢 しやすい体質なのにねぇ(たぶんそういう生活の積み重ねの結果なんだろうケド)
下痢 しやすい体質なのにねぇ(たぶんそういう生活の積み重ねの結果なんだろうケド)
 って思うと、「ああ、日本人にうまれて良かった~」って思います。
って思うと、「ああ、日本人にうまれて良かった~」って思います。


 なのですが、大黒柱様はただただお酒を飲んで楽しくワイワイやるだけ。
なのですが、大黒柱様はただただお酒を飲んで楽しくワイワイやるだけ。
 」ってくらい飲んじゃいます。
」ってくらい飲んじゃいます。 」なんて苦しんでます。
」なんて苦しんでます。



 (たまに一日2~3個食べる程度なら問題ないと思います)
(たまに一日2~3個食べる程度なら問題ないと思います) との事ですのでよっぽど食べ過ぎない限り問題ないと思われますけど、、、
との事ですのでよっぽど食べ過ぎない限り問題ないと思われますけど、、、 しちゃうんです。
しちゃうんです。
 と思って食べています。
と思って食べています。

 」と興奮して聞いたくらいですから
」と興奮して聞いたくらいですから

 」って言うよりは「作りたい!
」って言うよりは「作りたい!



 と堪忍袋の緒が切れました。
と堪忍袋の緒が切れました。
 ウナギ:ウナギ目ウナギ科 となっていて、タウナギ:タウナギ目タウナギ科 と言う事です。タウナギのヒレは退化していて、胸ヒレ腹ヒレは無く、エラも退化しているので空気呼吸を行わないと窒息してしまうそうです。
ウナギ:ウナギ目ウナギ科 となっていて、タウナギ:タウナギ目タウナギ科 と言う事です。タウナギのヒレは退化していて、胸ヒレ腹ヒレは無く、エラも退化しているので空気呼吸を行わないと窒息してしまうそうです。



