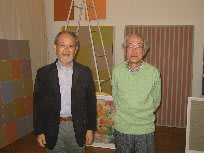生活の友社の『美術の窓』は作家や画廊に人気のある美術雑誌としてよく知られているが、創刊25周年を機に新たに『アート・コレクター』なる雑誌をを発刊した。編集・発行主幹の一井建二氏の挨拶文によれば、“コレクターのパートナーとしての美術雑誌”をめざすのだという。これは実に意味深いことである。
日本における美術の問題はそれが一部の人たちのものになっていて、ごく普通の人々が埒外に置かれていることである。そもそも美術業界というところは、作家と画商など供給者側とこれを支える美術評論家などによる閉鎖的な世界になっている。美術イベントの表舞台にいるのはこれら供給者側のプロばかりで、鑑賞者ないしコレクターのことは意識されていない。我々企業で仕事をしてきた人間からすると顧客重視は当たり前であるが、この業界は一向に変わろうとしない。勿論、画商にとって顧客は大事には違いないが、大事にしているのは資産家コレクターと一部のマニアコレクターというのが本当のところだ。全ての画廊がそうだというわけではないが、これではとても文化芸術の担い手とはいえない。特に現代アートのジャンルはもっとファンの底辺を広げるべきであったのに、そうなっていないところに問題がある。
私が5年前に立ち上げた『アートNPO推進ネットワーク』は、こういう壁を突き破りたかったからであり、美術館や美術評論家、画商などが手をこまねいている、ごく普通の人々にとっての“日常生活のなかの生きがい実現”、“生きる上での文化芸術の価値認識”のためのアート市民運動であった。
そういう意味で、この新しい雑誌がコレクターのパートナー誌として、コレクターの視点に立った編集を意識しているように見え、楽しみだ。この雑誌の企画担責任者は編集の細川英一氏であるが、企画段階でちょっと相談があり、「今、美術界にはコレクターの視点が必要なのではないですか」というタイトルの座談会に登場させていただいた。感謝!・・今後の『アート・コレクター』誌のご発展を祈りたい。(山下)

*写真は山下、御子柴、伊藤三人の座談会記事掲載ページ
日本における美術の問題はそれが一部の人たちのものになっていて、ごく普通の人々が埒外に置かれていることである。そもそも美術業界というところは、作家と画商など供給者側とこれを支える美術評論家などによる閉鎖的な世界になっている。美術イベントの表舞台にいるのはこれら供給者側のプロばかりで、鑑賞者ないしコレクターのことは意識されていない。我々企業で仕事をしてきた人間からすると顧客重視は当たり前であるが、この業界は一向に変わろうとしない。勿論、画商にとって顧客は大事には違いないが、大事にしているのは資産家コレクターと一部のマニアコレクターというのが本当のところだ。全ての画廊がそうだというわけではないが、これではとても文化芸術の担い手とはいえない。特に現代アートのジャンルはもっとファンの底辺を広げるべきであったのに、そうなっていないところに問題がある。
私が5年前に立ち上げた『アートNPO推進ネットワーク』は、こういう壁を突き破りたかったからであり、美術館や美術評論家、画商などが手をこまねいている、ごく普通の人々にとっての“日常生活のなかの生きがい実現”、“生きる上での文化芸術の価値認識”のためのアート市民運動であった。
そういう意味で、この新しい雑誌がコレクターのパートナー誌として、コレクターの視点に立った編集を意識しているように見え、楽しみだ。この雑誌の企画担責任者は編集の細川英一氏であるが、企画段階でちょっと相談があり、「今、美術界にはコレクターの視点が必要なのではないですか」というタイトルの座談会に登場させていただいた。感謝!・・今後の『アート・コレクター』誌のご発展を祈りたい。(山下)

*写真は山下、御子柴、伊藤三人の座談会記事掲載ページ