当人相応の要求(16)
例えば、こうである。
疑いをかけられたことに対する結果としての動揺。それから、仲間うちでの理解できる言語と、それぞれの自立。そのことを、一人の人間として小さく扱うのか、国家の問題として捉えるべきか。
1894年のフランスに住むドレフュスという人物に起こった事柄から開始する。情報というものが今より大事であったか、どうかは分からない。ただ、疑われるべき(外部に情報が洩れてしまう)ことがあって、その犯人をつきとめたいという衝動も人間にはあり(往々にしてみつからないことも多々あり)、その二つの決着点にドレフュスさんという人が表れる。国籍を抜きにした所属する人種という問題。そう、かのドレフュスさんはユダヤ人。金銭的に有利にあった(なぜ、その民族はそのことに優れているのだろう)支配というか状況の下で、貧しい人たちの嫉みも前提にある。しかし、本当の犯人より、もろもろの権力のここちよい解決策としての犯人像は、ドレフュスが引き受けることになる。もちろん、当人や家族のないがしろにされた気持ちは無視することとして。ゾラという作家もそのことを、不正は不正という当然の帰結としてペンで太刀打ちするが、その抵抗もむなしく有罪というハンコを押され解決。
彼は、思う。小さな疑いをかけられることは生きていく限りあるということを。そして、問題を生み出した人たちは、その疑いを解決しようなどと、ほとんど思っていないことを。
自立の問題に話を移す。あきらめてしまうことと、それを希望のつぼみにすりかえること。テーオドール・へルツルという人物が現れる。とりあえず自分たちの安住できる土地が必要だろう、との気持ちを、その事件を新聞記者として追いかけるうちに見出していくのだろう。自分の憎まれている民族(言い過ぎか?)誤解を受けやすい人々。1860年生まれなので、事件当時は34歳ということになる。
小さなこととして自分の感情に引きずり込むため、彼も自分の親元での生活ではなく、自分の小さな国家、簡単にいえば一人暮らしのこととして捉えようと考える。なにも干渉されないで、我が法律を作ること。法律があれば条文もある。それを読み上げる言語もある。
言語の問題に移行する。集団としての流行り言葉。仲間うちでの、くだけた、それでいて寛いだ会話。
エリエゼル・ベン・イェフダーという人物を、ここで登場させる。リトアニアという国から、パレスチナに移住し、ヘブライ語を現代に取り戻す。本人がどこまで本気であったのか、それとも、言語を習ったり話す能力が、ひときわ好きとか、向いていたのかどうかも分からない。ただ、その人物は、埋もれていた遺跡を掘り起こすように、言語のまわりについていたほこりを取り除き、博物館のなかに眠らせるのでもなく、生きたものとして流通させる。
その人の息子は、その言語で幼いころから教育させる。ほぼ2000年を経ての、その言語を母国語にした人物が産まれる。奇跡のような結論。
この物語の彼は、体感的にはこれらのことがらについて何事も理解していないし、判断もできないような状況でいる。しかし、呪われたような辛い運命は、「質屋」というニューヨークを舞台にした映画で、一端でも知ろうとする。その救いのないようなクインシー・ジョーンズの映画音楽を足がかりにして。
言語に戻る。バスク語というものがあるらしい。フランスとスペインに挟まれた山沿いの場所。そこの人々は、その両隣の大国と、自分の言語を持たされてしまうらしい。必要上と信念上か。だが、そのバスク語というものは、世界中のどの言語とも似ていないということになっている。彼は、考えをめぐらす。そんなことがありえるのだろうか。
それから、疑いをかけられないように、自分の小さな王国を築くこと。仲間うちだけでも、理解できるような言語をもつこと。しかし、どの面においても難しい。ひとからいろいろ言われ、生き方を注意されること自体が、生きている証のようにも思えてくる。
彼は、黙る。でも、こころの奥で理解しあえる関係と、その通信手段としての言語の投げ合いを強固なものとして、育む共同体や、共同生活を夢想する。1948年5月14日。イスラエルという国家が中東に誕生する。それで、物事が丸く収まったかどうかは、他の人々のほうが良く知っているだろう。
例えば、こうである。
疑いをかけられたことに対する結果としての動揺。それから、仲間うちでの理解できる言語と、それぞれの自立。そのことを、一人の人間として小さく扱うのか、国家の問題として捉えるべきか。
1894年のフランスに住むドレフュスという人物に起こった事柄から開始する。情報というものが今より大事であったか、どうかは分からない。ただ、疑われるべき(外部に情報が洩れてしまう)ことがあって、その犯人をつきとめたいという衝動も人間にはあり(往々にしてみつからないことも多々あり)、その二つの決着点にドレフュスさんという人が表れる。国籍を抜きにした所属する人種という問題。そう、かのドレフュスさんはユダヤ人。金銭的に有利にあった(なぜ、その民族はそのことに優れているのだろう)支配というか状況の下で、貧しい人たちの嫉みも前提にある。しかし、本当の犯人より、もろもろの権力のここちよい解決策としての犯人像は、ドレフュスが引き受けることになる。もちろん、当人や家族のないがしろにされた気持ちは無視することとして。ゾラという作家もそのことを、不正は不正という当然の帰結としてペンで太刀打ちするが、その抵抗もむなしく有罪というハンコを押され解決。
彼は、思う。小さな疑いをかけられることは生きていく限りあるということを。そして、問題を生み出した人たちは、その疑いを解決しようなどと、ほとんど思っていないことを。
自立の問題に話を移す。あきらめてしまうことと、それを希望のつぼみにすりかえること。テーオドール・へルツルという人物が現れる。とりあえず自分たちの安住できる土地が必要だろう、との気持ちを、その事件を新聞記者として追いかけるうちに見出していくのだろう。自分の憎まれている民族(言い過ぎか?)誤解を受けやすい人々。1860年生まれなので、事件当時は34歳ということになる。
小さなこととして自分の感情に引きずり込むため、彼も自分の親元での生活ではなく、自分の小さな国家、簡単にいえば一人暮らしのこととして捉えようと考える。なにも干渉されないで、我が法律を作ること。法律があれば条文もある。それを読み上げる言語もある。
言語の問題に移行する。集団としての流行り言葉。仲間うちでの、くだけた、それでいて寛いだ会話。
エリエゼル・ベン・イェフダーという人物を、ここで登場させる。リトアニアという国から、パレスチナに移住し、ヘブライ語を現代に取り戻す。本人がどこまで本気であったのか、それとも、言語を習ったり話す能力が、ひときわ好きとか、向いていたのかどうかも分からない。ただ、その人物は、埋もれていた遺跡を掘り起こすように、言語のまわりについていたほこりを取り除き、博物館のなかに眠らせるのでもなく、生きたものとして流通させる。
その人の息子は、その言語で幼いころから教育させる。ほぼ2000年を経ての、その言語を母国語にした人物が産まれる。奇跡のような結論。
この物語の彼は、体感的にはこれらのことがらについて何事も理解していないし、判断もできないような状況でいる。しかし、呪われたような辛い運命は、「質屋」というニューヨークを舞台にした映画で、一端でも知ろうとする。その救いのないようなクインシー・ジョーンズの映画音楽を足がかりにして。
言語に戻る。バスク語というものがあるらしい。フランスとスペインに挟まれた山沿いの場所。そこの人々は、その両隣の大国と、自分の言語を持たされてしまうらしい。必要上と信念上か。だが、そのバスク語というものは、世界中のどの言語とも似ていないということになっている。彼は、考えをめぐらす。そんなことがありえるのだろうか。
それから、疑いをかけられないように、自分の小さな王国を築くこと。仲間うちだけでも、理解できるような言語をもつこと。しかし、どの面においても難しい。ひとからいろいろ言われ、生き方を注意されること自体が、生きている証のようにも思えてくる。
彼は、黙る。でも、こころの奥で理解しあえる関係と、その通信手段としての言語の投げ合いを強固なものとして、育む共同体や、共同生活を夢想する。1948年5月14日。イスラエルという国家が中東に誕生する。それで、物事が丸く収まったかどうかは、他の人々のほうが良く知っているだろう。










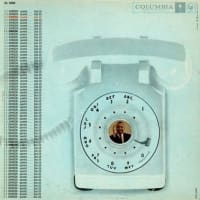


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます