日本人は独自の『笑い』を持った民族である。
西欧人にとって笑いとは可笑しいか、相手を侮蔑する時以外には発せられない。
しかし、日本人は照れくさい時にも笑うし、相手を拒否する時にも笑う。
「顔で笑って、心で泣いて」というように、悲しいときでさえ笑うことがある。
ジャパニーズ・スマイルと言われ、「日本人は無表情か、薄ら笑いを浮かべているかのどちらかだ」と表現されるように、あまり評判のいいものではない。
では、どうしてこのような笑いが発生したかというと、日本人は古来、笑いの中には邪悪なものを追い払う力がある、と思っていたからである。
たとえば、村の中で悪い行いをした者がいると、悪い行為をしたその本人が悪いのではなく、邪悪な霊がその人の悪い行為を行わせたと考えた。
その時、村人は、悪い行為をした者を取り囲んで嘲笑した。笑いにより、邪悪な霊を取り除こうとしたのである。
時代が下ると、邪悪な霊を追い払う、という儀式的な面は忘れられ、「笑いものにされる」といった表現に見られるように、マイナスのイメージだけが残るようになる。
今でも神事の際には「笑い祭」などが全国に伝わっているが、元来、笑いは宗教的なものであった。
その笑いは、神事や民俗芸能には伝承されていたが、落語としてきちっとした形態を帯びるようになるのは、寛政の頃である。
それ以前にも、辻話として、落語の萌芽は芽生えていた。
延宝年間((1673~1680年)から元禄にかけて、京に露五郎兵衛、大坂で米沢彦八、江戸で鹿野武左衛門が現れた。
三人とも非常な人気を博したが、現在も伝わる『寿限無』は彦八の考案である。
一方、他のふたりよりやや遅れて現れた武左衛門は、他愛もない話を書いたに過ぎないが、評判の大きさから幕府から咎めを受け、伊豆大島に6年間に亘り流罪になっている。
寛政に入ると、江戸では三遊亭可楽と三遊亭円生、上方では桂文治が現れた。
この三人が落語の祖といってよいだろう。
文化・文政期になると、三遊亭円朝、柳家小さんといった現在に残るビッグネームも次々に登場している。
その後、天保期には水野忠邦の改革により、寄席が大激減させられるという打撃を受けるが、改革が終わるとそぞろ復活し始め、明治に至る。
ちなみに、この天保期、寄席を潰すことに大反対したのが遠山の金さんこと、遠山左衛門丞であった。
日本人の歴史(樋口清之)講談社
↓ よろしかったら、クリックお願い致します。
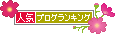
西欧人にとって笑いとは可笑しいか、相手を侮蔑する時以外には発せられない。
しかし、日本人は照れくさい時にも笑うし、相手を拒否する時にも笑う。
「顔で笑って、心で泣いて」というように、悲しいときでさえ笑うことがある。
ジャパニーズ・スマイルと言われ、「日本人は無表情か、薄ら笑いを浮かべているかのどちらかだ」と表現されるように、あまり評判のいいものではない。
では、どうしてこのような笑いが発生したかというと、日本人は古来、笑いの中には邪悪なものを追い払う力がある、と思っていたからである。
たとえば、村の中で悪い行いをした者がいると、悪い行為をしたその本人が悪いのではなく、邪悪な霊がその人の悪い行為を行わせたと考えた。
その時、村人は、悪い行為をした者を取り囲んで嘲笑した。笑いにより、邪悪な霊を取り除こうとしたのである。
時代が下ると、邪悪な霊を追い払う、という儀式的な面は忘れられ、「笑いものにされる」といった表現に見られるように、マイナスのイメージだけが残るようになる。
今でも神事の際には「笑い祭」などが全国に伝わっているが、元来、笑いは宗教的なものであった。
その笑いは、神事や民俗芸能には伝承されていたが、落語としてきちっとした形態を帯びるようになるのは、寛政の頃である。
それ以前にも、辻話として、落語の萌芽は芽生えていた。
延宝年間((1673~1680年)から元禄にかけて、京に露五郎兵衛、大坂で米沢彦八、江戸で鹿野武左衛門が現れた。
三人とも非常な人気を博したが、現在も伝わる『寿限無』は彦八の考案である。
一方、他のふたりよりやや遅れて現れた武左衛門は、他愛もない話を書いたに過ぎないが、評判の大きさから幕府から咎めを受け、伊豆大島に6年間に亘り流罪になっている。
寛政に入ると、江戸では三遊亭可楽と三遊亭円生、上方では桂文治が現れた。
この三人が落語の祖といってよいだろう。
文化・文政期になると、三遊亭円朝、柳家小さんといった現在に残るビッグネームも次々に登場している。
その後、天保期には水野忠邦の改革により、寄席が大激減させられるという打撃を受けるが、改革が終わるとそぞろ復活し始め、明治に至る。
ちなみに、この天保期、寄席を潰すことに大反対したのが遠山の金さんこと、遠山左衛門丞であった。
日本人の歴史(樋口清之)講談社
↓ よろしかったら、クリックお願い致します。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます