丁髷(ちょんまげ)は、兜を被ったときに頭頂部が蒸れないようにとの工夫から生まれた髪型だった。
踊り字のゝ(ちょん)に似ているから付けられたと言う。
踊り字とは、「学問のすゝめ」のように繰り返しに使われる記号だ。
ただ、「ゝ髷」では字面が悪いので「丁髷」の字が充てられるようになった。
先日、磯田道史氏の「歴史の愉しみ方」を読んでいたら、この丁髷に関する興味深い記事が載っていた。
丁髷が発生した戦国時代では、頭の前部、つまり月代に当たる部分の髪の毛は刃物で剃らないで、抜いていたというのだ。
「慶長見聞集」には「黒血流れて物すさまじ」との記述があるようだが、これでは我慢大会だ。
剃るようになったのは、秀吉以降の天正期以降だというのだが、織田信長なども、ヒーヒー言いながら、毛を抜いていたのだろうか。
丁髷を結う行為は戦闘の準備行為であり、主君への忠誠を示す姿勢でもあった。
であるから、丁髷を結わないのは、主君に対する不忠であった。
磯田氏は「彦根往古ノ聞書」を資料として、江戸初期、丁髷を結わないで登城した武士についての記述を行っている。
それによると、剣豪の血を引く上泉権左衛門という武士が丁髷を結わず、長髪で登城したところ、彦根藩主(井伊直孝)に咎められた。
権左衛門は「拙者は髪にて御奉公はつかまつらず」と反論したというが、この理屈に藩主は激怒し、閉門とさせられた。
彦根藩では、その後、ふたりが長髪の咎を負い閉門。
もうひとり、松井七左衛門という藩士は、丁髷を糸で結わず藁で結ったため、処分されている。
なんとなく、この辺りは管理社会へ移行する際の見せしめ的な要素を感じるが、現代社会でも普通の会社で、金八先生のような髪型は認められてはいないのだから、同じようなものだ。
ひげについても、江戸時代では幕府から禁止令が出ている。
明治以降、ひげを生やす政治家が多かったのも、禁止令への反感もあったようだ。
↓ よろしかったら、クリックお願いします!!

人気ブログランキングへ

にほんブログ村
<iframe src="http://rcm-fe.amazon-adsystem.com/e/cm?t=tadious-22&o=9&p=8&l=as1&asins=4121021894&ref=tf_til&fc1=000000&IS2=1<1=_blank&m=amazon&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>


踊り字のゝ(ちょん)に似ているから付けられたと言う。
踊り字とは、「学問のすゝめ」のように繰り返しに使われる記号だ。
ただ、「ゝ髷」では字面が悪いので「丁髷」の字が充てられるようになった。
先日、磯田道史氏の「歴史の愉しみ方」を読んでいたら、この丁髷に関する興味深い記事が載っていた。
丁髷が発生した戦国時代では、頭の前部、つまり月代に当たる部分の髪の毛は刃物で剃らないで、抜いていたというのだ。
「慶長見聞集」には「黒血流れて物すさまじ」との記述があるようだが、これでは我慢大会だ。
剃るようになったのは、秀吉以降の天正期以降だというのだが、織田信長なども、ヒーヒー言いながら、毛を抜いていたのだろうか。
丁髷を結う行為は戦闘の準備行為であり、主君への忠誠を示す姿勢でもあった。
であるから、丁髷を結わないのは、主君に対する不忠であった。
磯田氏は「彦根往古ノ聞書」を資料として、江戸初期、丁髷を結わないで登城した武士についての記述を行っている。
それによると、剣豪の血を引く上泉権左衛門という武士が丁髷を結わず、長髪で登城したところ、彦根藩主(井伊直孝)に咎められた。
権左衛門は「拙者は髪にて御奉公はつかまつらず」と反論したというが、この理屈に藩主は激怒し、閉門とさせられた。
彦根藩では、その後、ふたりが長髪の咎を負い閉門。
もうひとり、松井七左衛門という藩士は、丁髷を糸で結わず藁で結ったため、処分されている。
なんとなく、この辺りは管理社会へ移行する際の見せしめ的な要素を感じるが、現代社会でも普通の会社で、金八先生のような髪型は認められてはいないのだから、同じようなものだ。
ひげについても、江戸時代では幕府から禁止令が出ている。
明治以降、ひげを生やす政治家が多かったのも、禁止令への反感もあったようだ。
↓ よろしかったら、クリックお願いします!!

人気ブログランキングへ
にほんブログ村
<iframe src="http://rcm-fe.amazon-adsystem.com/e/cm?t=tadious-22&o=9&p=8&l=as1&asins=4121021894&ref=tf_til&fc1=000000&IS2=1<1=_blank&m=amazon&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>










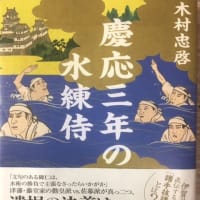
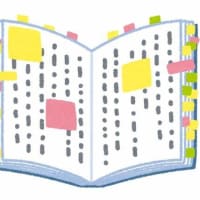
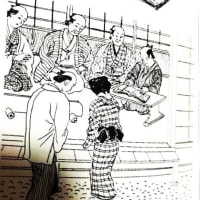
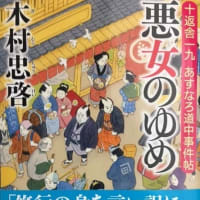
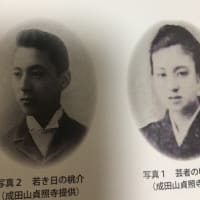

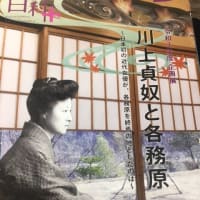
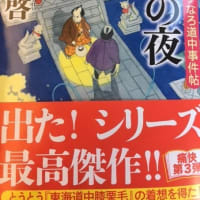
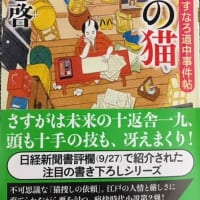
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます