遊郭の吉原は「江戸のテーマパーク」という一文に出くわした。
吉原は、田舎から出てきた者が必ず見物に行くような憧れの場所であった。
灯りが高価であった江戸時代にあって、夜間でも煌々と焚かれた灯によって不夜城であり、花形花魁は錦絵という、いわばブロマイドによって更に名が広まった。
江戸の二大悪所と言われた歌舞伎にも吉原での出来事は盛んに取り上げられ、吉原は現代にたとえたなら芸能界のような趣を呈していた。
だから、吉原を「江戸のテーマパーク」と呼ぶ言い方があるのだろうが、吉原が人身売買によって成立した売春街であるという事実を忘れてはならない。
江戸研究の大家である石川英輔氏は、豊かな現代でさえ、春を売って楽に金を稼ごうとする女性が多いとし、
「人間の本質がそれほど容易に変わらない以上、江戸時代でも自分から進んで遊女になった人がかなりいたはずだと思うのが常識であろう」(雑学 大江戸庶民事情・講談社文庫)
と書いているが、これは行き過ぎである。
吉原がどんなにきらびやかにみえても、それは虚飾でしかない。中身はもっとどろどろしたものである。
前置きが長くなったが、吉原の遊女にも厳格な格付けがあった。
高級な遊女を花魁(おいらん)と呼ぶのをよく耳にするが、花魁は格を示す言葉ではない。
吉原は、一回移転しているので、移転する前を元吉原、移転後を新吉原(または単に吉原)と区別するが、元吉原が出来上がった当時は
①端(はし)女郎 → 格子(こうし)女郎 → 太夫
という格付けであった。
それが、元吉原後期には、
②切見世(きりみせ) → 端女郎 → 局(つぼね)女郎 → 格子女郎 → 太夫
の5段階となる。
移転後の格付けは、
③切見世 → 局 → 散茶 → 格子 → 太夫
となり、さらに、
④切見世 → 局 → 梅茶 → 散茶 → 格子 → 太夫
となる。
この中の散茶というのは、振らないでも出る挽いた茶のことであり、「客を振らない」に引っ掛けた言葉である。
さらに、挽茶を薄めたという洒落から「梅茶」なる格も生まれた。
ここまで続いた最高位の太夫とは、もとは舞台芸人の統領の呼び名であったが、時代が下ると吉原でも用いられるようになった。
太夫の呼び名は有名なので、江戸末期まで存在したかというと、さにあらず。吉原が移転した際には、20~30名ほどの太夫がいたとされるが、安永九年(1780年)に太夫格の女郎はいなくなったと言う。
これは、吉原の上客が武士階層から商人層に移行したという理由もある。商人は格式の張る太夫よりも、もっと実利ある女郎を求めたのである。
太夫がいなくなってからの格はそれまでのものとは、かなり変わる。
⑤切見世 → 部屋持 → 座敷持 → 附廻 → 昼三 → 呼出
太夫に代わり最高位となった呼び出しは、客の呼び出しがあるまで自分の部屋で待機し、呼び出しがかかると客の待っている茶屋まで行く遊女である。
昼三は、昼でも夜でも、揚げ代が三分かかる遊女。附廻とは、昼二の別名のとおり、揚げ代が二分の遊女。
座敷持ちは居室のほかに座敷、つまり2ルーム持っている遊女で、ここまでが上級とされた。
それ以下の遊女の揚げ代はピンキリで、切見世だとチョンの間(10分)百文という相場もあった。
もっとも、10分ではあまりにも短いため、あらかじめ客は2倍か、3倍の金を払うことが多かったという。
呼出の揚げ代は、1両1分=四千四百文であるから、切見世の揚げ代が仮に二百文とすると、二十倍の格差があることになる。
江戸300年 吉原のしきたり 渡辺憲司 青春出版社
吉原入門 永井義男 学研
↓ よろしかったら、クリックお願いします。

P.S.クリスマス・イブに書いていたのかあ。7年前はどんなクリスマス・イブだったんだろう?
吉原は、田舎から出てきた者が必ず見物に行くような憧れの場所であった。
灯りが高価であった江戸時代にあって、夜間でも煌々と焚かれた灯によって不夜城であり、花形花魁は錦絵という、いわばブロマイドによって更に名が広まった。
江戸の二大悪所と言われた歌舞伎にも吉原での出来事は盛んに取り上げられ、吉原は現代にたとえたなら芸能界のような趣を呈していた。
だから、吉原を「江戸のテーマパーク」と呼ぶ言い方があるのだろうが、吉原が人身売買によって成立した売春街であるという事実を忘れてはならない。
江戸研究の大家である石川英輔氏は、豊かな現代でさえ、春を売って楽に金を稼ごうとする女性が多いとし、
「人間の本質がそれほど容易に変わらない以上、江戸時代でも自分から進んで遊女になった人がかなりいたはずだと思うのが常識であろう」(雑学 大江戸庶民事情・講談社文庫)
と書いているが、これは行き過ぎである。
吉原がどんなにきらびやかにみえても、それは虚飾でしかない。中身はもっとどろどろしたものである。
前置きが長くなったが、吉原の遊女にも厳格な格付けがあった。
高級な遊女を花魁(おいらん)と呼ぶのをよく耳にするが、花魁は格を示す言葉ではない。
吉原は、一回移転しているので、移転する前を元吉原、移転後を新吉原(または単に吉原)と区別するが、元吉原が出来上がった当時は
①端(はし)女郎 → 格子(こうし)女郎 → 太夫
という格付けであった。
それが、元吉原後期には、
②切見世(きりみせ) → 端女郎 → 局(つぼね)女郎 → 格子女郎 → 太夫
の5段階となる。
移転後の格付けは、
③切見世 → 局 → 散茶 → 格子 → 太夫
となり、さらに、
④切見世 → 局 → 梅茶 → 散茶 → 格子 → 太夫
となる。
この中の散茶というのは、振らないでも出る挽いた茶のことであり、「客を振らない」に引っ掛けた言葉である。
さらに、挽茶を薄めたという洒落から「梅茶」なる格も生まれた。
ここまで続いた最高位の太夫とは、もとは舞台芸人の統領の呼び名であったが、時代が下ると吉原でも用いられるようになった。
太夫の呼び名は有名なので、江戸末期まで存在したかというと、さにあらず。吉原が移転した際には、20~30名ほどの太夫がいたとされるが、安永九年(1780年)に太夫格の女郎はいなくなったと言う。
これは、吉原の上客が武士階層から商人層に移行したという理由もある。商人は格式の張る太夫よりも、もっと実利ある女郎を求めたのである。
太夫がいなくなってからの格はそれまでのものとは、かなり変わる。
⑤切見世 → 部屋持 → 座敷持 → 附廻 → 昼三 → 呼出
太夫に代わり最高位となった呼び出しは、客の呼び出しがあるまで自分の部屋で待機し、呼び出しがかかると客の待っている茶屋まで行く遊女である。
昼三は、昼でも夜でも、揚げ代が三分かかる遊女。附廻とは、昼二の別名のとおり、揚げ代が二分の遊女。
座敷持ちは居室のほかに座敷、つまり2ルーム持っている遊女で、ここまでが上級とされた。
それ以下の遊女の揚げ代はピンキリで、切見世だとチョンの間(10分)百文という相場もあった。
もっとも、10分ではあまりにも短いため、あらかじめ客は2倍か、3倍の金を払うことが多かったという。
呼出の揚げ代は、1両1分=四千四百文であるから、切見世の揚げ代が仮に二百文とすると、二十倍の格差があることになる。
江戸300年 吉原のしきたり 渡辺憲司 青春出版社
吉原入門 永井義男 学研
↓ よろしかったら、クリックお願いします。

P.S.クリスマス・イブに書いていたのかあ。7年前はどんなクリスマス・イブだったんだろう?










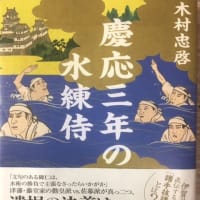
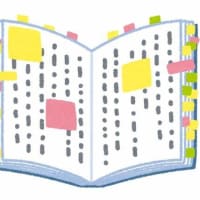
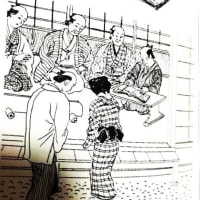
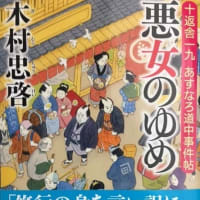
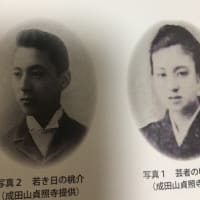

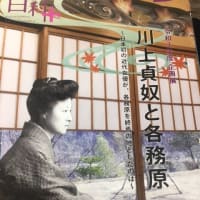
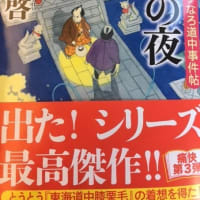
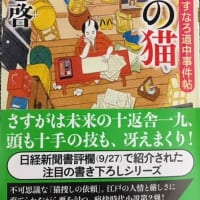
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます